令和2年度消費者団体等との意見交換会(鳥取県)の概要
|
中国四国農政局では、消費者団体等との意見交換会を鳥取市で開催しました。 |
1. 開催日時、場所
令和2年7月16日(木曜日) 13時00分~15時10分
鳥取第1地方合同庁舎 2階 共用会議室
2. 中国四国農政局からの情報提供
(1)消費者や企業等による農林水産業の支援の取組について
(2)CSF(豚熱)及びASF(アフリカ豚熱)について
(3)ジビエの安全性確保の取組について
(4)地場産農林水産物の消費の推進について
3. 出席者(順不同、敬称略)
- 公益財団法人 鳥取県学校給食会
- 特定非営利活動法人 コミュニティネット山陰
- 鳥取市消費者団体連絡協議会
- 鳥取市連合婦人会
- 安全食品を守る会
- 鳥取県食生活改善推進員連絡協議会
- JAとっとり女性協議会
- とっとり県消費者の会
- 公益社団法人 鳥取県栄養士会
- 鳥取県生活協同組合連合会
| 消費者団体等 | 10名 |
| 農政局 | 6名 |
| 出席者計 | 16名 |
4. 出席者からの主な意見・要望・質問等
- 同じ野菜で自県産と他県産が店の棚に並んでいた場合、地元の商品を必ず選んでいるが、選ぶ時には、安い方が良いが、新鮮さとメーカーを必ず見るなど、とにかく安心な物を選んでいる。
- スーパーに地元産と他県産があれば、迷わず地元産を求めるが、スーパーには置いていないことが多い。高齢者には、JAの産直店に行けない方もたくさんおり、地元のスーパーの方が近く、歩いて行ける人もいることから、スーパーにも地元産を置いて欲しい。また、以前に県の事業でやっていたように、表示とかノボリ旗により、ここには地元産があるということを消費者に分かるようにして欲しい。
- 今回のコロナウイルス感染症の発生は、地産地消を促進する良い機会になるのではないか。足りないのは広報活動であり、推進する際には、その活動にも力を入れて欲しい。
- コロナ禍で、人や物の動きが制限されていることと併せて、温暖化等により、日本だけでなく世界全体で食料が逼迫している中で、改めて、地産地消、地場産業、産直等の取組の要請が高まっており、消費者や企業、生産者が一緒になって食料の消費を高めていくことが大切であると考えている。
- 学校給食は加工した物を扱うことが多いが、生産者団体等から食材の申出があっても、地元に加工場がないのが課題であり、何らかの施策があれば良いと考えている。
- 当会では、冷凍野菜をメインにバラ凍結(IQF:Individual Quick Freezing)をやっているが、給食の調理場でもかなり重宝されており、家庭向けとしても保存も便利で使いやすいことから、この技術を使って、生産者と連携した商品開発や県内産の物を県内で加工するといった体制が取れれば、市場にも出て行くものと考えている。
- 食料自給率について、県ごとに目標を設定し、目標を達成するために、食品ロスの削減や補助金による生産コストの低減のほか、学校給食における地元産比率の向上等、県民運動として地産地消を進めていくことが必要ではないかと考えている。
- 有機野菜や手作りのケチャップ、焼き肉のタレを自分で作っているが、そういう物が安心・安全であることを、地道ではあるが、娘や娘の友人、若い方に伝えている。
- 食品ロス削減について、高校生や大学生に啓発していく必要があるとの観点から、昨年、高校生と大学生を対象に、消費者に出せないようなB級食品を使った調理コンテスト大会を開催したが、曲がった食材でも、きちんと料理をすれば美味しくなることを参加者に考えて貰う良い機会になったと考えている。
- 現在、食育は、中学生や小学生とその保護者が対象であるが、そろそろ食事を自分でやらなければならない高校生をターゲットに啓発活動を行うことも大切であると考えている。
- ジビエの推進について、スーパーで開催された親子講習会でジビエ料理を試食した際、小さい子どもも食べて美味しかったと言っていた。費用がないと簡単には開催できないが、直接、食べて、話を聞けるような場があれば、もっとジビエが広がっていくのではないかと考えている。
- ジビエについて、安心・安全面のことは詳しく分からないが、料理の仕方によっては美味しいことから、ジビエとしての利用拡大の取組が鳥獣対策に役立っていければ良いと考えている。
- ジビエについて、肉の検査体制はできていると思うが、これだけ森林が荒れているのに鳥獣は何を食べているのか、消費者としては少し不安である。
- 農林水産業を持続するためには、行政がリーダーシップを取り、6次産業を興していく必要があると考えているが、地元で採れた物を地元で使う、そこに雇用が生まれる、地域作りもできるという関連性が政策的に少し弱いのではないか。
- 退職してからの農業が大半だと思うが、今は、米を作っても収入にならない。毎年、肥料は新しく開発されているが、以前に比べて価格が高く、機械も高価で費用がかかることから、国の政策として、日本全体ではなく、北海道や東北等の米作地帯の生産者と中国四国のような小規模な生産者の対策を個々に考えて欲しい。
- 農林水産業の後継者対策については、高校を卒業してから支援するのでは遅く、低年齢の時から、農業や漁業のすばらしさや地場産業の大切さを教えていくことが人材育成につながると考えている。
- 国や県、市において、担い手や新規就農者の対策が措置されているが、やはり、長続きせず、地元では1~2年で辞めてしまうのが現状である。スマート農業は良い取組だと思うが、北海道で行うものであり、地元では無理ではないかと考えている。
- スマート農業については、費用がかかると感じており、ドローン以外のAIなどもすごく良い物だとは分かるが、大規模でなければ収入が得られないのではないかと考えている。
5. その他(意見交換会写真等)
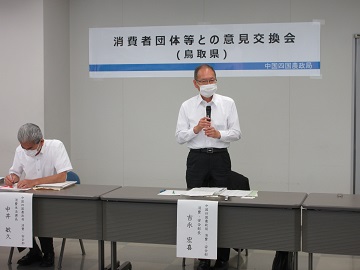 (吉永部長によるあいさつ) |
 (意見交換会の様子) |
お問合せ先
消費・安全部消費生活課
代表:086-224-4511(内線2322)
ダイヤルイン:086-224-9428




