令和4年度消費者団体等との意見交換会(高知県)の概要
|
中国四国農政局では、消費者団体等との意見交換会を高知市で開催しました。 |
1. 開催日時、場所
令和4年8月17日(水曜日) 13時40分~15時40分
高知地方合同庁舎 2階 会議室
2. テーマ
環境にやさしい持続可能な消費
3. 中国四国農政局からの情報提供
(1)第4次食育推進基本計画について
(2)みどりの食料システム戦略について
4. 出席者(順不同、敬称略)
- 有機農業生産者(有限会社大地と自然の恵み)
- 食育活動実践者(いただきます!ラボ)
- 高知県生活協同組合連合会
- 公益社団法人 高知県栄養士会
- 高知県食生活改善推進協議会
- 高知県漁協女性部連合協議会
| 出席者計 | 12名 |
| 消費者団体等 | 6名 |
| 農政局 | 6名 |
5. 取組紹介等
(1)有限会社大地と自然の恵み
大地と自然の恵みは、有機農業を始めて今年で40年になる。創業当時は有機農業と慣行農業を半々で行っていたが、結婚して子どもができたこと、自身が農薬にかぶれる体質だったことから、このままのやり方で農業を続けていくことに抵抗を感じるようになり、就農5年目で全ての圃場を有機に切り替え、今に至る。
当時は異端児扱いで周囲の農家との軋轢もあったが、有機農業で農作物を作るだけではなく、有機農業に取り組む中で、地域の自然環境や人とのつながりを考えることにつながれば良いと考えて、自社の理念をつくった。主たる販売先として、創業当時から有機農業専門又はオーガニックに特化した流通組合や共同仕入センターとお付き合いしている。
有機農業は、人と人との繋がり。有機JAS法があっても安心・安全が完全に担保されたわけではなく、作る人と、購入して使っていただく人との関係の上に成り立っている。それがなければ、次の世代に引き継ぐことが困難になると思っている。農業人口が減少し後継者不足と言われているが、作る人だけでなくそれを消費する人の後継者も、同時に育てていかなくてはいけない。
なぜ有機農業なのか、有機農産物が良いのか。消費者もモノだけを買うのではなく、モノの裏側にある環境や、人の思い、考えなどを議論する場があると良いと考えており、同じテーブルに着いて、同じ目線で、同じことを話していくことが大事。このような意見交換会の場はとてもありがたいが、やったという実績だけで終わらせることなく、今後も頻繁に行っていただきたい。
(2)いただきます!ラボ
「いただきます!ラボ」という屋号で活動していて、ラボラボ台所実験室という台所科学実験教室を展開している。管理栄養士であり、実験や化学に興味を持っていて、食を融合させたような形で、色の変化、形の変化を面白おかしく実験に落とし込んだ講座を行っている。
食にはもともと興味があったが、特に、家族ができ、子どもにちゃんとしたものを食べさせたいという気持ちが強くなって、食の情報収集をする機会が増えた。コミュニティに属して活動することで、たくさんの情報を得るようになったが、情報が偏っているのではないかと思い始めた。食の安全を突き詰めすぎると選択肢が狭くなったり、人間関係が制限されたり、息苦しいと感じ、特定のコミュニティに属するのはやめて、様々なルートからの情報収集を心がけるようになった。
本当に正しい情報かどうか判断するのはすごく難しい。コミュニケーションのとり方や情報の選び方、つかみ方が、今後、大事になっていくと思う。情報の選択が難しいと思う中で、自分なりに、食の情報を正しく分かりやすく発信していけたらと思う。ネットにもわかりやすい情報が掲載されているが、一般の人には見つけにくく、どうやったら消費者がアクセスできるかということも考えていきたい。
6. 出席者からの主な意見等
- コロナを契機に、消費者の中には、安全・安心、価格の安さのほかに、地域、社会貢献、持続可能な社会づくりに対する価値観が確実に高まっている。今までは、運動しないと社会参加できないという側面があったが、自分たちが利用することにより、消費行動を通じて、手頃に社会につながっていることを実感するという意識が出てきている。
- 子どもの頃から、食生活や食の選択について、正しい知識、情報に基づいて自ら管理したり、判断したりする能力を養うことが非常に重要と考えている。将来、賢い消費者となるために、学校での学習、学校給食での取り組みが大切である。
- 学校現場では、子どもにいろいろな視点で食べることの楽しさ、喜び、意義を伝えたり、家庭に給食便りなどを通じて日本型食生活の良さや意義を伝えたり、家庭で簡単に作ることができるレシピ提供を行ったりして、食べ慣れること、ひいては残食が少なくなるように努めている。
- 食品輸送に伴う環境負荷の低減に資することに加え、地場産物を使った学校給食を教材として、子どもたちに食文化の理解や感謝の心を持つよう指導している。地場産物を学校給食に使用することは非常に重要。
- みどりの食料システム戦略で有機農業を推進すると言われているが、できるかどうか疑問。そういう方向に進めていくのは小さい個人では難しく、国が旗振りをしていただけたら良いと思う。 社会的運動は大事。有機農法はいろいろ出ているが、それぞれバラバラでまとまっていないと感じる。団体をつくってまとまって一緒に活動できたらよいのでは。
- みどりの食料システム戦略を2050年までに達成するというが、あと30年しかない。目標は素晴らしいが、本当にできるのかどうか疑問。計画倒れになるのではないかと心配している。関係者だけでなく国民的に関心を高め、真剣度をもって取り組むことが必要。
- みどりの食料戦略システムを、実際にこれからどういうふうに事業として展開されていくのか、特に消費の部分を誰が啓発していくのか、予算の活用も含めて、わかりやすく 示してほしい。
- 今日の議題のような話を、一般の人に広め、理解してもらうことが大事。各省連携して、広報活動を強めてほしい。SNSの活用など工夫して、わかりやすく発信してほしい。
- 野菜を1日350g摂取しましょう、1日5皿、朝昼晩と食卓に載せましょうという啓発活動を行っている。コロナの感染拡大で活動ができなくなりさみしい思いをしているが、今後は地元に密着した活動の中から、環境にやさしい農業を応援する活動に繋げていきたい。
- 魚食普及活動に努めているが、海産物への関心が低下してきていると感じている。家庭で料理に使える時間が減っていて、加工品の魚を買うと割高になり、金額や手軽さから肉の方が食卓に上がる機会が多いと考えられる。魚を料理すると骨など食べられない部分が出るため、家庭で出るゴミを減らそうとする昨今の環境問題への風潮に反していることもその一因と考えている。
5. その他(意見交換会写真等)
 (意見交換会の様子) |
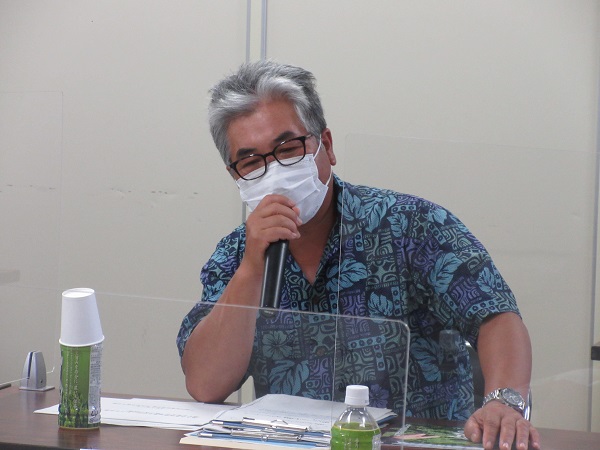 (有機農業に取り組む有限会社大地と自然の恵み 小田々様による取組紹介) |
 (食育活動に取り組むいただきます!ラボ 岡本様による取組紹介) |
お問合せ先
消費・安全部消費生活課
代表:086-224-4511(内線2322)
ダイヤルイン:086-224-9428
FAX番号:086-224-4530




