令和6年度消費者団体等との意見交換会(岡山県)の概要
|
中国四国農政局では、消費者団体等との意見交換会を岡山市で開催しました。 |
1. 開催日時、場所
令和6年6月4日(火曜日) 13時30分~15時35分
岡山第2合同庁舎10階 第10-AB会議室
2.行政からの情報提供
食品ロス削減取組説明及び容器包装事例の紹介について
3. 出席者(順不同、敬称略)
- 株式会社ハローズ(食品ロス削減取組事業者)
- 株式会社ケンジャミン・フランクリン(食品ロス削減取組事業者)
- 岡山県消費者団体連絡協議会
- 岡山県生活協同組合連合会
- 岡山県消費生活問題研究協議会
- 公益社団法人岡山県栄養士会
- 公益財団法人岡山県学校給食会
- 岡山県栄養改善協議会
- JA岡山県女性組織協議会
- 岡山市連合婦人会
| 出席者計 | 18名 |
| 食品ロス削減取組事業者 | 2名 |
| 消費者団体等 | 8名 |
| 農政局 | 8名 |
4.団体からの取組紹介
(1)株式会社ハローズ
日本のこども食堂は約9,000カ所あると言われているが、困窮しているこどもたちの3割位しか支援ができていないとされる。本当に必要な人に食料を届けるためには、コミュニティパントリー(公共食料庫)を日本で増やすことが必要である。このため、先進国英国の活動を見聞した。
あるコミュニティフリッジ(公共冷蔵庫)団体では、ボランティアが朝、食品販売店内から商品を軽トラックに積み、公民館のような建物に運ぶ。毎日ボランティア10人で400kgの商品を集荷し、2時間で約100人の人々に引き渡している。
提供側では、英国大手スーパーなど有力小売店のほとんどが行っていることもあって、コミュニティフリッジの団体数は260カ所に及ぶ。一方、日本では、コミュニティフリッジは31カ所程しか設立されていない。
日本の食品ロスの現状は、日本のスーパーマーケットから発生する食品ロスが60万トンであり、その半分を提供可能と仮定すれば、30万トン、円に換算すると3,000億円位がすべてのスーパーから提供できることになる。ハローズ1社では年間約300トン、約3億円を提供している。すべてのスーパーが協力すれば、提供量が増え、食品ロス削減につながり、コミュニティパントリーが増えていくのではないか。
そこで、ハローズは「支援を受ける団体が近隣の店舗で直接引き取る」フードバンクの新しいかたち「ハローズモデル」を開発・提唱した。ガソリン代も時間もかからない合理的な方法を全国拡大に向け懸命に取り組み、中国四国全県、近畿などに広がっている。
最後に、世界では、「善きサマリア人法」という法律がある。食べられる食品の提供に係る責任は、提供した方ではなく、もらった方の責任になるという提供側免責の法律である。米国、英国、豪州、仏国等の国であるが日本はない。一昨年ニュージーランドでこの法律ができたとたん、提供量が5倍になったという。日本も是非、消費者の皆さんの反対なく、法律ができることを願っている。法律が整備されれば、大手スーパーが協力し、コミュニティパントリーが増えていくものと期待している。
(2)株式会社ケンジャミン・フランクリン
岡山県吉備中央町で飲食店と買い物支援をしている。また、代表取締役は、NPO法人ジャパンハーベストでフードバンク活動を行いながら、岡山大学大学院で食品ロスをテーマとした研究に取り組み、さらに吉備中央町町議会議員を務めている。
国民が健康で豊かな食生活を送るためには、家庭レベルでの食品アクセスが十分に確保されている必要があるが、日々の移動販売で買い物弱者に会い、フードバンク活動で生活困窮者を目にしている。買い物弱者は、生鮮食料品店へたどり着けない方が2025年に598万人、総合スーパーになると814万人にもなると想定され、都市地域でも増加傾向になるといわれている。移動販売で出会った高齢者が、インスタント食品、巻寿司、天ぷらなど1週間分の食料品や日用品を手にすることで健康状態がなぜか改善したという例があるように、生活環境が整うことが健康面において非常に重要になっている。
また、フードレスキューの活動をしている。フードレスキューは、倉庫がなくても車と人がいればすぐに必要としている団体に届けられ、現在岡山、広島、香川、兵庫、東京など91の福祉施設等に配付している。障がい者であり生活困窮者でもあった方が一緒にフードレスキュー活動をしてくれることになり、生きがいを持って活動されている。
現在は、「人を育てる」をテーマに、ノウハウを伝え、仲間を増やすことに力を入れている。私たちにできることは、最寄りのスーパーが自分の家の冷蔵庫だと思えば買物の仕方から意識が変化していくと思う。
5.出席者からの主な意見・要望・質問等
〇食品ロス削減の取組の重要性に関する意見
- フードドライブを会員に持ちかけると管理しきれないくらい集荷できてしまい、人員不足の課題がある。できる範囲でやっていきたい。
- 家庭からの食品ロスを見直そうとこども食堂への提供やフードドライブに取り組んでいる。会合などの時、農家から作りすぎた野菜を提供してもらい、フードバンクに届けたり、取りに来てもらったりしている。果樹園にこどもを招待して持ち帰って食べてもらうこともしている。
- フードレスキューのような移動販売車は、昔よく回ってくれていた。今は街中でも高齢化が進み、買い物に行くことに困っている人がいる。行政に考えてもらうために地区の人にどれくらい困っているかをアンケート調査してみようと思う。
- かぼちゃは丸ごとのほうが日持するため、フードバンクから丸ごとと要望がある。さらに、農家に苗や種を配り、収穫時にこどもたちを呼んで収穫体験をするなど食育もあわせて取り組んでいる。
- 各地域で食品ロスやエコクッキングに関連した料理教室を行っている。また、冷蔵庫に貼り付けられるステッカーを食品ロス削減PR用にデザインを工夫して作っている。
- 販売サイドで困っていることに、賞味期限内にうまく回る入出庫を繰り返すことが課題である。運送側の問題で少数のケースをなかなか買えない状況が起き始めている。他県などと連携を取りながら課題について話し合いをしている。
- 一人暮らしの方がインスタント食品などいろいろな食品を食べて安定したという話では、汁を全部飲み干すと塩分摂取量が増えるので半分残すなど上手に食べてほしい。冷蔵庫、電子レンジを上手に使って料理していけば食品ロスは減ると思う。
- 地産地消などのエシカル消費にかなり取り組み、ゴミを出さないように料理をする料理教室など頻繁に開催している。
- 物流センター1カ所で行えば食品ロスが出にくい事業の構造になる。また、ミールキットといって、野菜など調味料もついて1セットを自宅で調理するだけという商品が非常に伸びている。ある程度出来上がっている冷凍食品で栄養バランスの良いものを冷凍庫で保存すればロス削減につながる。さらに、生産者と販売者が収穫量などの連絡を密に取り合う仕組みを作る。生協の仕組みのように、助け合いで離島などの集会場に商品を届け、そこからは地元の方々で配っていくことも今後大切になってくる。
- フードドライブを常設したものの、集まったものをどういうふうに届けていくか、他団体の協力が必要になっている。
- 以前は見切り品コーナーにあると手に取るのが恥ずかしかったが、「食品ロス削減に御協力ありがとうございます」というコーナーに変っているので、多くの方が買い物かごに入れる光景を目にする。国民全員消費者であると考えると、消費者の意識が変われば社会が変わっていくと感じている。
- フードドライブについて、フードバンク活動を長く熱心にやっている団体は最近商品が集まらないという。賞味期限数日前といった食品を集めないと家庭からは出てこないのではないかといわれているほど厳しい現状がある。
6.その他(意見交換会写真等)
 意見交換会の様子 |
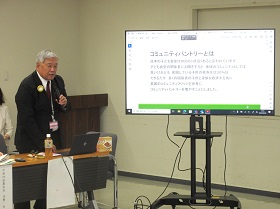 株式会社ハローズ太田様による 食品ロス削減の取組紹介 |
 株式会社ケンジャミン・フランクリン成田様 による食品ロス削減の取組紹介 |
 意見交換会の様子 |
 ハローズ店舗から一日で発生する 賞味期限前の食品ロスサンプルを展示 |
お問合せ先
消費・安全部消費生活課
代表:086-224-4511(内線2322)
ダイヤルイン:086-224-9428




