今後の肥料を考える地方シンポジウム~肥料制度の見直しなど、改めて土から考える~(九州地区)

農林水産省では、土づくりに役立つ堆肥や産業副産物由来肥料の活用とともに、農業者のニーズに応じた柔軟な肥料生産が進むよう、肥料に関する法制度の見直しを行っています。関係者の皆様と一体となって見直しを進めるため、「今後の肥料を考える地方シンポジウム~肥料制度の見直しなど、改めて土から考える~(九州地区)」を開催しました。本シンポジウムでは、肥料をめぐる状況と見直しの方向について説明したほか、有識者や民間企業等の取組を紹介しました。
日時:令和元年9月13日(金曜日)14時00分~16時20分
場所:熊本地方合同庁舎B棟2階共用会議室
参加人数:165人
開会挨拶
 |
神井 弘之 農林水産省消費・安全局 審議官 現在、日本では、水田での窒素の減少、土壌の栄養バランスの崩れ、微量要素の不足などの状況により、収量低下などの問題が顕在化している。 こうした課題については、関係者で一致して土壌の健康を取り戻す努力を行えば、生産性の向上、経営発展につなげることが出来るという発想の転換も可能である。 農林水産省としては、土壌診断に基づいて土づくりに取り組む生産者を応援していくこと、耕種農家のニーズにマッチした畜産廃棄物を供給する取組を応援していくこと、土づくりに役立つ堆肥や産業副産物をさらに利用しやすいよう、肥料取締法を見直すことを行っていきたい。 本シンポジウムを健康な土づくりにさらに一歩踏み込んでいただくための機会にしていただければ幸いである。 |
第1部 基調講演
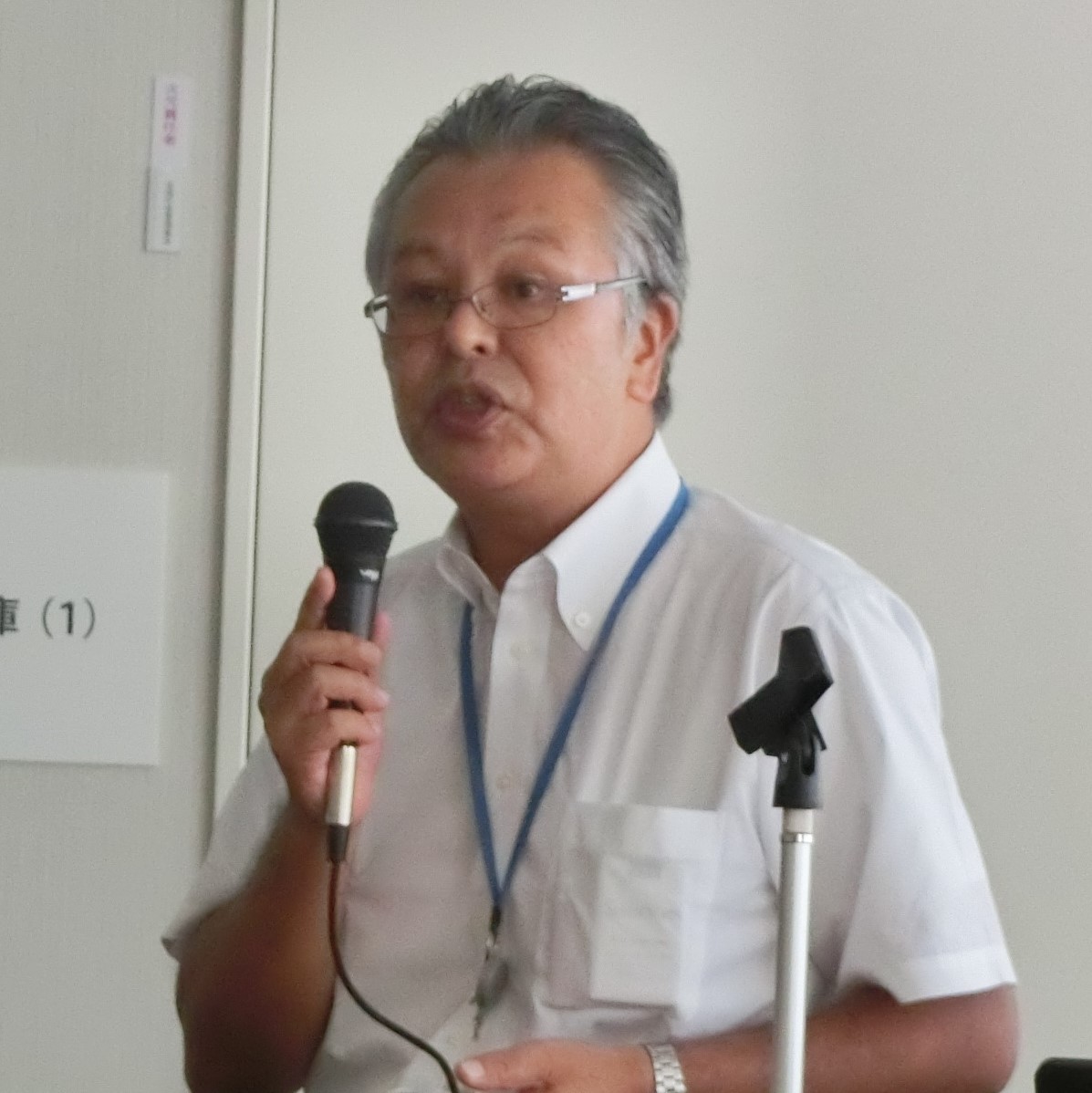 |
瀬川 雅裕 農林水産省生産局農業環境対策課 政策情報分析官 「土づくりの現状と課題」 現在、日本の農地土壌は、水田では可給態窒素の不足やケイ酸の減少、畑地ではリン酸過剰、塩基バランスの崩れ、微量要素の欠乏により、収量低下や生育障害が生じている。これを解決するためには、土壌診断、土壌管理の重要性を農家の方に理解していただくことが必要。 土づくりの推進のために、新しい土づくりの体制を作っていく。具体的には、土づくり専門家の育成、土壌データを集積・共有化するための土づくりコンソーシアムの取り組み等を進める。 土壌診断に基づく土づくりを進めるには、診断結果を踏まえた資材をすぐに提供できるようにすることも重要。 生産局農業環境対策課講演資料(PDF : 1,259KB) |
 |
春日 健二 農林水産省消費・安全局農産安全管理課 食品安全情報分析官 「肥料をめぐる状況と見直しの方向について」 これまでの制度見直しの経緯と見直しの方向性を説明。地力の低下など土壌の悪化が問題となる中で、有機・副産物肥料の利用が進む環境づくりを進めたい。 原料管理制度の導入などにより農家が安心して肥料を利用できるようにするとともに、堆肥と化学肥料の配合を可能にするなど新たな肥料の生産・利用を進めやすくするなどの見直し等を検討中。 堆肥と化学肥料の配合により、成分の安定化、散布に係る労力軽減、肥料のコスト低減等のメリットがある。 消費・安全局農産安全管理課配布資料(PDF : 1,068KB) 消費・安全局農産安全管理課講演資料(PDF : 452KB) |
 |
藁田 純 農林水産省生産局畜産部畜産振興課 分析官 「家畜排せつ物の肥料としてのさらなる活用に向けて」 家畜ふん堆肥の広域流通、高付加価値化のため、ペレット化することにより、散布、流通、保管が容易になるという事例がある。 混合堆肥複合肥料の規格が新設されたことにより、付加価値が高く、利便性が良い堆肥を原料とした複合肥料が作られるようになったが、まだ規制上の制約がある。さらなる規制の見直しにより、牛ふん堆肥も含めて化成肥料との配合が可能になれば、肥料成分の安定と作物の発育に合わせた肥効の調整に寄与できる。 畜産経営は、家畜排せつ物は「厄介物」ではなく、「価値ある肥料原料」へ発想の転換をしていただきたい。 生産局畜産部畜産振興課講演資料(PDF : 1,431KB) |
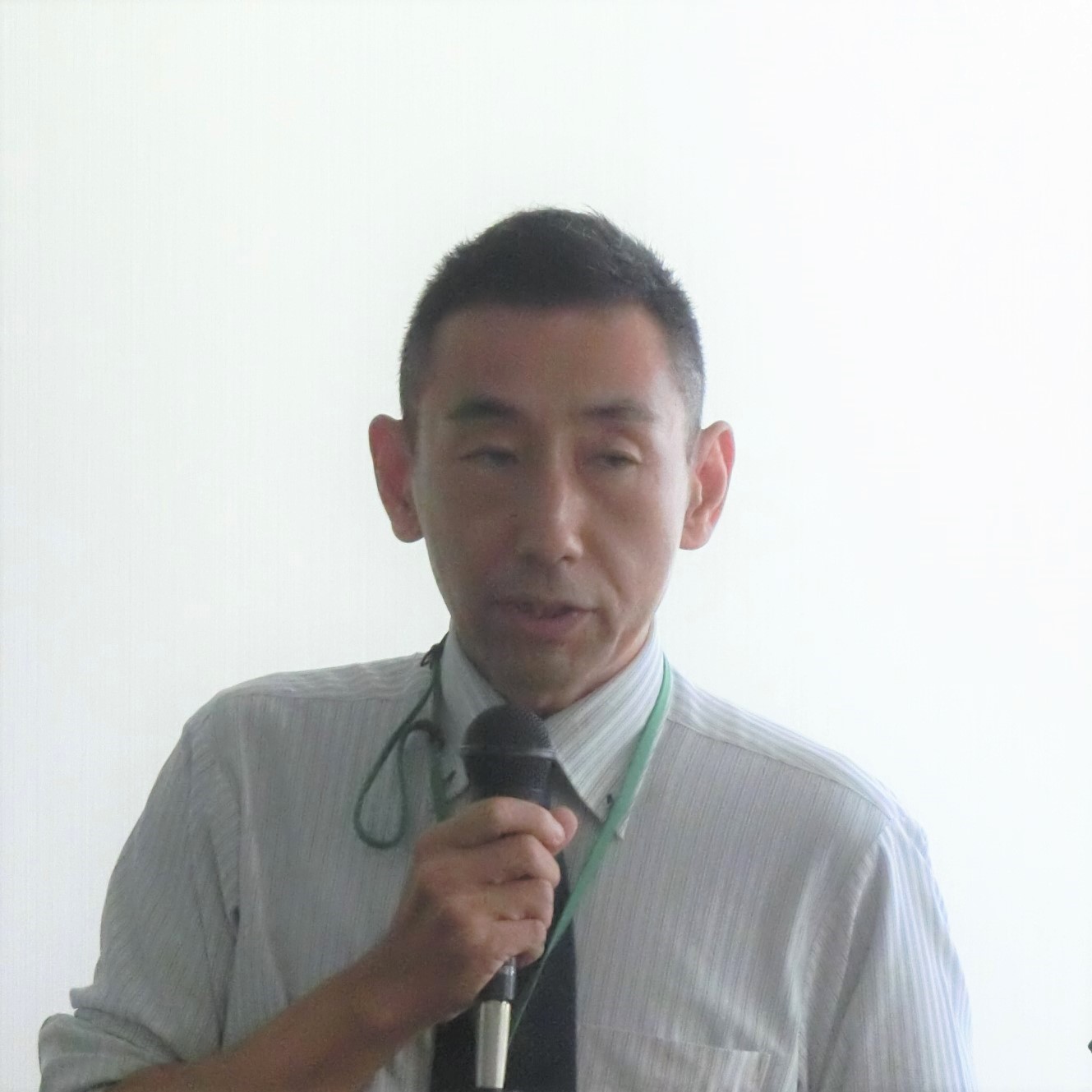 |
荒川 祐介 農研機構九州沖縄農業研究センター 畑土壌管理グループ長 「肥料原料としての家畜ふん堆肥の可能性」 堆肥の利用促進については、施肥のための労力や、含有する成分量が明確でないことがネックとなっている。 堆肥のペレット化については、容量が減少して運搬性が向上し、散布が容易になるという利点がある。また、混合堆肥複合肥料については、潜在的な肥料原料である家畜ふん堆肥を利用できること、施肥関連作業が軽労化できること等のインパクトがあり、農研機構でも、農林水産省委託プロジェクトにより、公設試験場、肥料メーカーとともに共同研究を実施して牛ふん堆肥ベースの混合堆肥複合肥料を開発した。 肥料制度見直しに対しては、堆肥を肥料原料として利用しやすくなるような規制の柔軟化を期待する。 荒川氏講演資料(PDF : 3,027KB) |
第2部 肥料をめぐる民間企業と農業生産現場の取組
 |
増田 誠四郎 南国興産株式会社肥料営業課 課長補佐 「資源循環の取り組みと課題について」 現在、鶏ふんと豚の排せつ物の混合物の燃焼灰は普通肥料の原料として使用できないが、当該燃焼灰はりん酸含有量が高い傾向にあり、有効な国内りん酸資源であるため、普通肥料の原料として利用できるよう制度改正を期待する。 牛ふんは土壌物理性の改善効果が高く、南国興産では、牛ふんにこだわった混合堆肥複合肥料の開発を目指している。しかし、現行の公定規格のC/N比15以下では、牛ふん堆肥の利用が制限される。このため、堆肥のC/N比ではなく、製品のC/N比での規格設定を期待したい。 堆肥を肥料原料として使う際、適正な水分と粒度がポイントとなる。これがクリアできれば、牛ふん堆肥の使用が増えるのではないか。そのためには、堆肥化施設等の設備投資に関し、国や行政機関によるバックアップが必要と考える。 増田氏講演資料(PDF : 1,847KB) |
 |
谷山 恵介 菊池地域農業協同組合畜産部畜産企画課 課長 「堆肥生産の現状について」 堆肥の販売先に苦慮する農家のため、JA菊池では平成18年に有機支援センターを設立した。JA菊池管内の畜産農家の取組を阻害しないよう、有機支援センターで取り扱う堆肥は、できるだけ管内の農家に販売せず、広域流通に取り組んでいる。しかし、堆肥の広域流通については、JA菊池だけでは需給のマッチングなどへの対応が難しいため、県などの調整が欠かせない。 農家のニーズに応える肥料生産が可能となるよう、制度改正にあたっては、堆肥と化学肥料の混合を可能にする一方で、手続きが煩雑であると対応が困難となるので、柔軟な対応と配慮をお願いしたい。 谷山氏講演資料(PDF : 2,693KB) |
質疑応答
質疑応答では、講演者間での質疑応答を行った後、会場からの質問に各講演者が回答しました。主な質問と概要は以下のとおりです。
(質問)行政として今後どのように土づくりを進めていくのか。
(回答)データ収集を加速化させるため、土づくりコンソーシアムのフェイズ2、フェイズ3には予算措置を検討しているところであり、取組の拡大を図りたい。これからの土づくりは、行政がサジェスチョンする一方的なものではなく、農家からもデータをいただき、それをフィードバックする双方向の形で進めていきたい。
(質問)堆肥のペレット化などに向けた対応はなされていると考えてよいか。
(回答)畜産農家が耕種サイドのニーズに対応した堆肥の生産・流通を促進する取組については、令和2年度の概算要求として要求しているところ。また、この事業で得られる成果については、全国の関係者で事例として共有できる形を作っていきたい。
また、混合堆肥複合肥料の生産が伸びているのは大変心強い。肥料制度の見直しの中で必要な限度の規制にすることにより、牛ふん堆肥のペレット化もさらに加速するのではないか。
(質問)肥料制度の見直しの今後のスケジュールを教えてほしい。
(回答)肥料制度の見直しについては、まず肥料取締法改正に係る国会審議が必要。農林水産省としては、秋の臨時国会への提出に向けて努力しているところ。国会で可決成立すれば、その後に省令、告示、通知を見直す必要がある。法律の施行にあたっては、一定程度の周知期間を設けることが想定される。
(質問)公定規格の基準をクリアした上で登録を受けているにもかかわらず、汚泥肥料は農家から敬遠されている。下水汚泥という言葉からマイナスのイメージが生じており、「汚泥」の名称を何とかできないのか。
(回答)下水汚泥肥料については、りん酸資源として非常に重要なものであり、大きなポテンシャルを有していると認識している。他法令との関係上、名称変更は困難と考える。肥料の利用者側の意識改革が必要であり、我々も努力していきたい。
(質問)堆肥と肥料は分けて流通しているのでその観点を踏まえて検討してほしい。また、堆肥は時期によって成分が変動するので、化学肥料で成分を補えるようにしてほしい。
(回答)堆肥については、ペレット堆肥としてそのまま利用する、さらに今後は肥料原料として利用することが可能になる。2つのパターンに応じて流通の仕組みを作っていただいた上で、関係者と一緒に進めていきたい。また、肥料制度の見直しにあたっては、堆肥と化学肥料を配合できるようにする方向で検討している。
〈会場の様子〉

質疑応答の様子(左から藁田、瀬川、春日、神井)

質疑応答の様子(左から荒川氏、増田氏、谷山氏、福永)

会場全体の様子
添付資料
シンポジウム(九州地区)開催概要(PDF : 147KB)お問合せ先
九州農政局消費・安全部 農産安全管理課担当者:肥料管理係・副産物肥料管理係
代表:096-211-9111
(内線4982)肥料管理係
(内線4232)副産物肥料管理係
直通:096-211-8739 (肥料管理係)
096-300-6136 (副産物肥料管理係)




