「みどりの食料システム戦略推進鹿児島ネットワーク報告会」が開催されました!
令和7年7月29日(火曜日)に、「みどりの食料システム戦略に関する取組の報告会」をオンラインで開催しました。報告会には、農業者、JA、流通・販売業者、有機関連団体、大学などのほか、鹿児島県や市町村の行政機関を含めて、63名の方々が参加されました。
まず、農林水産省から「みどりの食料システム戦略に関する令和7年度の取組」について説明を行った後、生産・流通・消費の分野から代表して、4名の方から、取組事例を発表していただきました。
取組事例の発表内容等について、簡単にご紹介します。
【施設ピーマンにおけるIPMの取組(JAそお鹿児島ピーマン部会 天敵研究会会長 下前泰雄氏)】
・ 就農当時、化学農薬を散布する際に、大量の農薬を体に浴びながら作業することに対し、ショックを受けた。このため、化学農薬を散布しない農法
について試行錯誤した。
・ IPM農法は、害虫(アブラムシ等)に対し、化学農薬ではなく、スワルスキーカブリダニ、タバコカスミカメ、ヒメカメノコテントウ等の天敵を
活用した防除方法。天敵を誘引し、定着・増殖を助けるインセクタリープラント(ソルゴー、ゴマ、クレオメなど)を活用することが肝。
・ また、蛾の幼虫に対しては、フェロモン剤を設置して、交尾を攪乱することによって発生を防いでいる。
【南九州市における有機農業の推進(南九州市役所農業振興課 農業技術指導監 下沖美幸氏)】
・ 南九州市では、茶の有機栽培は県内トップクラスであるが、野菜や水稲では低調であることから、有機農業栽培技術研修会(座学と現地研修)を
独自で開催した。
・ 研修会のアンケートでは、研修への参加理由として、「有機農業での単収や品質を向上させたい」、「仲間作りがしたい」等の回答が多かった。
また、「研修会を継続してほしい」、「オーガニック給食を進めてほしい」、「有機農業で成功している経営事例を紹介してほしい」などの
有機農業に前向きな意見が多かった。
【環境と身体にやさしい農産物の販売等の取組(株式会社ハルタ 代表取締役社長 春田晃秀氏)】
・ 自分自身がアトピーやアレルギーで苦しみ、妹を免疫障害で亡くした経験がある。
・ こうした中で、ある有機農業者との出会いから、食の安全・安心の大切さを再認識した。健康は失ってからでは取り戻せないため、
環境や身体にやさしい食材を数多く取り扱っている。
・ 店舗では、農業者の写真やコメントを記載するなど、工夫を凝らしたポップを掲示しての販売や、シェフによる有機野菜の料理ゼミ、予防医学の
先生方などによる食と健康の講座、保育園とのオーガニック給食などにも取り組んでいる。
【地産地消の推進と菜園(さえん)畑の拡大(鹿児島県栄養士会 川辺地区栄養士会会長 鮎川ゆり子氏)】
・ 最初は、小麦を蒔くところから、収穫までの一連の作業を親子で体験してもらう「実から実への命のつなぎ」の活動から始めた。
・ 収穫した小麦は、来年の種を残して、余った実が私たちの食料となる。このことは、体験しないとなかなか実感することができない。
・ 現在、無農薬・無化学肥料の畑で、子ども達と野菜を育てる活動も行っており、そこで採れた野菜は、やさしい味がして野菜嫌いの子供もよく食
べてくれる。
・ また、「さえん畑広げ隊」を結成し、さえん畑で採れた種や苗の配布を行い、さえん畑を広げる活動を行っている。
※さえん(菜園)畑とは、鹿児島弁で、自宅前で自家用の野菜を育てる菜園のこと。
【主な質疑応答】
・ お客様は、有機農産物であっても、見栄えが良いものや包装の仕方、美しさなどを求めて購入されているのか。
・ →有機農産物でも見栄えは重要。袋詰めやトリミングなどの見せ方は工夫している。
見栄えは悪くても、品質は変わらないので、有機農産物等を自然と選んでもらえるような情報発信が必要と考える。
・ 消費者は、つい見栄えが良いものを選んでしまうが、自分で栽培することで、少々の見栄えの悪さや虫食い等を許容できるようになったという話
を聞く。今後、さえん畑を広げるための考えを聞かせてほしい。
・ →料理教室、学校での授業などでは、さえん畑で採った種・苗等を使って説明したり、プランターなどでも野菜を栽培することができることを
伝えている。また、オーガニックイベントでは、さえん畑で採れたものを試食してもらうなどの活動を行っている。
今後も様々なイベントで、さえん畑の取り組みを広げていきたい。
2時間の会合予定でしたが、時間を超過して質疑応答が続き、有意義な意見交換会となりました。参加いただいた皆さま、ありがとうございました!
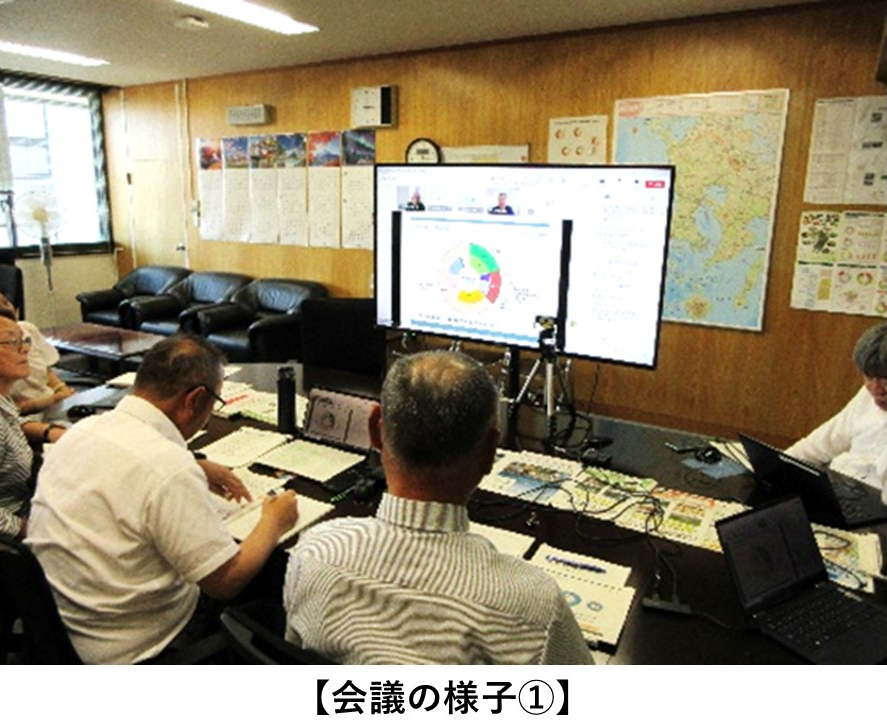

お問合せ先
みどりの食料システム戦略推進鹿児島ネットワーク事務局(九州農政局鹿児島県拠点地方参事官室)電話:099-222-5840
E-mail:kagoshima_info@maff.go.jp
電話受付時間:月~金曜日 9時00分~17時00分




