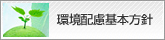1.古代(弥生時代~平安時代)那賀川(なかがわ) 平野は典型的な三角州扇状地です。三角州とは、川から運ばれてきた砂レキが海岸にたまって形成される扇状の土地のことで、那賀川が平野に出る地点、持井(もちい)橋(阿南(あなん)市持井)あたりがかつての河口でした。およそ4,500年前に、古毛(こもう)、古庄(ふるしょう)、宮倉(みやぐら)、中庄(なかしょう)(いずれも阿南市羽ノ浦(はのうら)町)などの中州が形成されたとあります(※)。 阿南市には○○島といった地名がいたる所にあります。那賀川は下流でレース模様のように派流に分かれ、中世まで平野は自然氾濫状態が続いたとあります。島の名がつく所は中州になった小高い場所で、川が氾濫しても水に浸かりにくかったのでしょう。古代人はそうした場所に集落を造り、周りの湿地帯に稲を植えたりして暮らし始めました。 この阿南市や小松島(こまつしま)市からは銅鐸(どうたく)が10個も見つかっています。徳島県全体では42個で、これは島根県の54個に次ぐ全国2番目の多さです。通常、銅鐸の分布は近畿を中心とする円を描き、銅剣や銅矛(どうほこ)は北九州を中心に分布しています。しかし、徳島県からはこの両方が発見されており、2つの文化圏の接点であったことを示しています。 奈良から紀の川を経て紀州、阿波(あわ)へと渡る舟のルートは南海道(なんかいどう)として多く利用されており、荷物を積んだ場合はむしろ陸路を往くよりも楽でした。 また、この那賀川周辺は海人(あま)族も勢力を持っており、朝廷への貢ぎ物として海産物が多く記録に残っています。物資輸送や時には海賊(かいぞく)まがいの行為もあったのでしょう。紀貫之(きのつらゆき)の『土佐日記』には土佐赴任からの帰路、海賊に追われたことが5回も記されています。 この地方に平安朝まで隠然(いんぜん)たる力を持っていた豪族は長(なが)氏。古くは長国(ながのくに)、粟国(あわのくに)と分かれていました。大化の改新で長・粟は阿波国として合併され、公地公民制により全国に条里制(じょうりせい)がしかれます。この那賀川平野にも、上流南岸、中流北岸一帯に口分田が整備されました。この地割による地名は、九の坪、一丁ヶ坪、三反田などの字(あざ)として多く残っています。 また平安時代中期になると、須恵器(すえき)の分布などから下流南岸の富岡(とみおか)町、日開野(ひがいの)町、学原(がくばら)町(いずれも阿南市)一帯が発展していったことが分かっています。ちなみに、学原という地名は、長氏の私塾があったところとも伝えられています。 しかし、いずれにせよ平安時代まで氾濫が繰り返され、三角州の形成途上にあったこの平野では目立った開発は見られず、島と名のつく地に点々と集落が散在していたのでしょう。平安時代中期に編纂(へんさん)された『和名抄(わみょうしょう)』には、那賀郡は八郷と記録されていることから、1郷50戸平均として約400戸程度であったと推定されています。もっとも当時、記録に残されるような家には1戸あたり家族や使用人など20~50人程度が住んでいたので、人口は1万人を超えていたと思われます。 寺戸恒夫(てらどつねお)『那賀川下流域の古地形の復元』より 【写真】那賀川平野の旧河道(寺戸恒夫作図)
|
お問合せ先
那賀川農地防災事業所〒774-0013
徳島県阿南市日開野町西居内456
TEL:0884-23-3833