長崎の農山漁村のすがた(あぜみち写真館)
![]() 長崎県拠点トップページへ戻る
長崎県拠点トップページへ戻る
![]() 長崎の農政の動き(あぜみち写真館)へ
長崎の農政の動き(あぜみち写真館)へ
![]() 九州のあぜみち写真館へ(九州農政局)
九州のあぜみち写真館へ(九州農政局)
令和5年3月7日 ばれいしょ畑(諫早市)
諫早市飯盛町のだんだん畑では、ばれいしょ(じゃがいも)の芽が出始めていました。
ばれいしょの種芋を植えた畝に、保温や雑草が生えないようにマルチといわれるポリフィルムを被せてあります。
春になるとマルチの下で芽吹くため、芽が焼けないよう1~2日おきに見回りながら、ポリフィルムを破って芽を出してやらなければなりません。
出荷や収穫の作業が集中しないよう、品種や植付時期をずらしてあり、このあたりの収穫は5月ごろになりそうです。



令和4年4月6日 早期水稲と麦類(諫早市)
諫早市森山町では、この時期、水稲と麦類が同時に見られます。
早期水稲の田植えが3月下旬から行われる側には、5月の刈取りを待つ麦類の田も広がっています。
どちらも豊作となるよう、すくすくと育ってほしいものです。



令和3年11月19日 びわの摘らい(長崎市)
橘湾に面した傾斜地にある「びわ」園では、花の蕾を減らす作業「摘らい(摘蕾)」が行われていました。
びわは、多くの花を付けるため、そのままでは一つ一つの実が小さくなります。このため、今回の「摘らい」と、実のできはじめに減らす「摘果」を行い、最終的には1か所に3つほどの実に養分を集中させるようにします。木の高い位置にある花や実をとるため、斜面に植えられた木の1本1本に登ったり、枝を引き寄せたりと大変な苦労の末、大きな実が市場に出回ります。



令和3年10月26日 茶園(北松浦郡佐々町)
九十九島を見下ろす、山の上にある茶園です。
園の経営者によると、岩だらけの斜面の土地を先代が手作業で開墾したそうで、周りには大きな岩が園を見守るように残っています。
枝を整えるために、まもなく行われる刈り込みを待つ木の根元には、ツバキに似た白いお茶の花が咲いていました。



令和3年3月4日 ブロッコリーの収穫(諫早市)
次々と収穫されるブロッコリー。「生育が悪くて収穫を諦め、ほったらかして雑草だらけになってしまったが、一時期の暖かさで収穫できるまでになった。」と農家は言う。
露地野菜は、自然との戦い。厳しい寒さで全滅するかと心配していると、急な暖かさで復活したりすることもある。農家は同じブロッコリーでも、数種類の品種を植えることで、危機を分散し、同時に労力分散を図る。同一ほ場には、収穫中のところ、収穫が終わりトラクターで耕運したところ、6月に収穫するブロッコリーの苗を植え付けているところがあった。収穫作業は、まだまだ続くのである。



令和3年2月9日 ゆでぼし大根(西海市西海町面高地区)
西海市面高地区の冬の風物詩、『ゆでぼし大根』の茹で干し風景です。
地区では、細かく切った大根を茹で、断崖絶壁に組んだやぐらの上で冬場の北風を利用して乾燥させることで、「うまみ」「甘み」を凝縮させた保存食を昔から作ってきました。1月初旬からが最盛期であり、2月は終盤に入りますが、多くのやぐらで作業が進められています。


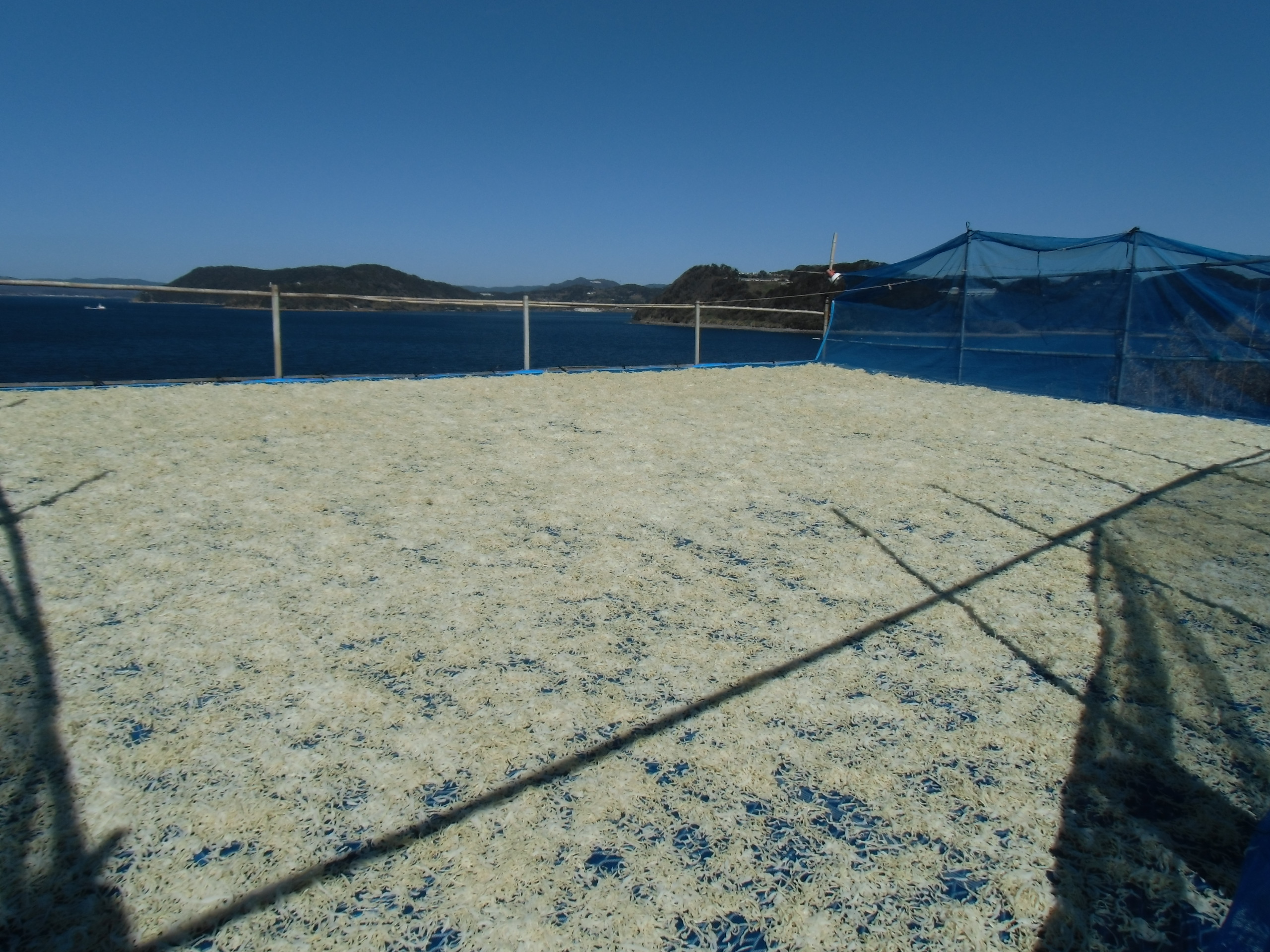
令和2年9月29日 大中尾棚田(長崎市)
彼岸花が咲く、稲刈り時期の大中尾棚田です。
長崎市の北西部(合併前の外海町)に位置する「大中尾棚田」は、平成11年に農林水産省によって「日本の棚田百選」に認定されています。

令和2年9月9日 水稲の花(佐世保市)
「水稲(米)の花を見たことがありますか?」
田で水稲を作っている人を除くと、実際に見たことがない人が意外と多いのではないでしょうか。
この写真は、長崎県拠点の統計チームが実測調査をしている田で撮影したもので、品種は長崎県の奨励品種である「にこまる」です。
水稲は、花が咲いているときに触ったりすると実を付けない恐れがあるため、田に入っての実測調査は行いません。この日も、他の田の実測調査を行い、この田は後日調査を行いました。


令和2年6月23日 鬼木棚田(東彼杵郡波佐見町鬼木郷)
東彼杵郡波佐見町の南東部に位置する「鬼木(おにぎ)棚田」は、長崎県内で最大の規模を誇ります。平成11年に農林水産省によって「日本の棚田百選」に認定されました。
波佐見町の南東部、佐賀県との県境に近い山間にあり、戦国時代から江戸時代にかけて開拓され、約22ヘクタールの区域に400枚ほどの水田が連なっています。



令和元年11月26日 みかんの新植(西海市)
西海市西彼町における、パイロット事業(農業目的に山野を開墾する事業)により、新しく植えられたみかんの苗木です。
西海市では、昭和45年にみかんの品種「宮川早生」から「原口早生」が枝変わりで発見されるなど、昔からの温州みかんの産地です。

平成31年3月以前については、九州のあぜみち写真館へ(九州農政局)
お問合せ先
長崎県拠点
地方参事官室
電話(095)845-7121




