地域の和食文化ネットワーク九州「第3回食文化保護・継承推進ミーティング」(令和6年11月6日開催)
平成25年12月、「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産へ登録され、「日本食と食文化」に対する国内外の評価が高まりました。
一方で、ライフスタイルの変化や食の多様化等により、和食や地域の伝統的な料理(郷土料理)の存在感が薄れつつあり、これら食文化の保護・継承が喫緊の課題となっています。
九州農政局では、地域における食文化保護・継承活動の活性化の支援と、その活動を支える多様な関係者の連携を図ることを目的として、令和3年2月、「地域の和食文化ネットワーク九州」を設置し、メールマガジンの配信やイベントの開催等により、食文化の保護・継承に関する様々な情報提供及び情報交換の場としての活用に取り組んでいます。
今回、この取組の一環として本ミーティングを開催し、取組事例の共有及び情報交換を行うことにより、九州地域における和食文化の保護・継承活動の推進と会員間の交流・連携を図りました。
開催概要
1.開催日時
令和6年11月6日(水曜日)13時30分~16時10分2.開催方法
対面(熊本地方合同庁舎A棟10階農政第7会議室)及びオンライン(Microsoft Teams)3.参加者
地域の和食文化ネットワーク九州会員及び一般参加者:計57名4.内容
【第1部】取組事例の共有(講演)「地域の食文化保護・継承」
演題 「郷土料理のストーリーの伝承について」
(1)講師:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 執行役員 総料理長 戸澤 清水氏



【第2部】分散会及び全体発表
-
テーマ1「郷土料理の伝承方法(特に料理に付随するストーリーの伝承について)」
・各会員の生活する地域で伝承されている郷土料理には、どのようなストーリーがあるのか。
・地域の郷土料理をどのように掘り起こしているのか。
・次世代への承継体制 -
テーマ2「活動に取り組む中での課題や悩みなど自由討論」
・地域コミュニティーの変化
・地域特有の食材、調理道具、食環境、時代のニーズ、食品製造に関する制度の変化
・各会員の取組みに対する参考意見など
(Aグループ:女子栄養大学生涯学習講師・野菜ソムリエ上級プロ・くまもとふるさと食の名人 持田 成子氏)
地域の祭りのときにあったような食事が郷土料理なのではないかという会話を皮切りに、ハレの日やケの日の食事の中で色々な食材があることを思い起こした。
鯨文化を伝えている会員の方から、鯨汁にも地域性があることや、地域の伝統野菜も鯨汁と併せて伝承している取組みのお話があった。
私自身は野菜ソムリエとして、伝統野菜をどうやって残していくかを生産者と共に考える活動をしている。戸澤氏の講演のとおり、郷土料理も進化しないといけないならば、伝統野菜も今の栽培技術を活用して守るべきではないかと思った。
また、小中学校や大学で調理実習の講師をする機会がある。その際には、伝統的な郷土料理を守ることも大事だが、年代に合った調理法で教える必要があると感じている。
くまもとふるさと食の名人としても大先輩から郷土料理を教わることがあるが、大先輩のようにAランクでなくても、B~Cランクの技でも次の世代に伝えるために、私たちも学び、伝える方法や場所を考えていく必要があると感じている。
(Bグループ:和食料理教室四季の會 主宰 五嶋 幸子氏)
充実した分散会だった。
郷土料理を継承するためには、子どもたちに伝えることが重要であり、家庭と給食の両方から伝えないといけないのではないかと思う。郷土料理の背景のストーリーも伝えて、子どもたちに郷土料理について理解してもらう必要があると感じた。
九州農政局農泊推進プロモーション事業を活用した農泊のイベントでは、「郷土料理じまん大会」があるというお話を聞き、興味を引く表現で良いと思った。
和食の基本である出汁がもう少し伝承されるべきだという意見も出た。
(Cグループ:一般社団法人 九州のムラ 泰永 幸枝氏)
郷土料理継承に係る課題は大きく2つある。
1つ目は、伝統的な郷土料理の継承者の高齢化。グループ内では、継承者を増やすため、大学生に伝統的な調理方法を伝える取組みをしている方のお話を聞いた。
2つ目は、戸澤氏の講演のとおり、郷土料理において伝統的な味と現代に合ったアレンジレシピの両方を伝える難しさ。調味料・調理方法・調理器具は変化している。分散会では現代に合った減塩の健康的な糠炊きを伝えていく取組みのお話を聞いた。伝統的な味と現代に合ったアレンジレシピの両方を伝えるために、作る機会・食べる機会の頻度を増やすことが重要だと感じた。
(Dグループ:事務局(九州農政局 経営・事業支援部 食品企業課))
大学で講師をしている会員から、大学でアンケートを実施すると、子ども(大学生)は郷土料理を学ぶことに対して、親よりもポジティブなイメージを持っていたというお話があり、興味深かった。
また、継承者の高齢化により、郷土料理を伝える機会が減少しているため、レシピを冊子にして子どもたちの学びの場で伝える活動をしている方のお話も聞くことができた。
今の世代には、SNSを利用した郷土料理の普及が必要であるが、SNSに頼るだけではなく、伝承の場所が必要という意見や、食文化は時代によって変わるが、伝統的な郷土料理の伝承も必要という意見も出た。
(Eグループ:キッズキッチン協会 松本 典子氏)
郷土料理は、地元の年配の方に調理方法を聞き、食育を通して伝えている。
次世代への継承方法は、地域特有の料理がある所に長年住んでいる方は興味がない場合が多く、どう興味を持ってもらうかを考えなければならない。
郷土料理は伝統的な味をそのまま伝えるべきという意見もあるが、時代と共に生活や嗜好は変わる。伝統的な部分(気候風土を活かし発展してきた部分)と新しい部分の両方を伝えればよいのではないかという意見が出た。
地域特有の料理があるところ以外に住んでいる方(料理人等)に、地域の郷土料理のアレンジレシピを作ってもらったり、料理教室・イベントを開催してもらったりすることで、伝統的な郷土料理に新たな価値が見いだされて、継承されやすくなるのではないかと思った。
【会場の様子】
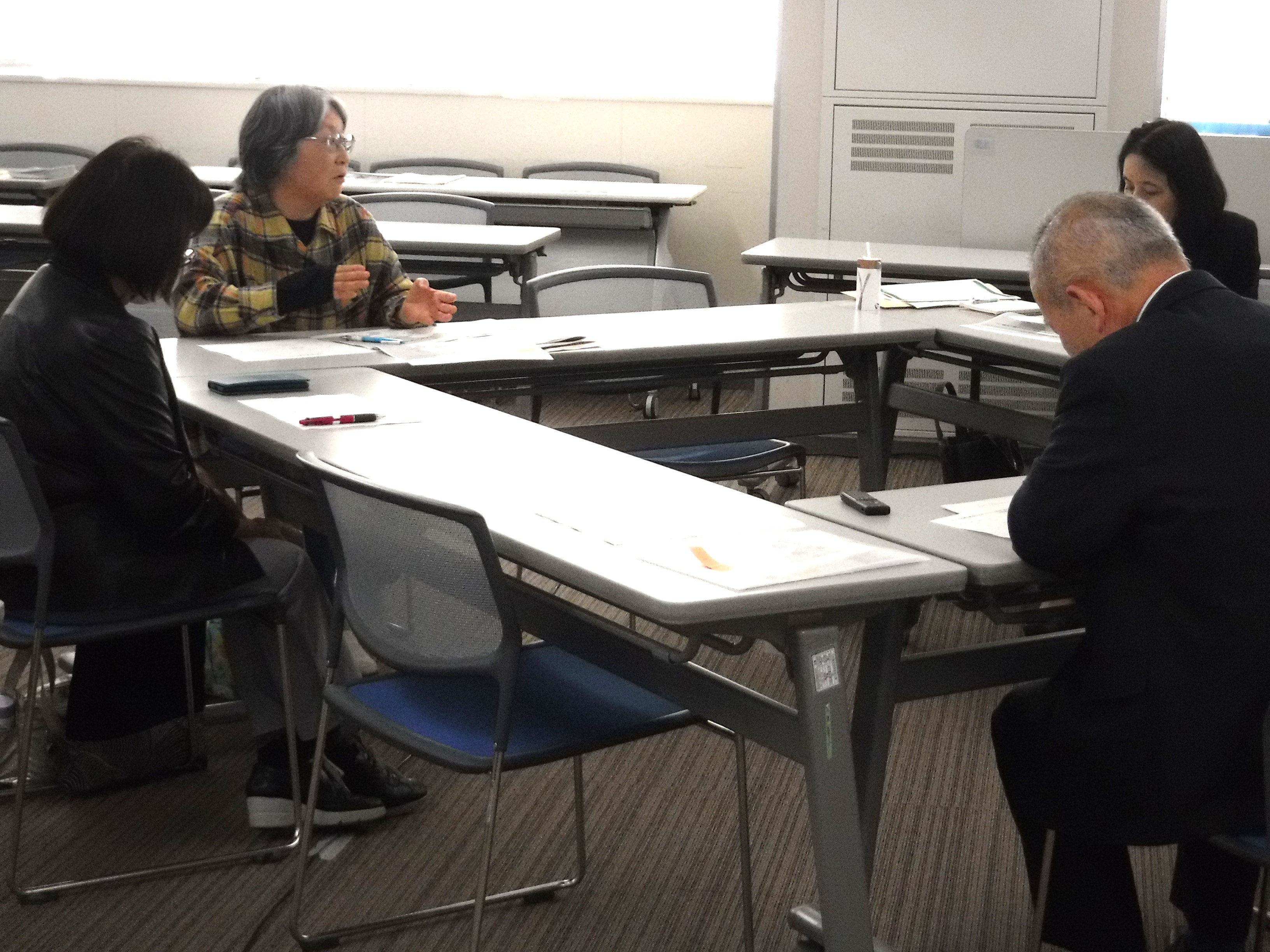 分散会グループA
分散会グループA
分散会A全体発表:女子栄養大学生涯学習講師・野菜ソムリエ上級プロ・くまもとふるさと食の名人 持田 成子氏

分散会B全体発表:和食料理教室四季の會 主宰 五嶋 幸子氏(写真右)

分散会C全体発表:一般社団法人 九州のムラ 泰永 幸枝氏(モニター画面)
5.アンケート結果(ご意見・ご感想等)
アンケートにご協力いただいた方におかれましては、心より感謝申し上げます。集計結果を以下のファイルにてお知らせいたします。
アンケート結果(PDF : 755KB)
お問合せ先
経営・事業支援部 食品企業課
担当者:地域食品・連携班
ダイヤルイン:096-300-6369




