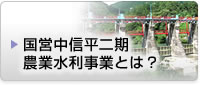さらに詳しく 松本盆地の複雑な地形
この盆地の中央には、糸魚川(いといがわ)―静岡構造線が通っており、いわゆるフォッサマグナの西端となっています。近年のプレートテクトニクス理論によると、日本列島は4つのプレートがぶつかり合うところに形成されたらしく、東日本と西日本は別々のプレートに乗っているとのこと(その境目が糸魚川―静岡構造線)。
いわば、西日本と東日本がぶつかり合ったところということになります。したがって、この盆地の地層は極めて複雑で、同じ松本盆地でも、市内中心部一帯(奈良井川の東側)は深志(ふかし)盆地といって学問上は区別されています。中信平の東側(梓川両岸)は砂礫の多い扇状地であるのに対して、深志盆地はかなりの砂泥層や泥炭層が見られるとのことです。昔は湿地帯であったらしく、深志の地名も「深瀬郷」が転訛したものと言われています。
対して、構造線の西側は飛騨(ひだ)山脈が陥没し、そこへ河川によって砂礫や火山灰が運び込まれたものとされています。地質は、火打岩(松本市梓川倭)より西半分が中・古生層、東半分が第三紀層や火山岩と分れています。
こうした地形の違いや成りたちの違いが、人間社会の歴史や農にも大きな影響を与えることになるのです。
お問合せ先
農村振興部水利整備課ダイヤルイン:048-740-9836