令和5年度「和食・食文化シンポジウム」を開催しました
近畿農政局は、令和5年11月30日(木曜日)京都市国際交流会館及びオンラインにて、令和5年度「和食・食文化シンポジウム」を開催しました。
次世代に和食の魅力を伝えるため、和食に欠かせない「醤油」に焦点を当て、醤油を通して関西の食文化を学ぶ基調講演とパネルディスカッションを行いました。
本シンポジウムでは、「地域の和食文化ネットワーク近畿」の会員及び和食に興味・関心をお持ちの方等、会場とオンラインを合わせて約100名の方々に御参加いただき、安東近畿農政局長の挨拶で開会しました。
第1部 基調講演
〇基調講演1
文化庁食文化推進本部事務局 参事官(生活文化連携担当)付 文化財調査官(食文化部門)大石 和男氏に「食文化と木桶・木樽」をテーマに御講演いただきました。
木桶と木樽の違いや食の製造で活躍する木桶・木樽についてなど、写真により分かりやすく御説明いただきました。
〇基調講演2
株式会社クリエテ関西 和食専門ウェブ・マガジン「WA・TO・BI~和食の扉~」編集長 中本 由美子氏に「関西の和食文化と醤油」をテーマに御講演いただきました。
江戸時代に淡口(うすくち)醤油とだしが出合い関西で和食が花開いたという興味深い歴史についてや、「WA・TO・BI」で掲載された淡口醤油を使用した料理の現代のトレンドなど御紹介いただきました。


第2部 パネルディスカッション
〇事例発表
(1)ヒガシマル醤油株式会社 取締役研究所長 古林 万木夫氏に淡口醤油の発祥の歴史や揖保川伏流水とだしと淡口醤油の関係などについて、お話いただきました。
(2)瓢亭 十五代目当主 髙橋 義弘氏に料理人の立場から、白身魚の刺身醤油としてトマト醤油の作り方や淡口醤油を使うことにより食材の色を生かすことができるなどお話いただきました。
(3)株式会社大阪ガスクッキングスクール 営業部 フードコミュニケーションチーム マネジャー 吾妻 直子氏に家庭料理講師の立場から、淡口醤油の使い方やレシピなどお話いただきました。


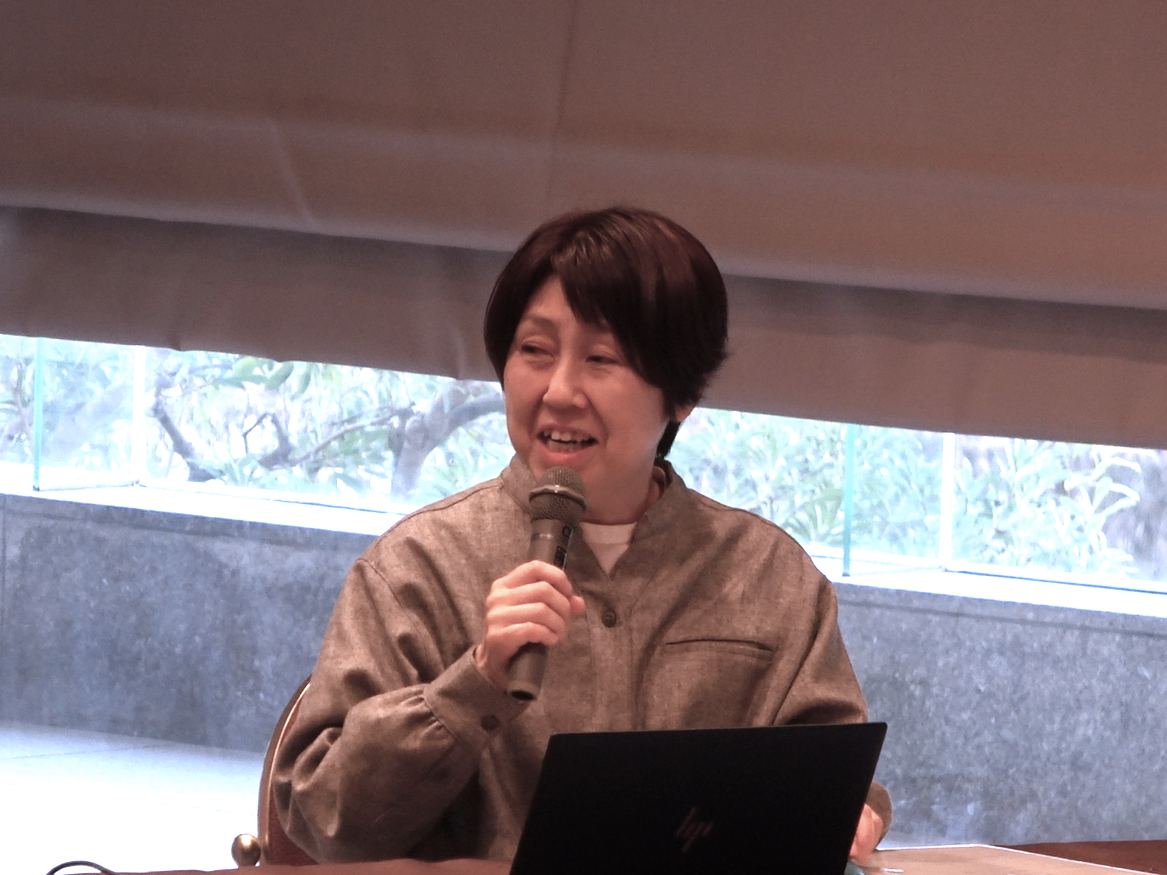

〇ディスカッション
事例発表につづき、「和食文化の保護・継承を進めるために~醤油の魅力をさぐる~」をテーマに、中本編集長のコーディネートでパネルディスカッションを行いました。
「淡口醤油が近畿に根付いたのはなぜか」、「近畿の和食文化の魅力を維持・継承し、次世代に伝えるにはどうすればよいか」について、事前にパネリストからお聞きしていたキーワードを基に進行いただきました。
最後「今までにないような淡口醤油の使い方」について、ヒガシマル醤油の古林氏からは淡口醤油プリンや淡口醤油とオリーブオイルを使ったカルパッチョソース、瓢亭の髙橋氏からは昆布締めの代わりに淡口醤油に潜らせる使い方や野菜を加えたオリジナル醤油、大阪ガスクッキングスクールの吾妻氏からは淡口醤油とトマトジュースなどを使ったトマト素麺つゆの紹介がありました。
参加者からは、「淡口醤油を日常的に使いたい」、「淡口醤油とだしの関係の話が勉強になった」などの感想をいただき、和食文化の保護・継承が大切であることを再認識する場となりました。


<参考>
お問合せ先
経営・事業支援部 食品企業課
担当者:和食・食文化担当
ダイヤルイン:075-414-9024




