有機農業産地づくりに向けた取組 ~「いのち育む有機稲作栽培技術勉強会」~
和歌山県は、平地が少なく中山間地域で栽培される「梅、桃、柿、ミカン」などの果樹の生産額が県全体の農産物生産額の6割以上を占める果樹県であるが、果樹における有機栽培の技術はそもそも難しい現状にある中、令和6年2月23日(金曜日)和歌山県JAビル和ホールにおいて、NPO法人和歌山有機認証協会(以下、「和歌山有機認証協会」という。)第25回通常総会の記念企画として「いのち育む有機稲作栽培技術勉強会」が開催されました。
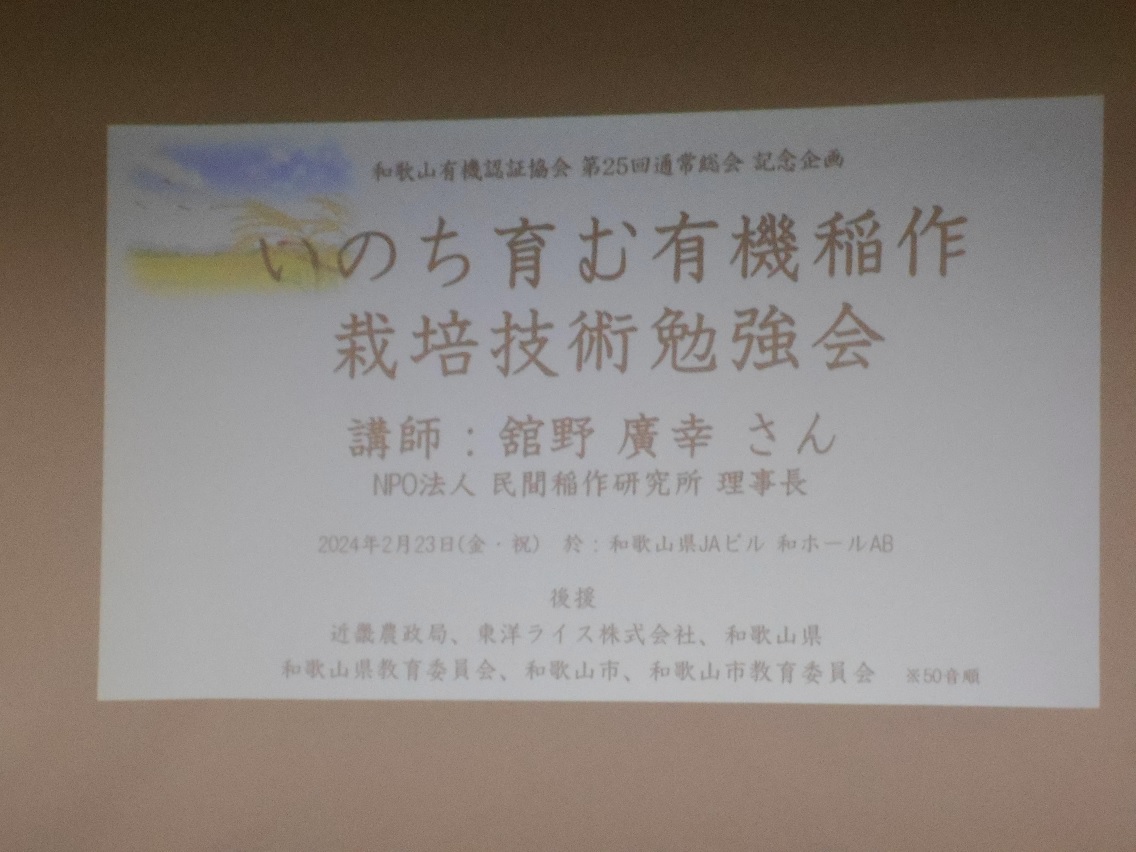
和歌山県において、「みどりの食料システム戦略(以下、「みどり戦略」という。)」の2050年までに目指す姿の達成に向け、有機農業を核とした環境保全型農業による有機農産物等の生産を増やし、学校給食に供給する仕組みづくりのきっかけに有機稲作栽培技術を学ぶ機会として、勉強会が開催されました。

勉強会の冒頭、和歌山有機認証協会の道本浩司理事長から「多くの参加者で会場が埋まり、有機農業への関心の高まりを感じており、継続して有機農業の取り組みを進めていきたい。」との挨拶の後、栃木県有機農業生産者でNPO法人民間稲作研究所理事長舘野廣幸氏(以下、「舘野氏」という。)を講師に迎え、民間稲作研究所の循環型有機稲作技術体系をテーマに基調講演が行われました。

民間稲作研究所の循環型有機稲作技術体系の講演では、舘野氏から育苗や秋耕、代かき等、各作業工程での栽培技術の詳細について講演が行われました。稲刈り後は早めに秋耕して、稲わらの分解・雑草の肥料利用で化学肥料が不要、代かきは、重要な作業でやり方により雑草の発生が変わる。そして、その後の水管理で雑草を防ぐ。との説明を参加者も熱心に聞いていました。

地域循環型の有機稲作技術は気候変動を防ぎ、地球も生き物も健康に持続できる社会の基礎である。また、有機農産物を学校給食へ提供する利点として、1.食材の安全性と子供たちの健康 2.食育と環境学習効果 3.自然環境の維持 4.地域内流通による地域社会の発展。に貢献する。また、「自然生態系の維持こそが、私たちの生命と社会の存続に繋がる。それが、有機農業の本質である」との舘野氏の説明が印象的でした。
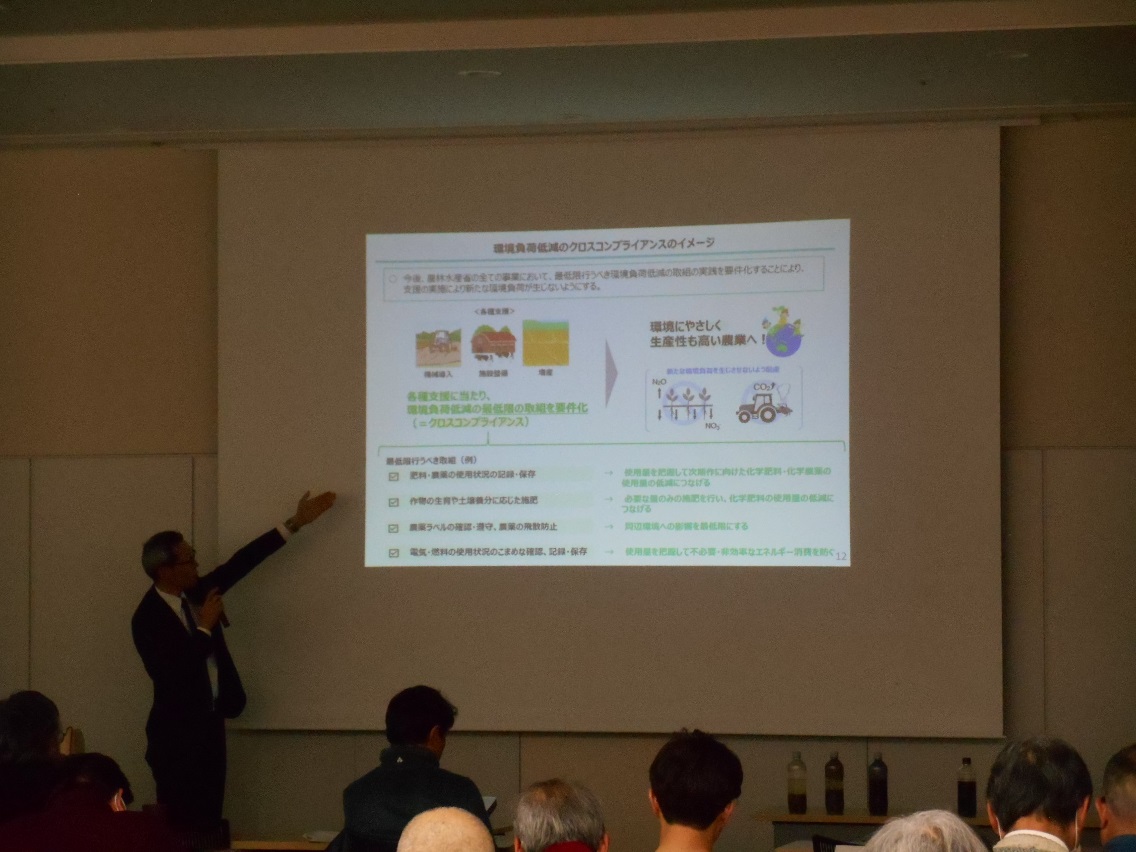
勉強会の後半は、近畿農政局、和歌山県及び和歌山市から「みどり戦略」に係る施策、有機栽培の推進に関する補助事業等の支援策の情報提供がありました。
近畿農政局からは、「みどり戦略」に係る4つのポイントとして「みどり認定」、「温室効果ガス削減の見える化」、「環境負荷低減のクロスコンプライアンス」、「Jクレジット制度」についての情報提供を行いました。

勉強会の最後に和歌山有機認証協会の宇田篤弘副理事長から「和歌山県において、有機栽培に取り組む農業者が増えている。この流れを継続していくためにも、本日の勉強会が有機農業推進の転機となることを期待している。そして、消費者と協同した取り組みを進め、消費者に有機農産物への理解を深めてもらうことが大切であることから、今後も活動を進めたい。」との閉会の挨拶があり、参加した農業者等は最後まで熱心に聞き入り、盛況な勉強会となりました。
お問合せ先
近畿農政局和歌山県拠点
ダイヤルイン:073-436-3831




