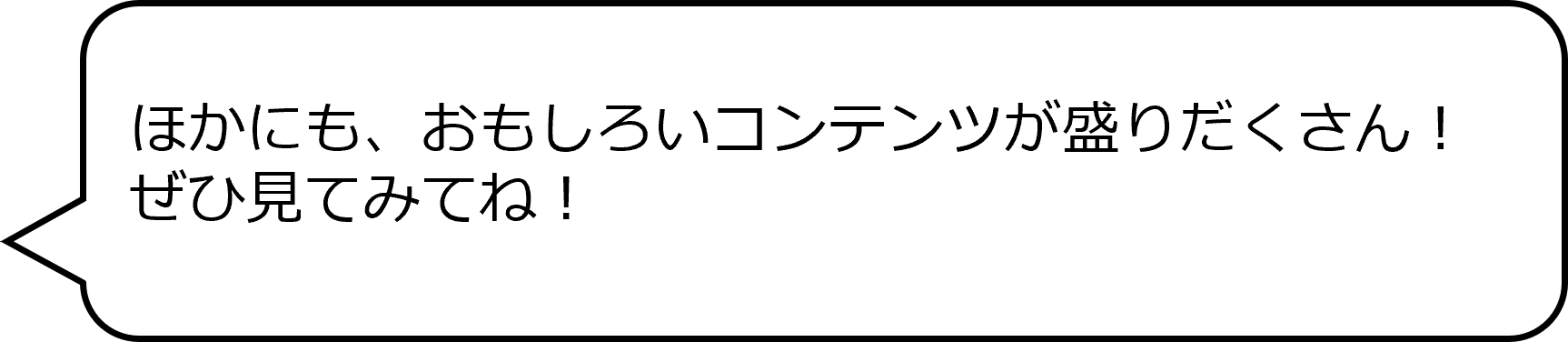日本と世界の食料自給率
 |
||||||||
  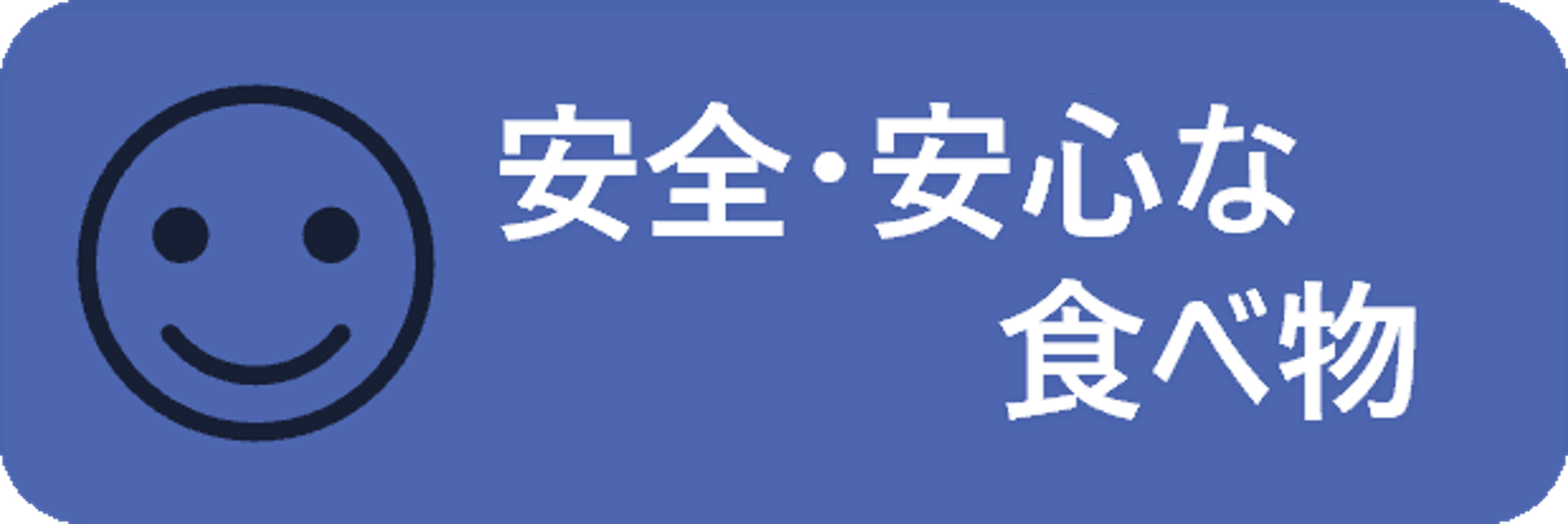 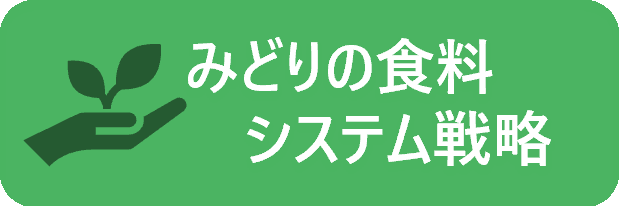 |
||||||||
日本で生産されている食料は少ないの?食料自給率とは?日本で消費する食料は、国内で生産される農産物だけでは足りず、多くの農産物などの食料を外国から輸入しています。 自分の国で消費する食料のうち、自分の国でどのくらい生産しているのかを割合で表すものとして、「食料自給率」という言葉があります。 式で表すと「食料自給率=自分の国で生産している食料÷自分の国で消費する食料」となります。
自給率を上げるためにはどうしたらよいでしょう。自分たちの食料は、自分の国で作るように努力することが大切です。 日本では、令和12年度(2030年度)までに、食料自給率(カロリーベース)を45%に上げることを目標としています。 自給率を上げるために、生産者は、消費者の好みに合わせて食料を生産し、消費者は、国内でとれるお米などの農作物をしっかり食べて、食べ残しを減らす努力をすることが必要です。
食料自給率の低下と、食生活の変化の関係
日本の食料自給率は、昭和35年度(1960年度)の79%から減り続けて、令和4年度では38%になっています。
地元でとれる食材を日々の食事にいかしましょう!私たちが住んでいる土地には、その気候や地形などの環境に適した食べものが育ちます。 一人ひとりが地元でとれる食料を食べることが、食料自給率を上げることにもつながります。
ほんの少し意識を変えるだけでも食料自給率を上げることができます!
ニッポンフードシフトって知ってる?農林水産省では、食とかん境を支える農業・農村への国民への理解と共感・支持を得つつ、国産の農林水産物の積極的な選たくなど具体的な行動の変化に結び付くよう、官民が一緒になって行う国民運動として「食から考える。ニッポンフードシフト」を展開しています。
|
||||||||
|
お問合せ先
企画調整室代表:022-263-1111(内線4500、4313)
ダイヤルイン:022-221-6107