|
 
岩手の郷土料理「うこぎのほろほろ」 R4.3.31
本日3月31日は山菜の日です。
「さん(3)さ(3)い(1)」の語呂あわせから山形県のとある山菜料理店が制定したもので、雪の多い山形では春の山菜が待ち遠しい時期であり、3月の最終日のこの日を「春ですよ」との合図として定めたのだとか(^o^)
今回は、春の山菜「うこぎ」を使った岩手県央地域に伝わる郷土料理「うこぎのほろほろ」をご紹介します。
ところで、皆さんは「うこぎ」をご存知でしょうか。
うこぎとは、たらの芽やうどと同じウコギ科の落葉低木で山野に自生していますが、岩手県や山形県では古くから食用を兼ねた生垣として利用されて来たそうです。
|
 |
「うこぎのほろほろ」は、3月から6月頃に芽吹くうこぎの新芽を茹でて細かく刻み、みそ漬け大根とくるみを刻んだものと混ぜ合わせたもの。
ふりかけのようにして、そのまま熱々のご飯にかけて食べるそうです。
「ほろほろ」という名前の由来は、かつて南部藩の武士が食べようとしたら、箸からほろほろとこぼれ落ちてしまったからだとか(^o^)
先日、八百屋さんでうこぎの新芽を見つけたので買ってみました。
新芽は5センチ位の長さで柔らかい葉っぱという感じです。
 
早速、うこぎのほろほろを作ってみました♪
【うこぎのほろほろ】
〇材料
うこぎ30グラム、みそ漬け大根20グラム、
くるみ30グラム、しょうゆ適宜
|
 |
1.うこぎは熱湯に塩をひとつまみ入れてさっと茹で、水にさらしたら、ぎゅっと絞って細かく刻みます。
2.みそ漬け大根、くるみを細かく刻み、1のうこぎとよく混ぜ合わせて出来上がり。
お好みでしょうゆや白ゴマを加えても可。
分量に決まりはなく、家庭によって食材の割合は様々。
うこぎが多ければ淡白な味に、みそ漬け大根が多ければ長持ちし、くるみが多ければコクがでるそうですよ。
炊きたての熱々ご飯に、たっぷりかけていただきました(^o^)
うこぎのほろ苦さとくるみの甘さ、みそ漬け大根の塩気が相まって、みそ漬け大根のカリカリした食感も良く、ご飯がすすみます!
素朴な味ですが、春を感じる一品ですね(*^_^*)
【豆知識:うこぎの話】
うこぎは中国原産の植物で薬用として日本に伝わり、平安時代から漢方の強壮剤として使われていたとのこと。また、茎にトゲがあることから、戦国時代の城下町では防犯対策も兼ねて生垣として盛んに植えらていたそうです。
江戸時代に米沢藩(山形県)で飢餓が起こり、米沢藩主の上杉鷹山公がうこぎの垣根や食用を奨励したことで、薬用・防犯用としてだけでなく、春先から新芽が芽吹くと摘んだ後も次々と芽吹き、食材として重宝されました。
今も生垣から収穫しますが、パックなどに入って売られているうこぎは、畑で栽培されているそうですよ。
ポリフェノールや食物繊維、カルシウム、ビタミンC、などを豊富に含んでおり、抗酸化作用や血糖値低下作用、コレステロール低下作用、腸内環境改善などに効果があると言われています。
令和4年3月31日
宮城の郷土料理「おくずかけ」 R4.3.17
「暑さ寒さも彼岸まで」と言われますが、少しずつ日が長くなり春めいてきました(^^♪
明日3月18日は彼岸の入りです。
今回は、宮城県県南地域を中心に、春と秋の彼岸やお盆の時期などに食べられる郷土料理「おくずかけ」をご紹介します。
おくずかけの由来は、禅宗に伝わる仏事や法要の後にもてなされる「普茶 (ふちゃ)料理」の代表的な料理「雲片(うんぺん)」にあるという説があります。
雲片は油で炒めた野菜の葛煮(くずに)のことです。
|
 |
「おくずかけ」は普茶料理を作る際に残った野菜などを細かく刻んで葛でとじ、雲片に似せて作ったまかない料理を修行僧が食べていたのが始まりだとか。
野菜の皮や根、葉など余すところなくいただくという心が込められているそうです(*^_^*)
その後、おくずかけが地域に広まる中で、宮城県白石市の名産品「白石温麺(しろいしうーめん)」や豆腐、油揚げ、豆麩などが加わり、郷土料理として代々受け継がれてきました。
具材は地域や家庭によってさまざま。
宮城県県北の遠田地域では「すっぽこ汁」と呼ばれ、仏事の本膳の後にお手伝いの人たちに振舞われてきたそうです。
同じような料理なのに、地域によって呼び方も食べる時期も違うとは、奥が深いですね。
なんとも不思議な感じです。
ちなみに私は宮城県県南地域の出身ですが、小さい頃、我が家では白石温麺を箱買いしていて、ご飯が足りない時などに、具だくさんの温麺が出されていました。
「おくずかけ」とは呼んでいませんでしたが、今思うと、あれはもしかして「おくずかけ」だったのかもしれません。
昔を懐かしみながら「おくずかけ」を作ってみました。
【おくずかけ】
〇材料(4人分)
白石温麺1束(100グラム)、
里芋3個、人参 小1本、ごぼう3分の1本、
ささぎ6本、干ししいたけ5枚、油揚げ1枚、
豆腐 小1個、糸こんにゃく2分の1袋、
豆麩適量、水1,200㏄、
しょうゆ大さじ3、塩小さじ1、
水溶き片栗粉(片栗粉大さじ1、水大さじ2)
|

|
〇下ごしらえ
・干ししいたけは水で戻し、せん切りにします。(戻し汁は取っておきます)
・温麺はかために茹で、ざるにあげておきます。
・里芋と人参はいちょう切りにし、里芋を下茹でします。
・ごぼうはささがきにして水にさらし、ささぎは茹でて3等分に切ります。
・油揚げは油抜きして細切り、豆腐はさいの目切りにします。
・糸こんにゃくは下茹でして適当な長さに切り、豆麩は水で戻して絞ります。
材料は大きさをそろえるのがポイント!
ここまで出来ればあとは煮るだけ(^O^)
1.鍋に干ししいたけの戻し汁を入れて、人参、ごぼう、干ししいたけ、里芋の順に入れて野菜がやわらかくなるまで煮ます。
2.1に油揚げ、豆腐、糸こんにゃくを加え、しょうゆと塩で調味します。
*お好みで和風だしを加えても。
3.2に温麺と豆麩、水溶き片栗粉を加え、とろみがついたら火を止めます。器に盛りつけて、ささぎをのせて出来上がり。
*温麺を器に盛り、とろみ汁をかけてもいいです。
 
ほっこりとした素朴な優しい味わい。
彼岸とはいえ、まだまだ肌寒いのでとろみのある汁は身体が温まります(^O^)
【白石温麺(しろいしうーめん)のお話】
白石温麺はそうめんの一種ですが、麺の長さが9センチと短く、油を使わない製法なのが特徴。
約400年前の江戸時代に宮城県白石市で生まれた名産品です。
温麺の由来は、白石城下に住んでいた男が、胃病を患う父親のために消化が良く元気になる食べ物はないか探し回っていた折、旅の僧侶から油を使わずに麺を作る方法を教わり作ってみたところ、それを食べた父親が回復。
|
 |
この麺は評判を呼び白石城主 片倉小十郎に献上され、誕生秘話に感銘を受けた小十郎が「人を思いやる温かい心を持つ麺」という意味を込め、「温麺(おんめん)」と名付けたと言われています。
この功績により「味右衛門」と名乗ることを許され喜んで帰宅した男が、あまりの嬉しさに「温麺」の呼び名を忘れてしまい、うまい麺と褒めて頂いたことから「うめーめん……うーめん!」と呼ばれるようになったのだとか。
白石温麺は、胃にやさしい思いやりが込められた麺なのですね(*^_^*)
令和4年3月17日
仙台いちご R4.3.10
近頃、スーパーの入口近くには沢山のいちごがならんでいますね(^O^)
フィルムのパッケージには「仙台いちご」の表記。
宮城県産のいちごが多く出回ると、春が来たなぁと感じます♪
令和2年産作物統計調査(農林水産省)によれば、宮城県は東北一のいちごの生産量を誇り、全国では10位。
仙台いちごは宮城県全域で生産されたいちごで、平成24年に地域団体商標に登録されました。
東日本大震災の前、宮城県内では亘理町と山元町がいちごの主な産地でしたが、震災の大津波で甚大な被害を受け、栽培施設の9割以上が壊滅したといいます。
現在は新たな大型いちご団地の建設で復興に取り組み、震災前の生産量を取り戻しつつあるそうです。
|
 |
仙台いちごの主な品種は「もういっこ」と「とちおとめ」に加え、令和元年に誕生した「にこにこベリー」の3つ。
「とちおとめ」の名前の由来は、言わずと知れた栃木県生まれであることから。
「もういっこ」の名前には、一つ食べると美味しくて、ついついもう一個手を出してしまうという意味が込められ、「にこにこベリー」には「もういっこ」に続く「にこ」という意味と、食べる人や生産農家が「にこにこ」笑顔になれるようにという思いが込められているそうです。
「もういっこ」も「にこにこベリー」も宮城県で育成された品種なんですよ!
可愛いらしいネーミングですが、良く考えられているものですね(*^_^*)
特徴としては、もういっこは大粒で、にこにこベリーは切り口が赤いとのこと。
味は、 とちおとめは甘味が強く、もういっこ、にこにこベリーは甘さと酸っぱさのバランスが良いのだとか 。
全国各地で栽培されているいちごですが、その品種はなんと300種以上。
各地で品種改良が重ねられ、前述の栃木県の「とちおとめ」をはじめ、福岡県の「あまおう」、熊本県の「ゆうべに」、静岡県の「紅ほっぺ」など、ご当地ブランドとなるいちごも生み出されています。
いちごの人気の表れですよね。
|
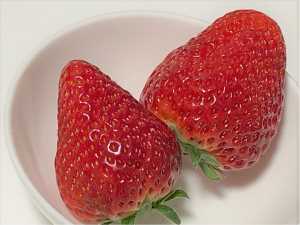
【仙台いちご もういっこ】
|
また、いちごはビタミンCが豊富。
みかんやグレープフルーツの約2倍含まれ、風邪の予防や疲労の回復、肌荒れなどに効果があると言われています。
いちごの赤い色素成分であるアントシアニンはポリフェノールの一種で、疲れ目や視力回復に効果があるそうですよ。
お疲れの方にはおすすめですね(^O^)
生でそのまま食べるのが一番美味しいと思いますが、気分を変えていちごサンドを作ってみました。
購入したいちごは「もういっこ」です。
搾るだけの市販のホイップクリームを使って、簡単に出来ちゃいました♪
|
 |
【いちごサンド】
1.食パン2枚の耳を切り、ホイップクリームをパンに塗りいちごを対角線上にならべます。
2.1の上にたっぷりのホイップクリームをのせ、もう1枚のパンを重ねて軽く押さえラップで包みます。
3.2を冷蔵庫で30分位冷やし、ラップをしたまま斜め4等分に切り、ラップをはずし皿に盛りつけて出来上がり。
3月13日はサンドイッチの日。
1が3に挟まれていることから制定されたとのこと。
3月13日は日曜日ですし、いちごや色々なフルーツ、食材のサンドイッチを作って、ランチやおもてなしを楽しんでみてはみてはいかがでしょうか(^^♪
令和4年3月10日
甘酒 R4.3.3
本日3月3日はひな祭り♪
五節句の一つ「上巳(じょうし)の節句」にあたり、女の子の健やかな成長と幸せを願う行事として「桃の節句」とも言われています。
ひな祭りといえばひな人形を飾り、桃の花やひし餅、ひなあられ、白酒、甘酒などを供える風習がありますね。
|
 |
厄払いのために飲まれる白酒にはアルコールが入っていることから、子供でも飲めるように「甘酒」がひな祭りの飲み物として親しまれるようになったのだとか。
甘酒には2種類あり、米麹甘酒と酒粕甘酒があります。
米麹甘酒は麹菌の発酵によって作られノンアルコールですが、酒粕甘酒は酒粕を水で溶き砂糖を加えて作られ、微量のアルコールが含まれているとのこと。
甘くて飲みやすいのは米麹甘酒の方ですね(^O^)
ところで、甘酒は「飲む点滴」と言われているのをご存知でしょうか。
甘酒に含まれるビタミンB群は肌を構成するたんぱく質の代謝を促すほか、食物繊維とオリゴ糖は腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整える働きがあるそうです。
特に米麹甘酒に多く含まれるブドウ糖は、消化を助け、血糖値をあげる働きがあるとのこと、まさに栄養満点ですね。
|
 |
そこで今回は、ひな祭りにちなんで「甘酒」を作ってみました(^_^)v
炊飯器で作る米麹甘酒のレシピをご紹介します。
【甘酒】
〇材料
もち米1合、乾燥米麹200グラム
*もち米の代わりにうるち米でも可。ごはんでも作れます。
1.米麹をバラバラにほぐします。袋に入れてほぐすと飛び散りません。
 
2.もち米を研いで炊飯器に入れ、3合のメモリまで水を入れて30分程度浸した後、お粥モードで炊飯します。
3.2のお粥が炊けたらよく混ぜながら60℃まで冷まして、1の米麹を加えて混ぜ合わせます。
4.炊飯器を「保温」にセットし、蓋を開けっぱなし状態でふきんをかけ温度を55~60℃に保ち、8~10時間程度保温したら出来上がりです。
途中、2、3回かき混ぜます。発酵が進んでどんどんトロトロになっていきます(^O^)♪
【ポイント】
*温度は55~60℃をキープすること。温度が高すぎても低すぎてもあまり発酵しませんよ。
*甘酒を鍋で沸騰しない程度にひと煮立ちさせると発酵が止まり、冷蔵庫で1週間程度保存できます。火入れしない場合は2、3日で飲み切りましょう。
まずは原液で飲んでみました。
口当たりがよく、砂糖でも入れたかのような優しい甘さでほっこりします(*^o^*)
お好みの濃さに薄めて温めたり冷やしたり、ミキサーでなめらかにしても良し。
牛乳で薄めたりショウガを入れても美味しいようですよ。
時間はかかりますが、作業は至って簡単です。
甘酒を飲み続けてみたら、お腹の調子が良くなりました♪
リピートして作ってみようと思います。
令和4年3月3日
|