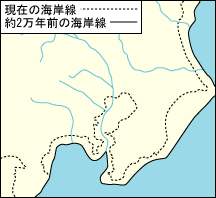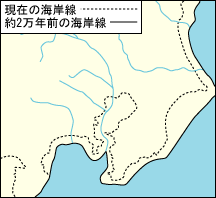1. 太古の住人と谷津田【「農」と歴史】
台地上の古代人
当事業地区の大部分を占める八街市(やちまたし)と富里市では、今から約3万年前、旧石器時代の遺跡が見つかっており、この頃には人々が生活していたことが分かっています。地質学的には氷河期に分類されるこの時代、海面は現在よりもはるかに低く、東京湾も陸続きだったようです。
その後、約6千年前、縄文時代の前期には、気候も温暖となり、海面は上昇します。旧石器時代とは逆に、現在よりもはるかに海面が高くなり、海岸線は現在の台地の端あたりまで迫っていました。関東地方では全国の約半数もの貝塚が見つかっていますが、その多くは、当時の海岸線に沿うように分布しています。
台地のほぼ中央に位置する当事業地区では、貝塚はほとんど見つかっていませんが、八街市、富里市では土器など縄文時代の遺跡も見つかっており、狩猟と採集による生活が続けられていたものと考えられます。
|
|
稲作の伝来と谷津田
|
谷津田 |
海面も低下し、現在の海岸線に近づいてきた弥生時代、日本には大陸から稲作の技術が伝わってきました。稲作はまず北九州に伝来し、西日本へと広がっていったため、関東地方に伝わるまでは比較的時間がかかったようです。初期の稲作は、その多くが河川の下流域、いわゆる湿地帯にあたる場所で営まれていました。
北総台地では、鹿島川の下流域、印旛沼(いんばぬま)の周辺で弥生時代中期の大規模な集落跡が発見されており、近くの谷底で谷津田が営まれていたものと考えられています。しかし、当事業地区では、この時期の遺跡がほとんど見つかっていません。この地区を流れる小河川は、川全体でみれば中流域から上流域に位置するため、稲作の伝来が遅れたのでしょう。
わずかに発見されている遺跡から、弥生時代の後半から古墳時代にかけて、ようやく鹿島川の中流域(八街市)や根木名川(ねこながわ)、高崎川の中流域(富里市)で谷津田が営まれ始めたことが想像できます。
| さらに詳しく |
お問合せ先