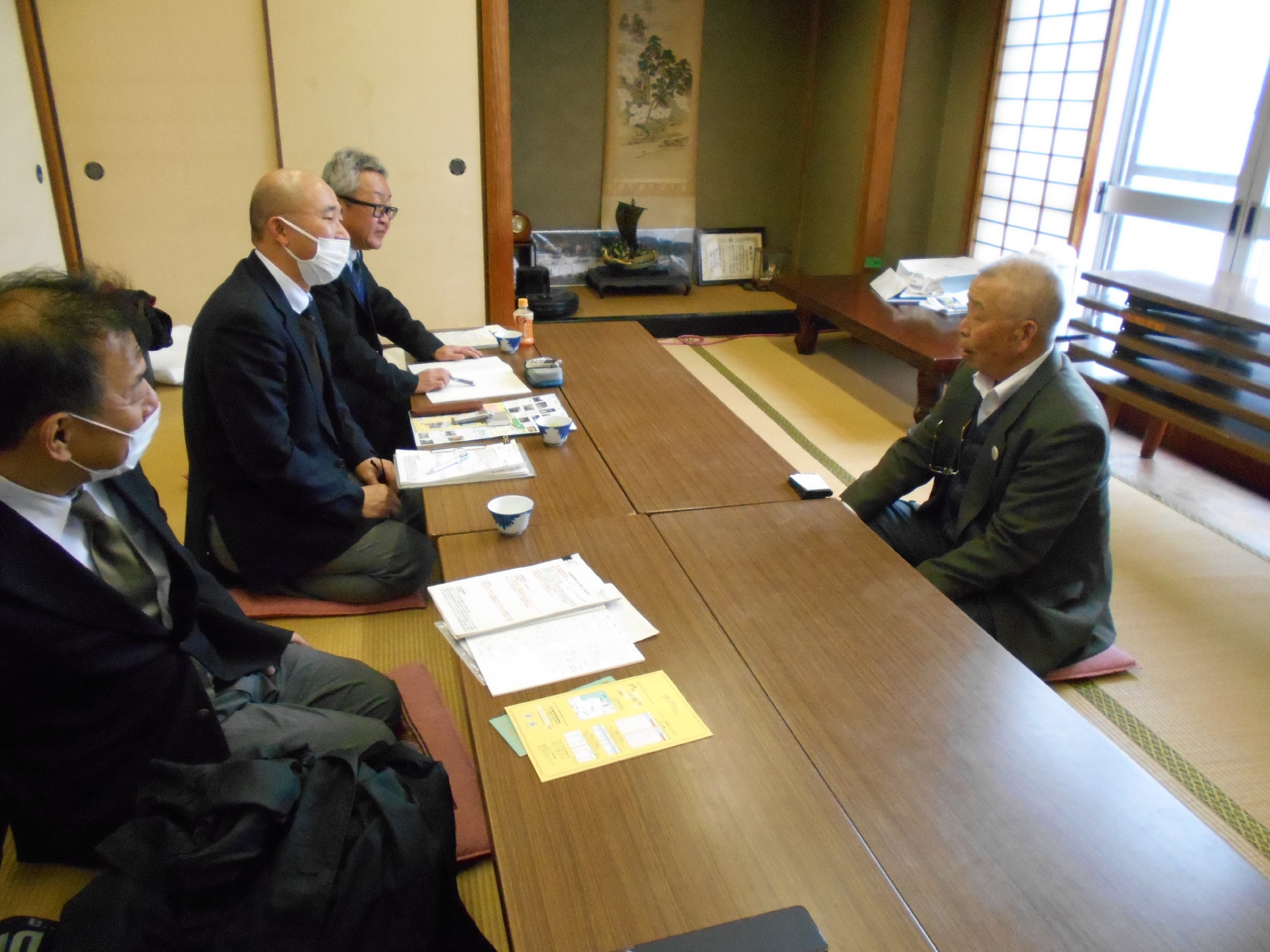日本唯一、湖上に人が暮らす島!海なし県の漁師村!
滋賀県近江八幡市|沖島漁業協同組合
近江八幡市の「沖島」にある沖島漁業協同組合を訪問し、意見交換を行いました。
「沖島」は対岸から1.5kmの沖合にあり、約240人(令和4年現在)が暮らしておられます。
 |
 |
沖島漁業協同組合
|
港からの家並み |
 |
琵琶湖の漁業を守り続けるために
奥村繁代表理事組合長に伺いました。
琵琶湖の年間漁獲量は、ピーク時(昭和30年頭)の約10,000t(うちシジミ等貝類が約8,000t)から現在では700tほどにまで減少したとのこと。減少した主な要因を聞いてみると、昭和47年から始まった琵琶湖総合開発により新たな漁港等が整備され、湖の水の流れが変わったこと、昭和40年頃まで盛んだったシジミ漁が水質汚染により衰退したことではないかとおっしゃっていました。
また、平成に入るとブラックバス等の外来魚が激増しましたが、当初は効果的な処分方法が無かったそうです。平成17年、特定外来生物に指定されてから本格的な駆除が始まり、その後は少しずつではあるが、減少傾向にあるとのことです。
|
| 沖島漁業協同組合 奥村代表理事組合長 |
|
|
昭和58年に滋賀県水産振興協会が設立され、ニゴロブナ、ホンモロコ等の放流が始まりましたが、現在でも放流した魚の生存率が1割に満たない。成魚まで育つ確率が上がる研究が進むことを期待されておられました。
外来魚の駆除については、在来魚の習性や成長に合わせた時期や場所で、集中的に行えば効果が上がるのではと考えておられました。
平成6年の琵琶湖の水位が-123cmとなった時には、スジエビ漁が翌年から平成9年にかけて危機的な状況になったそうです。
今年も80cm近く水位が下がっていたので、来年以降のことを心配されていました。
|
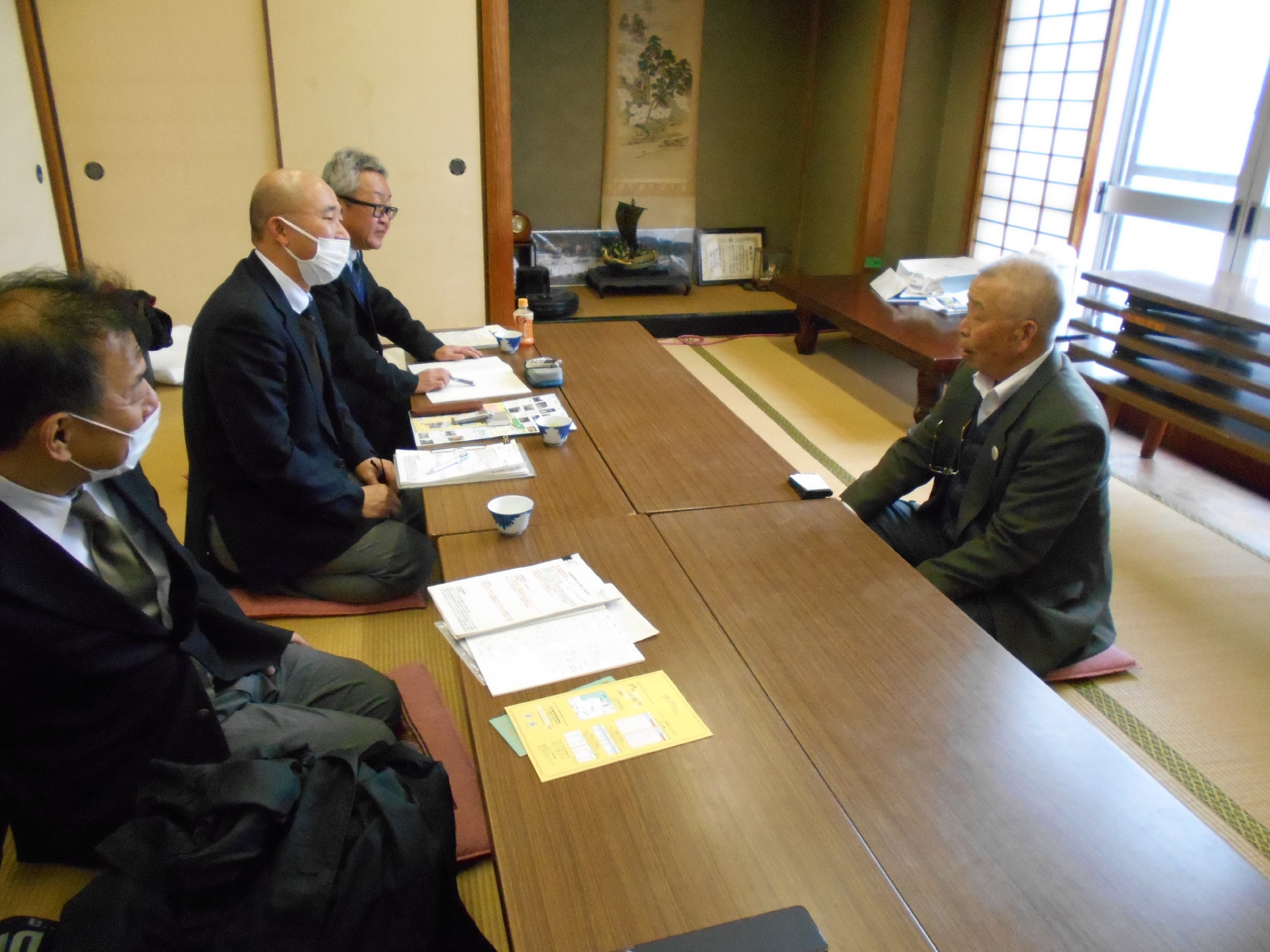
意見交換の様子 |
|
若い移住者を増やしていくためには
移住者の川瀬明日望(あすみ)さんと塚本千翔(ちしょう)さんに沖島に来られた経緯や、今後、若い移住者を増やす方法などを伺いました。
|

意見交換の様子
|
 |
川瀬さんは令和2年3月に近江八幡市の地域おこし協力隊員として沖島に来られました。島の魅力をアピールするために琵琶湖で獲れた魚を使った料理を京都市や近江八幡市のお店を借りて提供されたり、SNSや地域の情報誌を使って湖魚料理の情報発信をされていました。
地域おこし協力隊の任期満了1年前から漁協の仕事に関心があったそうで、現在は沖島漁協の職員として、計画されている「滋賀県1漁協(合併)」に向けた業務や、沖島漁協の施設改修業務に携わっておられます。
若者の移住については、最初から永く住む前提ではなく、短期間の移住にも対応できる環境があれば呼び込みやすいのではとおっしゃっていました。
|
|
沖島の風景をバックに川瀬さん (写真 ご本人提供)
|
|
|
塚本さんは、沖島の魅力に惹かれて島の民泊施設「湖心(koko)」の初代管理人になられました。
イベント等で湖魚やその加工品をPR・販売する際、「もっと魚のことを理解したうえで説明できないか」と奥村組合長のもと、国の研修事業を3年間受講され、令和5年、見事に漁師として独立されました。
漁師として約1年が経ち、昨年と比べて漁の技術は向上しました。 市内の料理店などに直接販売することで収入単価を上げるとともに、お客さんの顔が見えて、今はとても楽しいとおっしゃっていました。
若い人の移住については、求人窓口を一本化して、「移住マニュアル」を作成するなど「見える化」が必要だとおっしゃっていました。
|
 |
|
船上の塚本さん (写真 ご本人提供)
|
沖島漁業協同組合HP: http://www.biwako-okishima.com/
お問合せ先
滋賀県拠点 地方参事官室
TEL:077-522-4261