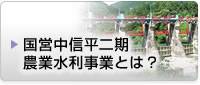2.みどころ【地域情報】
松本城
松本城(まつもとじょう)は室町時代末期の1504年に、この地方で大きな勢力を持っていた小笠原貞朝(おがさわらさだとも)が築城させたものです。戦国時代には武田信玄(たけだしんげん)がこの城を信濃(しなの)への進出の拠点とし、その後も小笠原氏、石川氏、戸田氏、松平氏、堀田氏、水野氏とめまぐるしく城主は交替しますが、1725年に入封した戸田氏が9代にわたって居城し、明治維新を迎えます。松本城の天守は五層六階の大天守を中心に、三層の乾小天守(いぬいこてんしゅ)を渡櫓(わたりやぐら)で連結し、さらに二層の辰巳附櫓(たつみつけやぐら)と一層二階の月見櫓(つきみやぐら)を複合した均整のとれた珍しい構成です。これらの天守群は国宝に指定され、大天守は五層六階としては現存する日本最古のものです。

奈良井宿
難所の鳥居峠をひかえた奈良井宿(ならいじゅく)は、中山道(なかせんどう)のちょうど中央にあたる宿場町で、かつては街道を行き交う旅人で栄えました。その様は「奈良井千軒」と謳われ、木曽路(きそじ)一番の賑わいでした。奈良井宿は鳥居峠の上り口の鎮神社(しずめじんじゃ)を京都側の入口とし、奈良井川(ならいがわ)に沿って約1kmの中山道沿いに町並みが形成されています。昭和53年には国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、現在も旅籠(はたご)の軒灯、千本格子(せんぼんこうし)など江戸時代の面影を色濃く残しています。そして「美しい日本の歴史的風土100選」にも選定されました。

お問合せ先
農村振興部水利整備課ダイヤルイン:048-740-9836