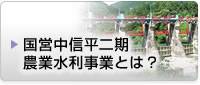3.特産物【地域情報】
わさび(安曇野市)
日本一の生産量を誇る安曇野市のわさびは、北アルプスから湧き出る豊富な湧水を利用したわさび畑で栽培されています。さしみ、そば、すしなどの香辛料として、すりおろしたものが親しまれていますが、「わさび漬」やわさびの「花のおひたし」など、産地ならではの味覚も人気があります。

スイカ(波田町)
火山灰土壌で、気象は昼夜の寒暖が大きく日照時間も多いことから、波田町はスイカの栽培に適しています。そのため、糖度が高く、シャリシャリとした食感で、品質の良いスイカができます。波田町では、昭和26年から普及した接木苗(つぎきなえ)利用による移植栽培、昭和35年頃から普及したマルチ栽培により生産の安定と省力化を実現し、スイカは町を代表する特産物となりました。スイカの成分のほとんどは水分ですが、利尿作用のあるカリウム、リン酸などの成分含有量が多いため、高血圧や動脈硬化、腎臓病の予防、むくみなどに効果があると言われています。

柿(朝日村)
朝日村では、「朝日村の特産品を考える会」の中で朝日村で収穫される渋柿(しぶがき)の商品化に取り組んできました。柿はポリフェノールやビタミンCが多く含まれ、健康に良いとされる果物です。サラダやフライが美味しくなる「柿ドレッシング」と「柿ソース」を開発し、主な特産物である高原野菜とあわせて提案しています。
写真提供:朝日村
やまいも(山形村)
日本に古くから自生し、「山うなぎ」と言われるほど、滋養強壮に良いことで知られているやまいもですが、長野県での栽培の歴史は古く、江戸時代から自家用に生産が行われていたといいます。戦後になると販売用の生産が本格化していきました。
特に、山形村は、長いもの産地として知られており、年に30~35万ケース(1ケース10kg)の出荷を誇っています。山形村の長いもの特徴は、火山灰土(かざんばいど)の土壌の影響から、甘くて粘り気が多いことだといいます。
タンパク質やミネラルを豊富に含んだ長いもは、健康食品としても注目されています。

ブドウ、ワイン(塩尻市)
塩尻市の桔梗ヶ原(ききょうがはら)では、年間の日照時間が長いという特徴を生かし、ブドウ栽培が盛んに行われています。ブドウの生産が行われるようになったのは、明治23年のことです。厳しい冬の寒さに苦しめられながら、海外から栽培に適した苗を取り入れるなど工夫を行い、ナイアガラやコンコードなど現在の代表品種の栽培が行われるようになっていきました。
大正時代からは、ワインの醸造業も盛んに行われるようになり、市内には、いくつものワイナリー(ワイン工場)があります。海外のワインコンテストで賞を受賞するなど、ワインの一大産地として高い評価を得ています。
写真提供:塩尻市農業協同組合
りんご(安曇野市)
長野県は、青森県に次ぐ全国二位のりんご産地として有名ですが、中でも安曇野には、広大なりんご畑が広がり、高品質なりんごが生産されています。おいしさの理由は、日照時間の長さと昼夜の温度差にあるといわれ、蜜がたっぷりつまった甘いりんごは高い評価を得ています。
代表的な品種は、「つがる」と「ふじ」で、五月には、りんごの白い花が畑一面を埋め尽くし、訪れる人を楽しませてくれます。

おやき(松本市)
おやきは、長野県の代表的な郷土食として有名です。小麦粉や蕎麦粉(そばこ)に水を加えて練り、薄くのばした生地であん(具)を包んで焼いて作ります。あんの材料は、野菜や山菜が一般的ですが、地域や家庭によって、小豆あん、野沢菜(のざわな)、なす、おから、きのこ、かぼちゃ、切り干し大根など、いろいろな具が使われます。調理法も、囲炉裏(いろり)の灰の中に入れて蒸し焼きにしたり、フライパンなどで焼いたりと、それぞれに特徴があります。
もともとは、米の収穫が少ない地方で、代用品として蕎麦とともに食べてられたことが、おやきの始まりだといいます。また、山に囲まれた豪雪地帯の保存食としても重宝されました。現在は、みやげ物としても人気があります。

お問合せ先
農村振興部水利整備課ダイヤルイン:048-740-9836