令和6年度東海消費者行政ミーティング~食をめぐる施策について~(岐阜県会場)(令和7年1月15日)
東海農政局は、食に関係する各方面の方にご参集いただき「農林漁業体験の推進」をテーマとして意見交換を実施しました。
日時
令和7年1月15日(水曜日)13時30分から15時30分
場所
ワークプラザ岐阜(岐阜県岐阜市鶴舞町2-6-7)
出席団体等
西美濃農業協同組合 女性部 ふるさと隊 代表 椙岡 智子氏
西美濃農業協同組合 総合企画部 地域ふれあい課 田中 優美華氏
生活協同組合 コープぎふ 常務理事 多村 幸司氏
STOYAMA Farm School 山里楽耕 代表 安藤 俊人氏、安藤 由美子氏
合同会社 地域と協力の向こう側 代表社員 中田 誠志氏
一般社団法人 ぎふの田舎へいこう推進協議会 事務局長 三島 真氏
岐阜県 農政部 農産物流通課 地産地消係長 宮崎 暁喜氏、地産地消係 技師 小林 映里奈氏
各務原市 産業活力部 農政課 参事 服部 憲浩氏、主事 市川 貴雅氏
(順不同)
主な内容
1.各団体の活動等について
西美濃農業協同組合 女性部 ふるさと隊
- 次世代を担う地域の子どもたちに食農教育活動を展開。体験は栽培・収穫・加工の過程を順に行い、継続して食のあり方や農の関係を学び、いのちの大切さを感じてもらうことが目的。
- 主な活動は小学3年生を対象とした海津市産大豆を教材とした出前授業。大豆の播種・栽培・収穫、豆腐の加工まで行う。本年度は管内(2市6町)の50校を目標に実施中。
- 地域の親子に向け、農業体験や紙芝居等を使った食農教育を実施。
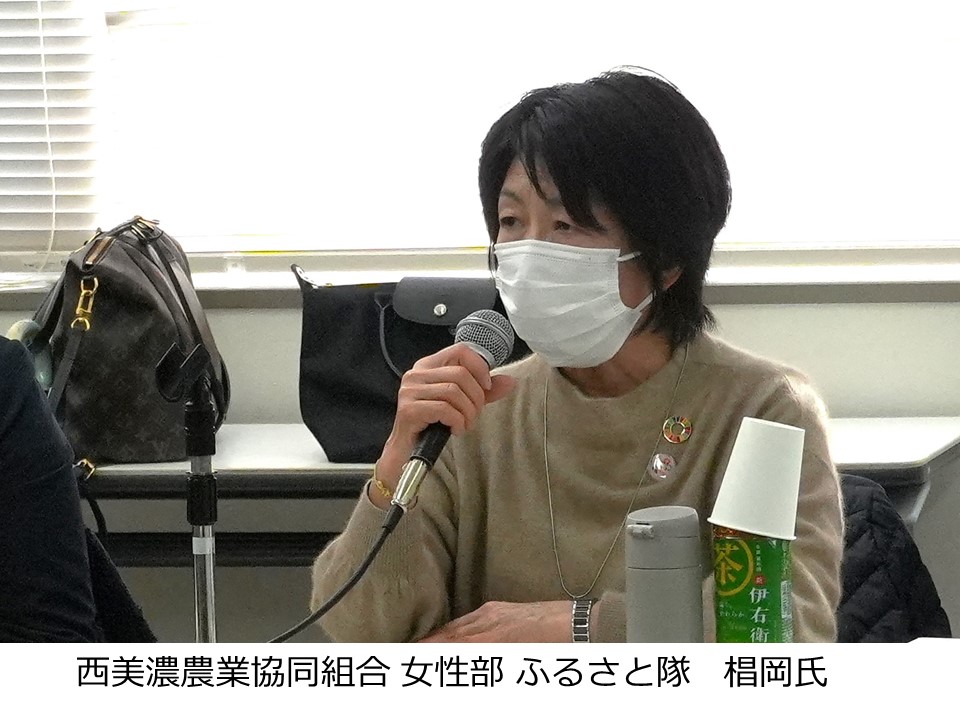

生活協同組合 コープぎふ
- 親子を対象とした食育活動(農業体験)を実施。
- 西美濃農協、東美濃農協と連携して米づくり体験(田植え、稲刈り)を実施しているが、人気があるため抽選で参加者を選定している状況。
- お茶の産地・メーカーと生協の交流の場をつくるための茶摘み体験、ソース・ケチャップメーカーのコーミ株式会社と連携した加工用トマトの収穫体験、中濃森林組合、関市や岐阜県等と連携した森づくりの体験(桜の植樹・椎茸の収穫)なども実施。
- 自前のほ場がないので生産者等の理解・協力が必要。

SATOYAMA Farm School 山里楽耕
- 2020年に恵那市内に家・農地・山林を取得。現在、生産活動と農家民宿を行っている。
- 取得した農地や山林を使って四季を通じたさまざまな体験を実施。体験は米作り・キノコの菌打ち・薪割り・しめ縄づくりなどで、体験者の要望に応じてオーダーメイドでメニューを作成。
- 敷地内にキャンプ場を整備し、小学校高学年を対象として水汲み・薪割り・野草摘みなど行う2泊3日の体験メニューを開始。
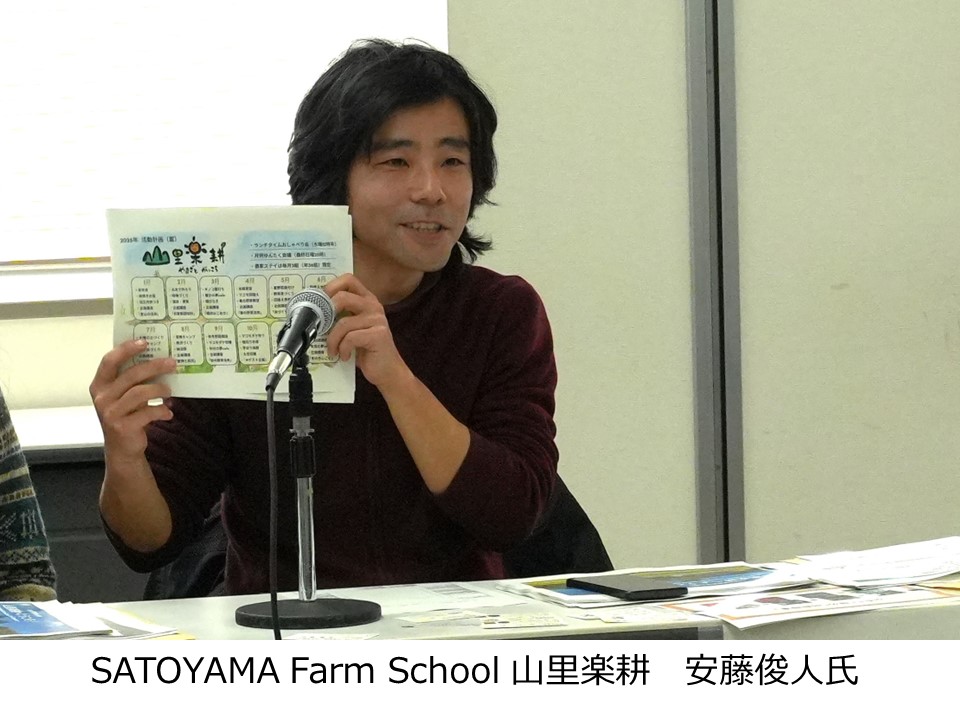

合同会社 地域と協力の向こう側
- 関市で古民家を再生したカフェを拠点に農業体験を実施。地域の農山村資源を活用し、地元の農事組合法人(自らも組合員)などと連携して事業を実施。
- 食べるだけ、買うだけではなく一連の体験を楽しむことにより、農山村との関わりを深めるなどの新たな関係性を構築することを目指している。
- 小学生対象の課外授業(農業用水の探求学習)・高校生のカフェ経営体験・大学生のワーキングホリディ(農業体験)の受け入れ・学校給食へのジビエの提供なども実施。
- 干し芋づくり、そば打ちなど加工品づくりの体験でも、「せいろで蒸す」「石臼でひく」など他では体験できないひと手間を加えることにより、人気となっている。
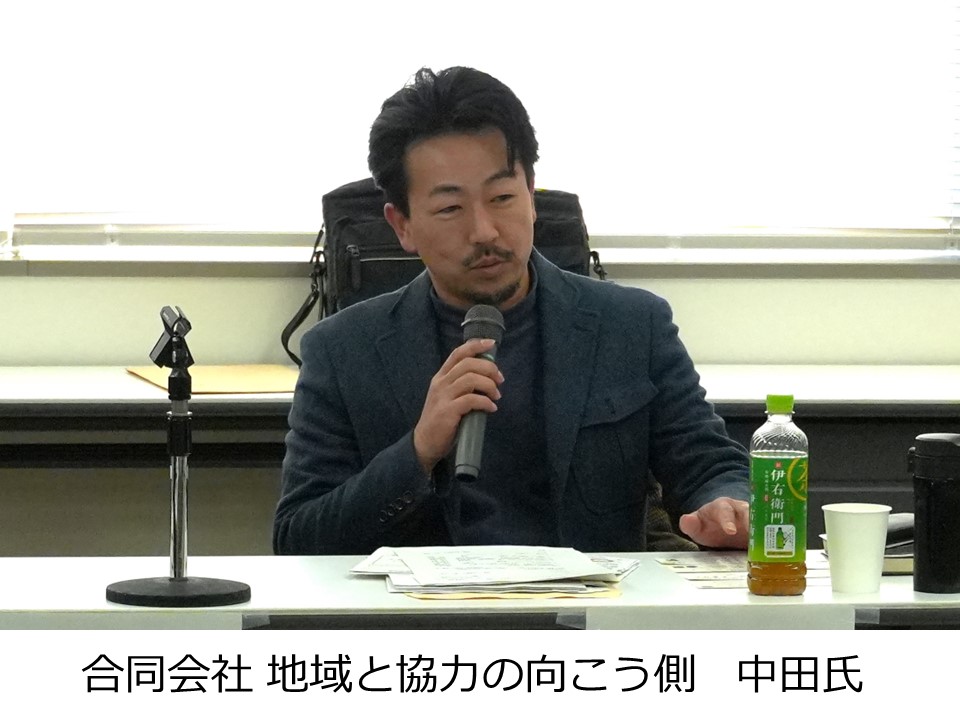
一般社団法人 ぎふの田舎へいこう推進協議会
- 平成29年5月にグリーンツーリズムを行う団体の取りまとめ役として発足。現在は135団体が加盟。
- 当初は補完的収入としてグリーンツーリズムに取り組む農業者の参加が多かったが、現在は自らのライフスタイルを発信する移住者の参加が増加。
- 会員同士の横のつながりを作るためのブロック交流会、メニュー作りのアドバイスなど地域の課題解決のための出前講座を実施。
- 県内の特徴ある地域を10か所選定し、地域貢献型体験ツアー【GIFU-DO農泊】を企画し、一元的に情報を発信。
- ツアーは1泊2日で農村体験&交流、地域貢献、地域の食体験という3要素で構成。
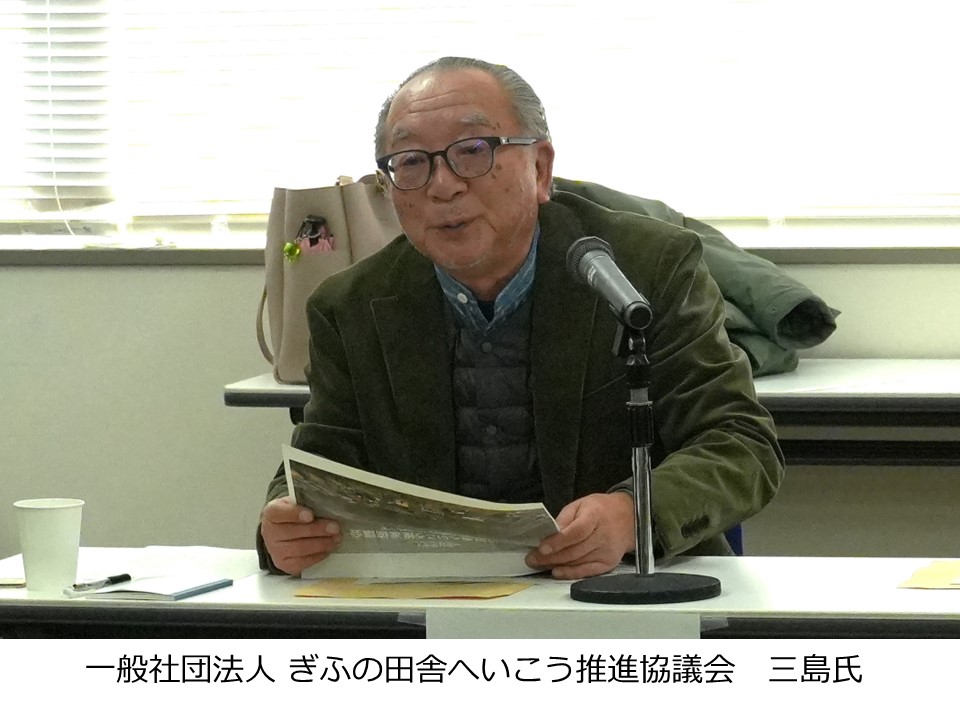
岐阜県 農政部 農産物流通課
- 消費・安全対策交付金を活用し、岐阜市において「岐阜市食生活改善推進員」活動支援、高校生への食育セミナー、幼児に対する調理体験を実施。
- 事前・事後にアンケートを実施し、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日食べている者の割合が81%から100%になり、食に関する意識の向上が確認できた。
- 一般市民に対する農業体験(大豆栽培、みそづくり)を実施する民間団体も支援。
- 小中学生と保護者を対象に、地域の特産品の収穫体験などを行う食農イベントを県内5か所で実施。
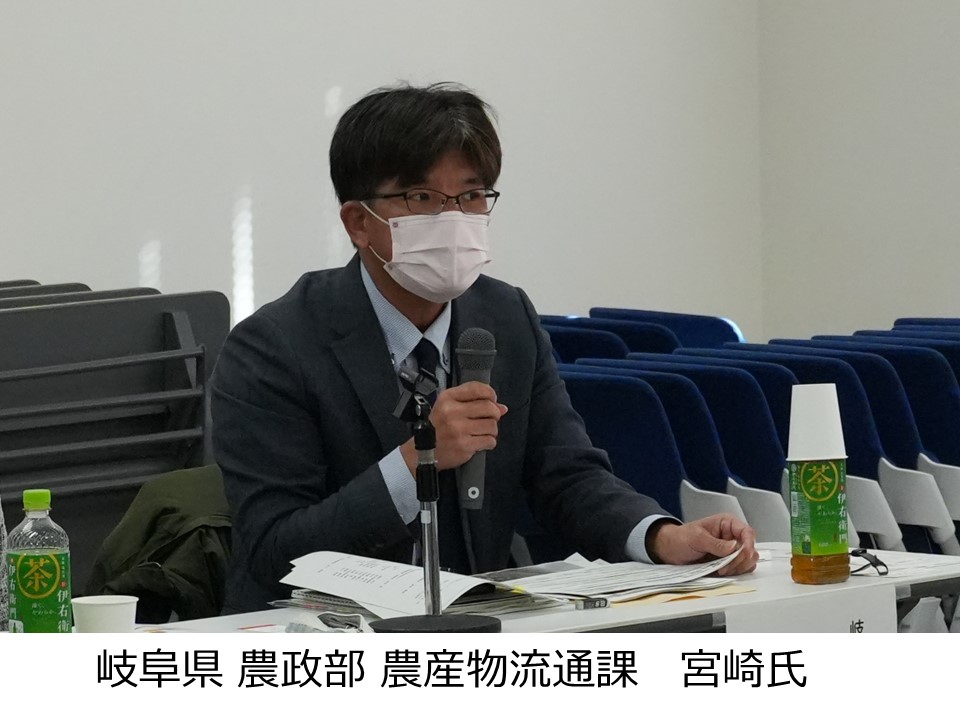

各務原市 産業活力部 農政課
- 岐阜大学応用生物科学部・各務原市畜産振興会・各務原市の三者連携で、市内小学校の高学年を対象として畜産体験を平成29年から実施。コロナで一旦中止したが、令和4年より秋休みに時期を変えて再開。
- 岐阜大学の農場で牛の乳しぼりや餌やり、聴診器で心音を聞くなどの体験を学生の協力を得て実施。
- 例年、定員の2倍以上の応募者があり、感想も好評。


2.意見交換
(1)体験内容の充実
【生活協同組合 コープぎふ】
自分たちだけでできることは限られているので、産地の方々や関係する諸団体との連携を重視している。
田植えに参加した方は優先的に稲刈りに参加できるよう配慮し、お米を作る一連の流れを学べるようにしている。
【合同会社 地域と協力の向こう側】
普段自分たちがやっていることを体験のメニューとしている。
食事と体験をセットにして理解を深めてもらい、農産物も購入してもらう。
年配の体験者の中には、ボランティアスタッフでいいから運営サイドとして手伝ってみたい、という人も出てきたがマネジメントが難しい。
【SATOYAMA Farm School 山里楽耕】
オンラインコミュティで自分たちの活動を発信している。
体験メニューを提供しながら、一緒に活動してくれる仲間を増やしている。
「田植えにきたら稲刈りもやりたい。自分たちの食べるものを自分たちで作りたい。」という会員が増えてきた。
【一般社団法人 ぎふの田舎へいこう推進協議会】
農業体験は天候に左右されるので雨天用のプログラムを作り対応している。
農作物の収穫期間は限られるため、同じ体験を何度もできないという課題がある。
(2)スタッフの確保
【一般社団法人 ぎふの田舎へいこう推進協議会】
スタッフは、体験メニューを確立していく中で増やしていく形になる。
アウトドアスポーツを行っている団体などは夏と冬が忙しいが、春と秋の農作業主繁忙期は時間があるため、農業体験を手伝ってもらえると年間を通じたスタッフ確保が可能になる。
(3)学校との関係
【西美濃農業協同組合 女性部 ふるさと隊】
地区ごとに代表がJAと一緒に教育委員会や校長に話に行っているが、断られる地区がある。
大きい市町村の場合、生徒数が多く調理室に一度に入れず分ける必要があり、時間割的に難しいというのが断りの理由。
また、教育委員会が非協力的な地区もある。
児童との対応が近年難しくなってきていることや、ボランティアの高齢化が進んでいることもあり、ボランティアスタッフの確保も課題となっている。
【各務原市 産業活力部 農政課】
子どもたちを交えて行事を行う際は、教育委員会部局(校長会・教育長)とやり取りをしながら計画を立てている。
体験時に事件・事故が発生することもあり得るので、保護者に説明し、同意を得た上で実施している。
(4)高校生、大学生、20代への食育
【SATOYAMA Farm School 山里楽耕】
オンラインコミュニティでつながった人たちが体験で来てくれて、その人たちがSNSで発信してくれている。
SNSの効果はあると考える。発信してくれるのは人間関係がきちんとつながっている人たちで、20~30代の独身女性が多い。
【合同会社 地域と協力の向こう側】
我々は高校生や大学生向けにSNSを発信していないしする必要もないと思う。
動画コンテストに出したいなど明確な目的をもっている高校生は自ら来る。
大学生も同様でテーマが関係している者は向こうから来る。
大切なのは8歳~10歳に至るまでの幼少期の経験。
この時期の経験がしっかりできていれば、学生の時期でも、家庭を持ってからでも、自ら体験の場に戻ってくると思っている。
【各務原市 産業活力部 農政課】
高校生や大学生の農業体験が手薄なのは、発信の仕方が悪いのでは無く、ある意味自然なことではないか。
その層を取り入れるのであれば、その層をターゲットとしたメニューを提供することが必要。
【一般社団法人 ぎふの田舎へいこう推進協議会】
ぎふの田舎応援隊のボランティアの内、2割は10代から20代。
その若者たちはボランティアに非常に積極的で、相手の役に立ちたいという気持ちが強い。
若者に対しては、きちんと「手伝ってください。助けてください。」というアプローチをした方が良いのではないか。
(5)移住を視野に入れての体験
【一般社団法人 ぎふの田舎へいこう推進協議会】
体験に来る人は都会での生活にはない部分を求めているので、移住にはつながらないと考える。
他方、受け入れ側に立って手伝いに来る学生や若者は地域のことを理解し、愛着を感じるようになるため、移住することがある。
【岐阜県 農政部 農産物流通課】
名古屋市中心部にあるイベント広場(オアシス21)に岐阜県のアンテナショップを設置し、移住相談窓口を設け、農業を目的とした移住相談も受け付けている。
(6)新たに体験を始める場合の地域のつながりなど
【合同会社 地域と協力の向こう側】
地元の事情を理解し、地域との関係を構築することが基盤となる。
体験の内容について価格・スパン・キャパなどをしっかり考えて、無理のない計画を作ることが一番の軸となる。
【SATOYAMA Farm School 山里楽耕】
集落一つ違えば全く違う場所になる。その集落で人間関係を作っていくことが大事。
新規で始める場合は農地の取得(農業者でないと農地を借りることができない)、農業機械の購入(高額であり負担が大きい)へのサポートが必要。
農作物を食べられてしまうと体験ができなくなるので、獣害対策が重要。
(7)農林水産省への要望
【一般社団法人 ぎふの田舎へいこう推進協議会】
小さな農家が、地域の特色ある農産物を生産し、伝統食を支えていたりする。そういう農家を切り捨てないような政策も考えてほしい。
消費者行政ミーティングの様子




お問合せ先
消費・安全部消費生活課
担当者:消費者対応班
代表:052-201-7271(内線2807)
ダイヤルイン:052-223-4651




