令和6年度東海消費者行政ミーティング~食をめぐる施策について~(三重県会場)(令和7年1月22日)
東海農政局は、食に関係する各方面の方にご参集いただき「農林漁業体験の推進」をテーマとして意見交換を実施しました。
日時
令和7年1月22日(水曜日)13時30分~15時30分
場所
三重県総合文化センター(三重県津市一身田上津部田1234)
出席者
株式会社 伊賀の里モクモク手作りファーム マネージャー 小松 浩也氏
生活協同組合 コープみえ 組織活動推進部 組織活動推進課 課長 長澤 理史氏、宅配事業部 商品活動推進課 岡田 誠一氏
有限会社 マルシゲ清水製茶 かぶせ茶カフェ、販売部門 担当 清水 加奈氏
JLLリテールマネジメント株式会社 渉外マネージャー 長岡 敏氏
国立大学法人 三重大学 大学院 生物資源学研究科 フィールドサイエンスセンター付属施設農場 農場長・教授 名田 和義氏
三重県 農林水産部 フードイノベーション課 課長 行方 典子氏、主事 菰方 彩貴氏
四日市市 商工農水部 農業センター 所長 岸田 諭祀氏
玉城町 産業振興課 主事 江島 知樹氏
(順不同)
主な内容
1.各団体の活動等について
株式会社 伊賀の里モクモク手作りファーム
- 宿泊施設を併設する体験施設。米、野菜、イチゴ、しいたけなどの収穫体験のほか、ウインナーやパン作り体験も実施。宿泊者には、朝の乳しぼり体験後、朝食でその牛乳を提供。
- 我々の活動に理解のある方が、ファン(リピーター)になっていただいていると理解。
- 2005年あたりから食育を目的に入社するスタッフが増えたが、最近は減っている印象。

生活協同組合コープ みえ
- JAの協力を得て、米作り体験(田植え、収穫、精米工場見学など)、みかん産地交流会(柑橘選果場見学、ミカン収穫など)を実施。
- 四日市市ふれあい牧場と連携し、乳しぼり、アイスクリームづくり体験を実施。
- 組合員と水産会社で商品を共同開発。
- 農業体験は人気があり、定員の20倍の応募あり。メディアにもPRし、参加できなかった組合員にもコープの活動が伝わるように心がけている。
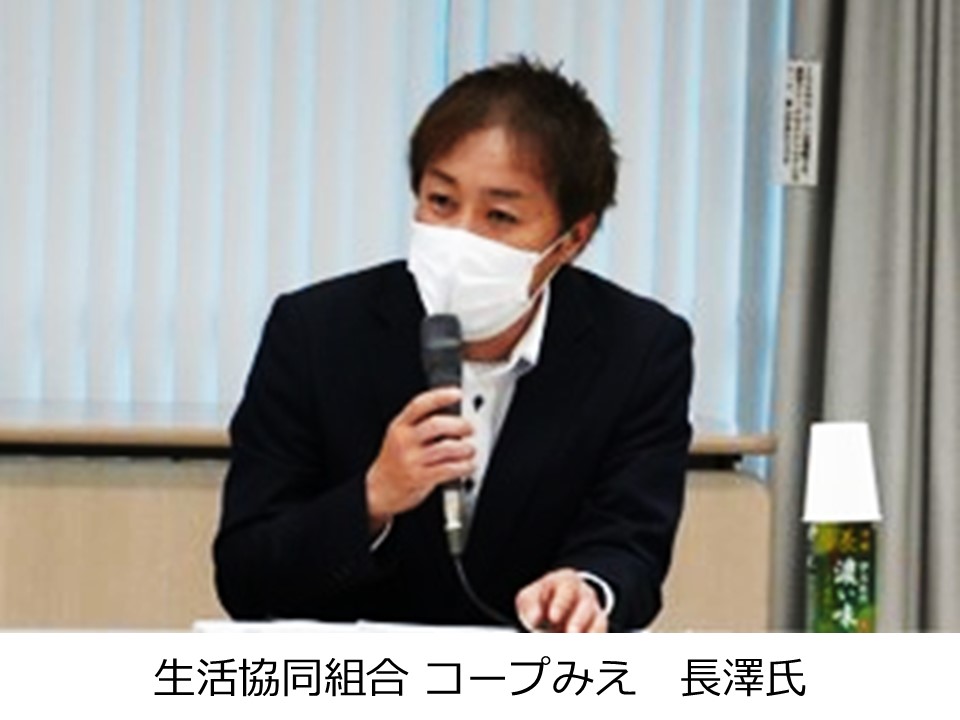

有限会社 マルシゲ清水製茶
- 家業のお茶栽培・製造のほか、かぶせ茶を多く知ってもらうため、「かぶせ茶カフェ(お茶は急須で入れる)」も経営。
- 茶摘み体験は新茶の季節に行い、茶葉の天ぷらも提供。リピーターも多い。茶摘み体験者は若い人も多く、お茶が好きになって繁忙期にアルバイトとして来てくれる人も多い。
- 茶摘み体験は自然相手でもあるので、予定どおりの時期にできないこともある。

JLLリテールマネジメント株式会社
- VISONを食の聖地とするため、スペインのサンセバスチャン市を地方再生のモデルとして、敷地内に農業体験のできる畑を用意した。日本の発酵文化や地域食材の普及支援を目指したい。
- 体験で収穫した野菜が食べられるレストランがある。収穫体験の場に加えて、自然農法を学べる自給自足カレッジも設けており、参加者は20代から60代まで幅広く、東京から通う人もいる。
- 食べ歩き・食事のエリアにある店舗では、体験(みそ作り)や見学(大根漬の製造)が可能。
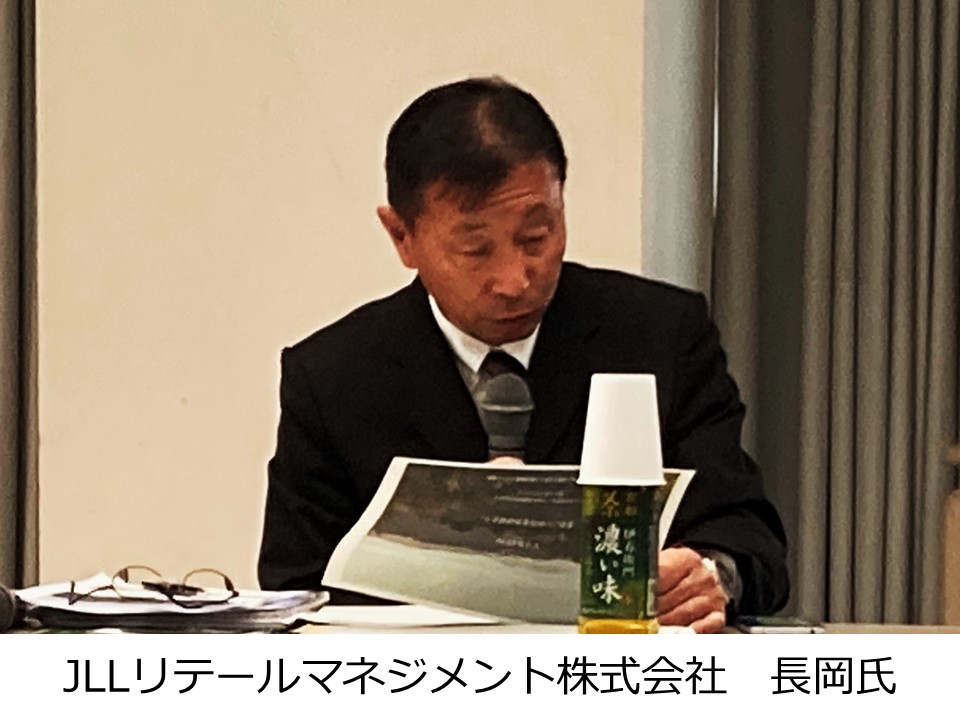
国立大学法人 三重大学
- 三重大の活動は、学生への農場実習、野菜果物等の生産性・品質向上に関する研究のほか、社会貢献活動として、子どもたちへの農業体験機会の提供がある。
- 農業体験は、小学生を対象に米、大豆(豆腐作りまで)、サツマイモ、ミカン、茶を実施しており、彼らは中学生になると職場体験として再訪してくれる。
- こういった体験が食への関心を高めることにつながっていると思う。子どもたちが家庭内で体験を話題にすることが一番の波及効果。
- 子どもたちと接することで教職員もやる気が出るといった効果もある。

三重県 農林水産部 フードイノベーション課
- 第4次三重県食育推進計画に基づき、三重県食育推進連絡会を設置し、庁内の食育関係課と連携しながら食育を推進。
- 令和5年度は小学生や大学生を対象に、もやしの生産工程見学を行い、小学生には給食でもやしを提供。
- 栄養教諭向けの体験(収穫体験や生産者への聞き取りなど)も行っており、実施内容をもとに食育教材を作成し、県内の栄養教諭に配布している。

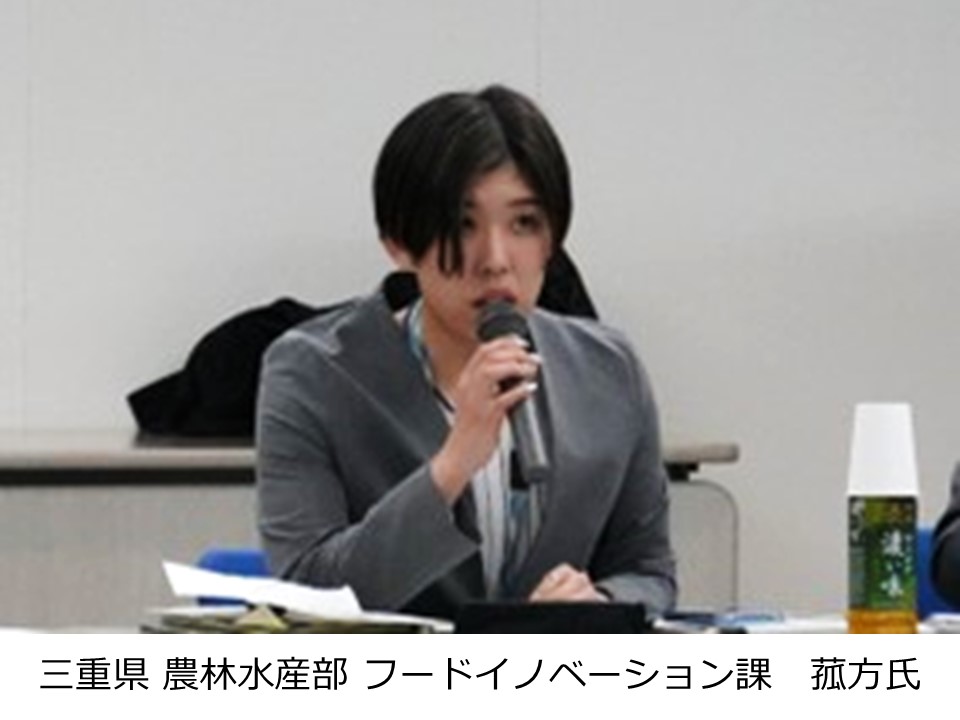
四日市市 商工農水部 農業センター
- 農家への支援や市民への農業に触れる場の提供を目的に、体験を実施。
- 栽培体験は、保育園児、小学生を対象に、栽培、収穫、加工といった一連の流れで実施。昨年は収穫したサツマイモを鬼まんじゅうに加工。
- 親子収穫体験は、年3回の「よっかいち農業マルシェ」に合わせて実施。加工・収穫体験は、市の広報で募集をかけて、春、夏、冬に計5回実施。
- 隣接の学校給食センターとの連携講座(夏休みと冬休みに小学生を対象に実施)では、農業センターが収穫体験と野菜クイズを、給食センターが収穫した野菜の調理体験を担当。こうした体験が、食に興味を持ってもらえることにつながっている。

玉城町 産業振興課
- 農業振興を目的に、小学生向けの農園見学と町民向けの講座(「玉城版農業大学」と称し、三重大教授を講師に招聘)を実施。講座の参加者の多くは、大変満足と評価。このほか、サツマイモの植付体験等も実施。
- 全国的に農業従事者が減る中、玉城町の若手農業者の中には新技術を取り入れている者も多く、小学生に最新の農業を見せることにより農業に興味を持ってもらえるようにしている。
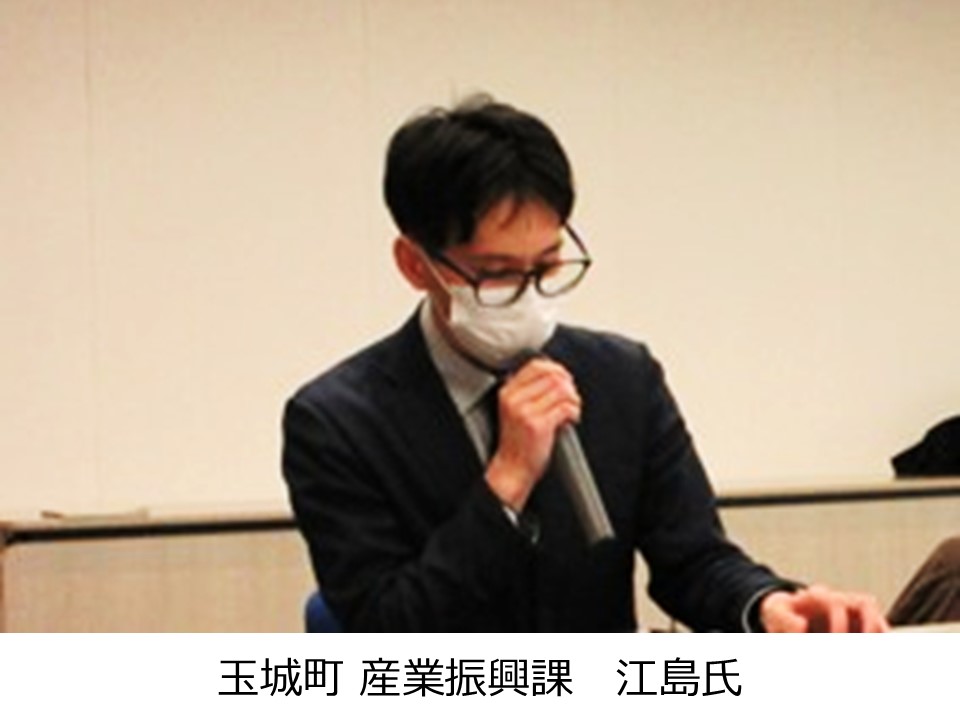
2.意見交換会の内容
(1)農林漁業体験における人手不足・体験内容の充実
【有限会社 マルシゲ清水製茶】
体験は収穫時期に当たるため、アルバイトを入れながらやっているが、受け入れ態勢には限界がある。
【株式会社 伊賀の里 モクモク手作りファーム】
体験はスタッフ2名で対応しており、人手不足のため体験の専任は難しく、他の業務を抱えながら担当してもらっている。業務量の半分ぐらいが体験というイメージ。
【JLLリテールマネジメント株式会社】
VISON内の農園で実施している「収穫体験」も、「自給自足カレッジ株式会社」が実施している農作業体験も有料サービスであり、有機農業にも詳しい専任のスタッフを配置している。
【生活協同組合 コープみえ】
コロナ禍での体験はリモートを活用したが、匂いを感じたり、土に触れたり、生産者と交流したりできず、記憶に残りづらかった。
ただ続けているだけでは形骸化・マンネリ化するので、最近は体験後に農家との交流会の機会を作っており、このことが農家にとって刺激になっているのでぜひ続けていきたい。
受入数に限界はあるものの、参加者集めにおいて、新聞やニュースに取り上げてもらうことは広く知ってもらう意味で必要。
【国立大学法人 三重大学】
現状では近隣小学校のみを対象としており、もっとたくさん受け入れたいという思いはありつつも、対応する現場的には今の数がちょうどいい。
この規模だからこそ20年間続けられた。
大学としては、細く長く(少人数で長期間)を選択していることに意義を感じている。
(2)学校との関係
【四日市市 商工農水部 農業センター】
ほ場の広さ、職員の数の制約から、近隣の幼稚園と小学校を対象としており、先生方は栽培期間を通じて作物の観察と世話に来てくれるが、少し離れた校園はそうもいかない。
中学生になると収穫体験ではなく、職業体験という形の受け入れをしている。
転勤した先生の情報からか、遠方の学校から職業体験の依頼を受けることもある。
【三重県 農林水産部 フードイノベーション課】
学校との関係では、まずは影響力の高い栄養教諭に生産現場の見学をいただいている。
先生方の反応は非常によく、この事前見学は県として力を入れているところ。
(3)高校生、大学生、20代への食育
【三重県 農林水産部 フードイノベーション課】
小学校、中学校での農業体験はあるが、高校になると食育の教育がなくなる。
一部の高校では農業体験を地域課題解決型キャリア教育の一部として取り組んでいるが、全体では困難。
【国立大学法人 三重大学】
ずっと農業への思いを持っているような学生は、自発的にボランティアとして農業体験に関わる者も多い。
三重大では、学生が地域おこし的なクラブを立ち上げ、畑を借りて作物を栽培し、地域の人と相談して派手な看板を作ったりして、自主的に農業にかかわっている。
【有限会社 マルシゲ清水製茶】
体験に来る年齢層は幅広い。SNSをうちの高校3年生の娘が作ったものに変えたところ、フォロワー数が倍増し、若いお客さんが増えた。若い世代にはSNSが必須と痛感。
四日市農芸高校とコラボプロジェクトを行っており、先日は、四日市商業高校も加えてイベントを開催したが、市内でも高校生同士のつながりが意外にないことを知った。
農業には商業の知識も必要だし、横のつながりが増え、地元に残って農業をする人が増えれば人口流出の歯止めになると感じた。
(4)農林漁業体験の持つ効果
【株式会社 伊賀の里 モクモク手作りファーム】
年末に来場した中学校教師から「こどもの頃、モクモクで農業体験をした。教師を辞めて今度、鳥取県で、兄弟で就農する予定」と聞いた。うちの体験がきっかけで獣医を目指している子もいる。
20年ぐらい体験を行っているが、まいた種が芽生えてきたと感じている。
【JLLリテールマネジメント株式会社】
自給自足カレッジに来る方は、東京と三重からが多い。自給自足カレッジは、農業者を増やすだけでなく、自給自足をクォーターファーマー(8時間のうち2時間を農作業にあて、それ以外を自由な時間として使う生活)という新しい生活スタイルの方法として推奨しており、カレッジ卒業生の中には2拠点生活を始め、耕作放棄地を借りて、米や野菜を作っている者もいる。
耕作放棄地を利用して生活したい人を増やし、日本全体をレジリエントにしたい。
カレッジ参加者の多くは自給や健康のためという方が多く、将来の食料危機や環境問題を考えている方も多い。
【生活協同組合 コープみえ】
体験のアンケートをみると、農業への理解が進んでいると感じている。
最近はSDGsの観点で地元野菜を食べるようにしたいという声も。米も三重県産を買いたいという声が多い。
【国立大学法人 三重大学】
短期的な効果はいろいろあるが、食育の効果は長期的な視点で考えるべき。
効果は、遅れてやってくるものもあるし、それなりに時間がかかる。
細々と長く続けていけるのは大学ならでは。
【三重県 農林水産部 フードイノベーション課】
水産の話になるが、海藻が減っている。海藻を食べる魚をみんなが食べることで藻場を守れることが分かれば、子どもたちの環境を守るという意識につながる。体験において地産地消も含めてこうした啓蒙もできたらいい。
【四日市市 商工農水部 農業センター】
大人の力を借りず、子どもだけでの加工収穫体験をすることが成長につながっていると感じる。
アンケートでは、ほぼ全員が野菜を作りたい、またやってみたいと回答し、食べ物に非常に興味を持ってくれたと感じる。
親子向け体験では、体験に関心を持つ親御さんもいる。
【玉城町 産業振興課】
体験に参加した親御さんは大変喜んでいる。
今年度は放課後の短時間の体験であったため、来年度は夏休みに少し時間をかけてやってみたい。
(5)農林水産省への要望
【JLLリテールマネジメント株式会社】
私は農家でもあるが、今後、少ない農業人口で安定的な食料確保を考えるとスマート農業となるが、私のような小さい農家では難しい。金銭面での国の支援があれば助かる。
【国立大学法人 三重大学】
農林水産省が食料安全保障をうたう中で、来年度が食育推進基本計画改定の節目ということなら、農林水産省には百年事業といった気合いで改定作業を進めてもらいたい。
懇談会の様子




お問合せ先
消費・安全部消費生活課
担当者:消費者対応班
代表:052-201-7271(内線2807)
ダイヤルイン:052-223-4651




