令和5年度の取組
令和5年度の取組を紹介します。
各大学との取組
     |
  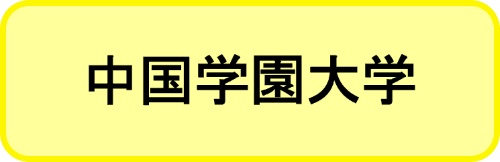  |
| 環太平洋大学(岡山県岡山市) |
| 令和5年10月4日 |
| 「食でつなげる人・未来!」~持続可能な社会を目指して~ |
|
食をテーマに、動物の体の特徴、みどりの食料システム戦略、共食、親子の絆の大切さといった幅広い話題を学生に提供。 学生の声:「食の大切さ、食で家族との絆が深まると感じた。」 |
| 令和5年10月11日 |
| なぜ今、有機農業なのか~有機農業・有機食品を知る~ |
|
有機農業についての説明と環境に優しく持続可能な生産~消費を実現するために農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」について説明。 学生の声:「身近なところにもオーガニック食品があることを知りました。」 |
| 令和5年10月18日 |
| ボランティア体験(有機農業) |
|
有機農業に取組まれている生産者のほ場等を訪れ、農作業体験を行った。 学生の声:「春菊をちょっと摘んで食べたら新鮮で甘い。」「有機農業の良さについてとても深く知れた。」 |
| 令和5年10月25日 |
| シンポジウム(キャリア教育としての人生観) |
|
有機農業に取組まれている農業者2名と消費・安全部長が、自身の経験談や人生観についてそれぞれの立場で発言。 学生の声:「普段聞けない農業という分野で働いている人の話を聞けてとても貴重な体験でした。」 |
| 令和5年11月8日 |
| 肥料・農薬の役割 |
|
農業生産における肥料や農薬の役割について講義。 学生の声:「今までデメリットの部分でしか見れていなかった農薬について生産者側のメリットの観点を知ることが出来た。」 |
| 令和5年11月15日 |
| ワークショップ(有機農業と生産資材の関係性を考える) |
|
有機農業と農薬・肥料を使用した農業のメリット・デメリットについて考えるグループ学習。 学生の声:「生産者と消費者の視点に加えて、地球の視点からも考えたいと思った。」 |
| 令和5年11月22日 |
| 農福連携 |
|
農福連携に取り組む事業者からの農業と福祉の連携について、自身の経験を踏まえ講義。 学生の声:「農福という言葉自体知らなかった。農業と福祉の連携は必要なことだと思った。」 |
| 令和5年11月29日 |
| ボランティア体験(農福連携) |
|
農福連携に取組まれている事業者のほ場等を訪れ、障がい者の方と共に農作業体験を行った。 学生の声:「農業の作業に限らず、働き方や生活の仕方等をサポートし合える環境づくりが大切だと考えた。農業の環境は福祉を行う上では開放的で良い環境だと感じた。」 |
| 令和5年12月6日 |
| 農福連携、フードロスについて考える |
|
障がい者の方との作業や生産段階での農産物廃棄を目の当たりにした体験をふまえ、「農福連携」、「フードロス」について考える講義。 学生の声:「農福連携で農業側のメリットデメリットを考えるのは簡単だったが、福祉側で考えるのは難しいと感じた。」 |
| 令和6年1月24日 |
| プレゼンテーション |
|
これまで実施してきた連携授業で学んだことを踏まえ、日本の農業が直面する課題に対して、自ら考えた課題解決についてプレゼンテーション。 学生の声:「有機農業や農福連携をする人が少しでもやりやすい環境になってほしい。」 |
| 岡山県立大学(岡山県総社市) |
| 令和5年8月22日 |
| 持続可能な食料システム戦略 |
|
日本の農業の課題から、持続可能な生産~消費を実現するために農林水産省が策定したみどりの食料システム戦略や有機農業について説明。 学生の声:「地産地消や有機食品購入は経済的なことが影響するため、難しい課題。価格が安くなれば購入する。」 |
| 令和5年12月6日 |
| 我が国の食料・農業の課題~有機農業と食中毒対策を例に~ |
|
日本の農業の現状を踏まえ、農林水産省が策定したみどりの食料システム戦略や有機農業について説明。 学生の声:「有機農業についてあまり知らなかったので、今回の講義でメリット・デメリットも含めて学ぶことができて良かった。」 |
| 香川短期大学(香川県宇多津町) |
| 令和5年4月10日 |
| 有機農業ワークショップ |
|
「日本の農業の状況と有機農業・有機農産物について」の講演が行われた後、グループ学習が行われました。 学生の声:「有機農産物への関心を高めるために、給食などに取り入れて子供の頃から触れることが大切だと思った。」 |
| くらしき作陽大学(岡山県倉敷市) |
| 令和5年11月10日 |
| 我が国の食料・農業の課題~有機農業と食中毒を例に~ |
|
日本の農業の現状を踏まえ、農林水産省が策定したみどりの食料システム戦略や有機農業について説明。 学生の声:「オーガニック食品について、買い物に行く時は有機JASマークに注目して買ってみたいと思った。」 |
| 中国学園大学(岡山県岡山市) |
| 令和5年11月25日 |
| シンポジウム(持続可能な食料システムの確立) |
|
「SDGsと有機農業」をテーマとし、基調講演とSDGsに関連するパネルディスカッションが実施された。 |
お問合せ先
消費・安全部消費生活課
担当者:消費経済係
ダイヤルイン:086-224-9428





















