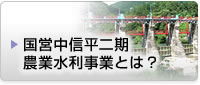さらに詳しく 安曇氏
安曇野(あずみの)を拓いたという安曇氏の起源は非常に古く、古事記には安曇族の祖先神は「綿津見命(わだつみのみこと)」とその子の「穂高見命(ほたかみのみこと)」であると書かれています。旧穂高町は安曇族の祖先神を地名としていることになります。
彼らの分布は、北九州、鳥取、大阪、京都、滋賀、愛知、岐阜、群馬、長野と広範囲にわたっており、「アツミ」や「アズミ」の地名を残しています。その北限が安曇野ということになります。
博多湾(はかたわん)の志賀島(しかのしま)には海神を祀った志賀海神社(しかうみじんじゃ)が現存し、全国の綿津見神社(わたつみじんじゃ)の総本宮となっており、安曇氏の発祥地とされています。神職は今も阿曇氏が受け継いでいます。
彼らはすぐれた航海術と稲作技術を持ち、古代の海人族の中でも最も有力な氏族でした。連(むらじ)という高い身分を大和朝廷から受け、中国や朝鮮にもたびたび渡っていたとも言われており、663年の白村江(はくすきのえ)の戦いでは、安曇比羅夫(あずみのひらふ)が大軍を率いて朝鮮にわたり、陣頭指揮にあたっています。
また、788年には宮中の食事を司る長官奉膳(ぶんぜ)の地位についていることからも、安曇氏は大和朝廷を支えた有力氏族であったことがうかがえます。
彼らがなぜこんな北の山国へ来て住み着いたのか、またどんなルートでたどり着いたのかよく分かっていませんが、おそらくは蝦夷(えぞ)の征伐が目的であり、ルートとしては、
- 北九州から日本海→姫川谷(青木湖から糸魚川に流れる川)から来たという北陸道説
- 北九州から瀬戸内海・大阪(安曇江)経由の東山道説
- 北九州から瀬戸内海→渥美半島(安曇族の開拓地)→天竜川を上った天竜川筋説
などがありますが、定かではありません。
安曇野へは4~5世紀に入ったという説もあります。その時代によりここを開拓した理由も異なってくるはずですが、今となっては謎のままです。しかし、安曇野という地名、あるいは穂高神社(ほたかじんじゃ)の存在だけでも大きな文化財を残したとも言えるでしょう。
お問合せ先
農村振興部水利整備課ダイヤルイン:048-740-9836