4.近代的水利システムへの道のり【「農」と歴史】
台地の開発
横堰(よこぜき)の完成などによって、松本平(まつもとだいら)、安曇野(あずみの)とも見事な沃野へと生まれ変わりました。(3.横堰による開発を参照)しかし、明治になっても、まだ粟やヒエを常食としなければならない村もありました。
山麓近くの高台にあった上波田(かみはた)、下波田(しもはた:現波田町)、竹田(現山形村)などです。それでも江戸時代は高い年貢に苦労をしてきました。
下波田地区では、村の惨状を嘆いた庄屋・波田腰六左が立ち上がり、梓川(あずさがわ)上流から水路を引く計画を立てます。下流の反対を押しのけ、資金や工事でも幾多の困難にあいながらも、明治4年に着手。同7年の完成を経て、同15年には200haの開田に成功するという快挙を成しとげています。
また、同様に水不足に悩んでいた上波田、竹田(現在の山形村)でも、江戸末期、中嶋貴右衛門ほか有志たちが、はるか遠く黒川谷から水を引く計画を立てて着工にいたりましたが、たいへんな難工事に資金を使い果たし、挫折しています。明治になって、その志を継いだ百瀬三郎平ほか7名が再び挑戦。言葉にはできないほどの苦労の末、遂に明治26年、通水に成功しました。最初の着工以来35年の歳月が流れていました。そして、同39年には85haの水田を拓いています。この用水はその後も、波田10時間、竹田15時間の番水(ローテーションによる配水)、水配人による水管理など、渇水時にも知恵を出し合い、少ない水を分け合って維持してきました。
左右両岸における用水の統合(県営梓川沿岸農業水利改良事業)
梓川には、両岸を含めて14ヶ所に堰が設けられていました。昔の堰は「牛枠(うしわく)」と呼ばれる土石と木で出来た構造物(イラスト参照)で川を塞き止めていただけでした。急流河川である梓川は、一雨降れば牛枠は流出、少し日照りが続くとたちまちのうちに川は細ります。
上流から順次取水するため下流の水不足は悲惨なものでした。水は農民の命。水をめぐる調整は、村の生死をめぐる調整と言っても過言ではありません。下流の村は、時に上流村に対し金品や酒をふるまいながら、夏中、交渉を続けたといいます。
特に江戸時代後半(文政・弘化年代)の水争いは激しく、江戸表での判決に及ぶこと数回、多数の犠牲者を出した記録が残っています。水利をめぐる権利は、上流・下流、右岸・左岸とも入り乱れて、江戸時代から複雑な確執を引きずっていました。
大正13年には、流血の惨事も起きています。この年の夏は大変な日照りが続き、梓川扇状地の水田約1,500haが収穫皆無に近かったといいます。その不満が爆発したのでしょう。手に鎌や棒を持ち両岸に対峙した農民達は、投石や殴り合いを繰り返し、ついに多数の警官の出動となりました。
しかし、この事件が契機となって、昭和6年、「県営梓川沿岸農業水利改良事業」によって赤松頭首工が完成。ようやく左岸八堰、右岸六堰の取水口が一本に統合され、両岸にまたがる地域約5,100haの水路が整備され、あわせて耕地整理が図られることとなりました。実に、平安時代から昭和まで約1,000年に及ぶこの地の宿命に、ようやく終止符がうたれることになったのです。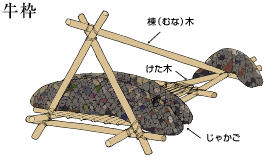

赤松頭首工の跡
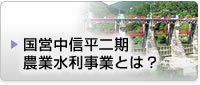




お問合せ先
農村振興部水利整備課ダイヤルイン:048-740-9836




