千曲川水系
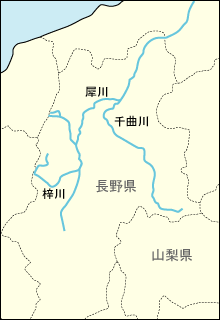
千曲川は信濃川の地域名称で、新潟県境から長野県に入ると「千曲川」と呼ばれます。流路
延長は約214km、流域面積は約7,100km2で信濃川の全流域面積約11,900km2の60%を占め
ています。
千曲川の水源は、西は標高3,000m級の山岳が連なる日本アルプスによって富山・岐阜県と
界し、東は2,000m以上の山脈により群馬・埼玉県等と流域を分けています。
流域はほとんどを山地部が占め、急峻な上流部は水力発電の好適地となっています。また、流
域内の平地部は農業が主産業のひとつであり、千曲川の水を利用した米作が大半を占めていま
す。長野県の特産として有名なりんごは善光寺平が中心で、他の特産品に中信平の南部、塩尻
市周辺のぶどう、穂高町のわさび等があります。
千曲川流域農業の変遷は大きく3つの時代に区分することができます。第1期は江戸から明治初頭までの水田開発の時代、第2期は明治後半から大正・昭和初頭までの養蚕盛時代、第3期は太平洋戦争中から戦後にかけての果樹園芸(りんご・梨・ぶどうなど)時代です。そして、それらのいずれもが千曲川水系との深いかかわり合いをもっていました。
ところで、昭和40年代に入って、稲作近代化のための農業構造改善や圃場整備政策が打ち出されると、千曲川や犀川流域の平地帯ではそれが最も大規模に、効率的に行われ、水田の大型化と乾田化が大きく推進され、長野平農業水利事業(昭和38~45)、中信平農業水利事業(昭和40~52)及び飯山開拓建設事業(昭和58~平成6)等の土地改良事業が実施されました。しかし、機械による協業化が普及し、余剰労力が生み出されたことによって、その余剰労力が工業生産へと動員され、各地に農村工場が出現するようになりました。農村部の生活は都市化され、豊かさがもたらされましたが、一方で専業農家の急減という問題が深刻になってきています。


梓川頭首工(中信平地区) 大規模な農地造成(飯山地区)
事務所概要
お問合せ先
西関東土地改良調査管理事務所
〒439-0031 静岡県菊川市加茂2280-1
代表:0537-35-3251












