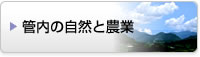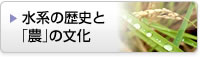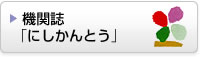富士川水系
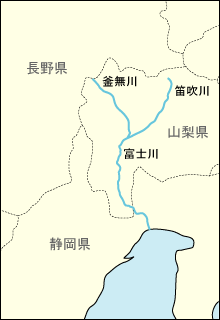 富士川水系はその源を山梨県北巨摩郡白州町と長野県諏訪郡富士見町境の鋸岳に発し、途
富士川水系はその源を山梨県北巨摩郡白州町と長野県諏訪郡富士見町境の鋸岳に発し、途
中多くの支流を合わせながら山間渓谷部を抜け、甲府盆地を南流し、盆地の南端、山梨県西
八代郡市川大門町において笛吹川と合流します。その後再び山間渓谷部に入り、静岡県富士
市と庵原郡蒲原町の境において駿河湾に注ぐ、幹川流路延長128km、流域面積3,990km2の
1級河川です。
その流域は長野県、山梨県及び静岡県の3県にまたがり、豊かな自然環境を有しています。
富士川と周囲の山々が醸し出す風情は、急流と清流が相まって、優れた景観美を造り、
その流れは県内外の人々に憩いと安らぎを与え、広く愛されています。
流域内の代表的な都市は、甲府盆地内の甲府市並びに河口部の富士市及び沼津市があり、
山梨県及び静岡県の中東部地区における社会、経済、文化の基盤をなしており、本水系の
治水、利水、環境についての意義が極めて大きい河川となっています。
富士川は、流域の約90%が急峻な山地で、3,000m級の山々に囲まれた日本を代表する急
流河川であり、河道は礫河原を呈しています。
富士川の水利用の歴史は古く、江戸時代から各所で取水堰が建設され、かんがい用水の確保が行われました。さらに、急峻な地形を利用して、明治後期から水力発電による水利用が盛んに行われるようになりました。
大正時代には、洪水被害のため、荒廃していた支流の笛吹川の廃河川跡で開墾事業が実現します。荒廃した河川跡に道路や水路を整備する工事は、大正15年から昭和8年まで行われました。
また、昭和のはじめには、同じく支流である釜無川で、江戸時代の開発以来、改修を繰り返しながら使用されていた徳島堰を近代的な頭首工へと改修し、用水幹線水路を整備する徳島堰用水幹線改良事業が行われました。


天科取水口(笛吹川地区) 徳島頭首工(釜無川地区)
富士川の利水は、農業用水及び発電用水が主で水道用水、工業用水は大半を地下水に依存しています。富士川の河川水は、農業用水として約38,000haに及ぶ耕地のかんがいに利用されるとともに、発電用水として69箇所の水力発電所で使用され、総最大出力約430,000kWの電力供給が行われています。

笛吹川
事務所概要
お問合せ先
西関東土地改良調査管理事務所
〒439-0031 静岡県菊川市加茂2280-1
代表:0537-35-3251