フォトレポート(高知県)平成29年度
|
高知県拠点が携わった農林水産施策(会議、イベント等)や農山漁村の風景などを紹介しています。
|
3月
|

田植え風景

植え付け田
|
南国市早期米植え付け
- 撮影場所:高知県南国市
- 撮影日:平成30年3月28日
早場米地帯の高知県南国市では、30年産米の田植えが始まっています。米農家の上野さんが、コシヒカリの苗を植え付けていました。
今年は3月になって気温の高い日が続いたため、例年より2日早い3月28日から田植えを開始したそうで、これから順次1.8ヘクタールの水田にコシヒカリを作付けし、順調に育てば7月27日頃には収穫できるそうです。
|
1月
|

施策説明を熱心に聞く生徒達

事例紹介を中心とした施策説明
|
高知県立農業大学校への施策説明
- 撮影場所:高知県いの町
- 撮影日:平成30年1月12日
高知県拠点では、将来の日本の農業を担う若者への施策説明を行っています。
平成30年1月12日、高知県立農業大学校の1年生・2年生(計48名)に中国四国農政局管内・高知県内の優良事例や施策活用事例の紹介を中心とした施策説明を行いました。
聴講者は卒業後、就農を希望又は予定している生徒も多数いることから、真剣な表情で説明を聞いていました。
|
12月
|

授与式:いしはらの里協議会1

授与式:いしはらの里協議会2

授与式:三原村農業公社1
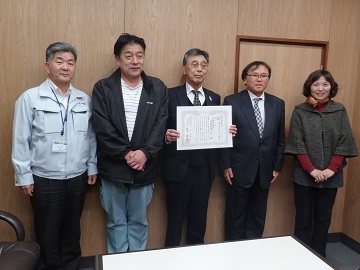
授与式:三原村農業公社2
|
中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証授与式の開催
- 撮影場所:高知県土佐町・三原村
- 撮影日:平成29年12月12日
平成29年12月12日中国四国農政局高知県拠点は、土佐町と三原村において、「中国四国農政局『ディスカバー農山漁村(むら)の宝』」選定証授与式を開催しました。
授与式では関係者が立会のもと、中国四国農政局塚元地方参事官から、いしはらの里協議会・筒井会長、三原村農業公社・藤本理事長へ、選定証が授与されました。
「いしはらの里協議会」は、地域住民自らが生活店舗・ガソリンスタンド、直販所「やまさとの市」を運営して地域の活性化に取り組んでいます。
「三原村農業公社」は、公社を中心としたゆず生産拡大や加工販売、新規就農者育成など三原村独自の農業システムの構築を目指した取り組みを実施しています。
【関連URL】
(プレスリリース)中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証授与式の開催について
|
11月
|
 食堂前では、のぼり等で被災地支援をPR 食堂前では、のぼり等で被災地支援をPR

食堂前の様子

福島県産コシヒカリを使った定食
|
食べて応援しよう! ~被災地産食品の利用・販売を推進~
- 撮影場所:高知県高知市
- 撮影日:平成29年11月21日
平成29年11月21日、高知県拠点は、高知地方合同庁舎食堂のご協力を頂き、「食べて応援しよう!(※)」に取り組みました。
この日の食堂で用意された昼食には、定食を始めすべてのメニューに「福島県産米」使用され、食事された方々は美味しいお米の味を堪能されていました。
農林水産省では、被災地産食品を積極的に消費することによって、産地の活力再生を通じた被災地の復興を応援するため、多様な関係者間で一体感を醸成できるよう、共通のキャッチフレーズ「食べて応援しよう!」の利用を呼びかけております。
【関連URL】
「食べて応援しよう!」(農林水産省HP)
|
10月
|

神事の様子

刈女らによる「抜穂」

稲を神前に奉納

残りの稲をみんなで収穫
|
新嘗祭献穀田抜穂式
- 撮影場所:高知県本山町
- 撮影日:平成29年10月5日
5月18日の「お田植え式」で植えられた苗は、献穀者の川村隆重さんの丁寧な管理により無事収穫期を迎え、10月5日に献穀田において「抜穂式」が行われました。
約70名の関係者が見守るなか神事が執り行われ、「抜穂」では6名の刈女(かりめ)と献穀者ら10名が、一人2束ずつ鎌で稲を刈り取り、神前に奉納しました。
この日刈り取った稲は、乾燥、脱穀の後に精米にして、一升(1.8リットル)を桐の箱に詰め10月26日に献納することにしています。
【関連URL】
(フォトレポート)豊作願いお田植式
|
9月
|

食味・目慣らし会の様子

食味用の梨

新高なし果樹園

収穫を待つ新高なし
|
平成29年産 新高なし食味・目慣らし会
- 撮影場所:高知県高知市
- 撮影日:平成29年9月25日
高知県の梨生産では106年の歴史がある、高知市「針木梨組合」で食味や品質を確認するため、「平成29年産新高なし食味会・目慣らし会」が、9月25日に開催されました。
「針木梨組合」の組合員数は32戸で、食味・目慣らし会には大きな新高なしが所狭しと出品されていました。
針木地区の新高なしは、「まるはり」のブランド名として知られており、大玉で甘みが強く高知県内外で親しまれています。
組合長の甲藤学さんによると、「今年は天候に恵まれ、平年並みの品質」とのことです。
今年の出荷時期は9月下旬から10月下旬、県内外で販売されるということです。
|
7月
|

早期米初出荷進発式

テープカット

新米の積み込み作業
|
平成29年産早期米進発式
- 撮影場所:高知県高知市
- 撮影日:平成29年7月27日
平成29年7月27日、全国農業協同組合連合会高知県本部で、平成29年産早期米の進発式が開催されました。
式典は、県・農業技術センター・JA・米卸業者・中国四国農政局高知県拠点など関係者約30名が出席し、早期米「南国そだち」の全国へ向けた出発を見送りました。
また、本年は、式に併せて「ナツヒカリ」に替わる新品種「高育76号」(名前募集中)の試食も行われ、来年の進発式が待ち遠しいと思える式となりました。
なお、平成29年7月27日農林水産省公表の早期栽培の作柄概況(7月15日現在)では、「やや良」又は「良」の見込みとなっています。
【関連URL】
平成29年産水稲の西南暖地における早期栽培等の作柄概況(7月15日現在)(農林水産省へリンク)
|
|

青々と育ったい草
 重機複数台での刈取り作業 重機複数台での刈取り作業
 い草用ハーベスター い草用ハーベスター
 刈取ったい草の積み下ろし 刈取ったい草の積み下ろし
|
い草の刈取り中
- 撮影場所:高知県土佐市
- 撮影日:平成29年7月14日
平成28年12月19日植え付けをご紹介した、土佐市の野村和仁さんの圃場にてい草の刈取りが始まりました。「今年は天候に恵まれ、草丈・くら張りも良好」とのことです。
暑い盛りなので、い草が蒸れないように朝4時30分頃から2時間ほど、い草用ハーベスター4台と積み込み用の重機を用いて刈取りし、その後は作業場へ場所を移して泥付け作業等を行います。
栽培面積2ヘクタールのうち、1日の刈取り面積は約0.15ヘクタールほどで、家族3世代とアルバイトも含めて総勢7名で作業を行い、2週間程度刈取り作業は続くそうです。
【関連URL】
(フォトレポート)い草の植え付け中
|
6月
|
 道路に面した販売所ときび(トウモロコシ)畑 道路に面した販売所ときび(トウモロコシ)畑
 販売所 販売所
 茹でたてのきび 茹でたてのきび
|
採れたて直販(きび街道)
- 撮影場所:高知県いの町
- 撮影日:平成29年6月9日
高知自動車道伊野ICを下りるとトウモロコシ畑を見ることができます。いの町枝川地区では、約30年前から地元農家数軒が採れたてのトウモロコシを畑周辺の道路端で茹でて販売しており、「きび街道」として県民に親しまれています。(高知県では昔からトウモロコシのことを「きび」と呼んでいます。)
お話しを伺った販売所での収穫・販売時期は6~7月で、早朝に収穫したトウモロコシはその日に売り切れ、土日は県内外の観光客でにぎわっています。
2月からビニールトンネルによる促成栽培を行い、6~7月の間、毎日販売できるよう畝ごとに時期をずらして栽培しています。販売所の農家は、「朝採れ、茹でたての甘いきびを県内外の皆さんに食べてもらいたい。」と作業されていました。
|
5月
|
 お田植え式神事 お田植え式神事
 田植え作業 田植え作業
 田植え作業 田植え作業
 献穀田看板 献穀田看板
|
豊作願いお田植式
- 撮影場所:高知県本山町
- 撮影日:平成29年5月18日
すがすがしい五月晴のもと、本年の新嘗祭に献上するお米の「お田植え式」が、5月18日に本山町の川村隆重さんの水田で行われました。
多くの関係者が見守るなか、地元の若一王子宮神社の宮司により厳かに神事が進められ、「田植えの儀」では、献穀者の川村さんと6名の早乙女が「にこまる」の苗を628平方メートルの献穀田に植え付けました。
この日植えられた稲は、10月中旬の「抜穂式」で収穫し、1升(1.8リットル)のお米が10月下旬に献納される予定です。
|
4月
|

ほ場で育つイタドリ

収穫作業
 加工品 加工品
 イタドリの炒め物 イタドリの炒め物
|
イタドリの収穫作業
- 撮影場所:高知県高知市
- 撮影日:平成29年4月20日
イタドリの収穫の季節になりました。
イタドリは「スカンポ」「イタンポ」「ダンジ」など、全国各地で様々な呼び方をされる野草ですが、高知県では良く食べられる山菜として親しまれ、栽培も行われています。
高知市鏡地区のほ場では、4月に肥培管理されたイタドリの収穫作業が行われます。
自生するイタドリは皮が硬く剥きにくいため、長年かけて皮が柔らかい株を選別栽培しています。
イタドリ特有の苦味の影響か、イノシシ等の鳥獣被害もないとのことです。
一度に全てのイタドリを収穫すると株が弱るため、毎日ほ場に出向き、太く育ったイタドリのみ収穫します。
収穫は手作業ですが、機械や力をあまり使わないため、高齢者でも楽しく栽培できるとのことです。
栽培農家さんは、「ポンッ」と気持ちの良い音を立てながら次々と手作業で収穫されていました。
収穫後のイタドリは皮を剥きあく抜きをした後、様々な調理法や味付けで食卓を彩ります。
直販所などの販売店では、生鮮のままやあく抜き後の加工品が販売され、旬の食材として人気があります。
また、家庭でもあく抜きしたものを冷凍保存すれば、年間通じて食べることもできます。
|
お問合せ先
高知県拠点
電話:088-875-7236












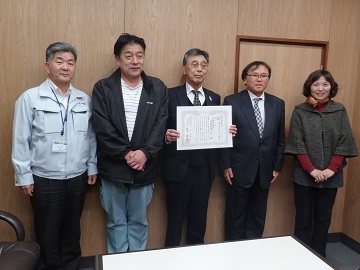
 食堂前では、のぼり等で被災地支援をPR
食堂前では、のぼり等で被災地支援をPR













 重機複数台での刈取り作業
重機複数台での刈取り作業 い草用ハーベスター
い草用ハーベスター 刈取ったい草の積み下ろし
刈取ったい草の積み下ろし 道路に面した販売所ときび(トウモロコシ)畑
道路に面した販売所ときび(トウモロコシ)畑 販売所
販売所 茹でたてのきび
茹でたてのきび お田植え式神事
お田植え式神事 田植え作業
田植え作業 田植え作業
田植え作業 献穀田看板
献穀田看板

 加工品
加工品 イタドリの炒め物
イタドリの炒め物