中国四国消費生活・食育ネットワークメールマガジン第42号
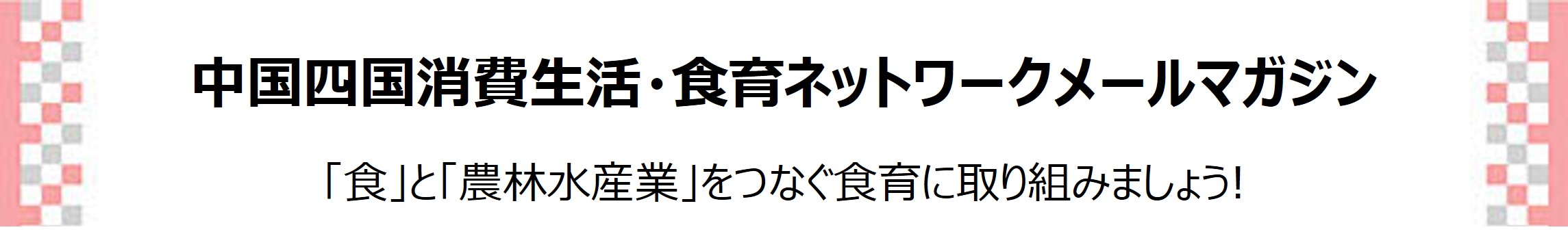
★もくじ (^_^)v
1 注目情報
◆ 鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及について
令和6年10月17日に北海道の家きん農場において、今シーズン初めてとなる高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました。
さらに、10月23日には、千葉県の家きん農場で今シーズン国内2例目の高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました。
政府としては、鶏肉・鶏卵は「安全」であり、我が国の現状において、家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザに感染する可能性はないと考えています。
(食品安全委員会ホームページ)
https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html
なお、鳥インフルエンザに感染した鶏肉・鶏卵は市場に出回ることはありません。
(食品安全委員会ホームページ)
https://www.fsc.go.jp/osirase/tori/tori_iinkai_kangaekata.pdf
一方、鳥インフルエンザウイルスは、通常、ヒトに感染することはありませんが、感染したトリに触れる等濃厚接触をした場合など、きわめて稀に鳥インフルエンザウイルスがヒトに感染することがあります。
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/qa.html
令和6年度秋以降の鳥インフルエンザに関する情報は、農林水産省ホームページに掲載しています。
(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/r6_hpai_kokunai.html
◆ 有毒な野生キノコによる食中毒に注意してください!
毎年、夏の終わりから秋にかけての時期を中心に、有毒な野生きのこによる食中毒が発生しています。
今月、中国四国地域でもヒラタケやシイタケ、ムキタケなどと間違えやすいツキヨタケによる食中毒が発生しました。
食用きのこと間違えられやすい毒きのこは、見た目が似ているだけでなく、食用きのこと同じ場所に生えていることがあり、見分けることが困難な場合があります。
食用であると確実に判断できない野生きのこは、採らない、食べない、売らない、人にあげないようにしましょう!
参考資料:毒きのこによる食中毒に気をつけて!/中国四国地域に自生する毒きのこ
本当に安全?STOP毒キノコ
<詳しくは、こちらをご覧ください>
(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/rinsanbutsu/yaseikinoko/yaseikinoko.html
(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201609/2.html
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kinoko/
◆ 11月3~7日は「いいさかなの日」!
その食べ物が「食べ物」になる前、材料たちがどのような姿であったか想像したことはありますか?
四国水族館では、11月3日(日曜日)~30日(土曜日)の間、「いいさかなの日」にちなみ、魚を使った四国の郷土料理や名産品を、関連生体水槽前にパネルを設置し、ご紹介します。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(水産庁ホームページ)
https://sakananohi.jp/news/news_2024101501.html
◆ 第20回食育推進全国大会 in TOKUSHIMAへのブース出展を募集しています!
毎年6月の「食育月間」に関連する取組の一層の充実を図るため、令和7年度の全国的な取組として、第20回食育推進全国大会が徳島県において開催されます。
現在、食育推進に係る「展示・PRブース」や、県産品、郷土料理、加工品等の「飲食・販売ブース」への出展者を募集しています!
<申込み方法等、詳しくはこちらをご覧ください>(徳島県ホームページ)
https://syokuiku-tokushima.jp
2 中国四国農政局からのお知らせ
◆ 消費者の部屋展示のご案内
〇「食と農のつながりの深化に着目した国民運動『食から日本を考える。ニッポンフードシフト』」
日本の食の未来を守るために、消費者と生産者や食品事業者が一体となって自分たちの課題と捉え、国産の農林水産物を積極的に選択するといった行動変容につなげていくため、「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」をスローガンとする国民運動を展開しています。
中国四国農政局では、令和6年10月21日(月曜日)~11月1日(金曜日)の間、岡山第2合同庁舎1階の消費者の部屋展示コーナーにおいて「食と農のつながりの深化に着目した国民運動『食から日本を考える。ニッポンフードシフト』」の展示を行っています。
今回は、「ニッポンフードシフト」の取組内容を分かりやすく紹介しています。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(中国四国農政局ホームページ)
https://www.maff.go.jp/chushi/press/seikatsu/241007.html
〇「地域の農林水産物・食品を海外へ!地理的表示(GI)保護制度ってなーに?」
地理的表示(GI)保護制度については、その地域ならではの自然的・人文的・社会的な要因の中で育まれてきた品質・社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護するものです。
中国四国農政局では、令和6年11月5日(火曜日)~15日(金曜日)の間、岡山第2合同庁舎1階の消費者の部屋展示コーナーにおいて、「地域の農林水産物・食品を海外へ!地理的表示(GI)保護制度ってなーに?」の展示を行います。
今回は、中国四国地域の主な農林水産物・食品の輸出促進に係る取組及び地理的表示(GI)についてご紹介します。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(中国四国農政局ホームページ)
https://www.maff.go.jp/chushi/press/seikatsu/241021.html
〇移動消費者の部屋in高知の御案内「もったいない!食品ロスを減らそう」
「食品ロス」を削減するため、農林水産省では関係省庁と連携して、食品小売事業者における納品期限の緩和や「てまえどり」の促進など、食品事業者、消費者双方の取組を推進しています。
中国四国農政局では、令和6年10月24日(木曜日)~11月6日(水曜日)の間、オーテピア高知図書館(高知県高知市)において、「もったいない!食品ロスを減らそう」の展示を行っています。
今回は、食品ロスの現状や削減に向けた様々な取組などについて紹介します。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(中国四国農政局ホームページ)
https://www.maff.go.jp/chushi/press/seikatsu/241010.html
◆ 皆様が開催される研修会などに講師を派遣します!
日々の暮らしの中で、「この食品は安全?」、「将来、食料や農業は大丈夫?」、「災害時に備えた家庭での食品備蓄はどうしたらいいの?」といった疑問を持たれることはありませんか。
そんな疑問にお答えするため、中国四国農政局では、消費者団体等の皆さまのご希望の日時・場所に、職員を無料で派遣する「食と農の知っ得講座」を実施しています。
「食品の安全とリスク」の講座では、食品の安全やリスクについての基本的な事項と、食中毒にならないために買い物から調理、食事の後片づけまでの行程で私たちがすぐにでもできる食中毒予防方法を紹介しますので、是非ご利用ください。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(中国四国農政局ホームページ)
https://www.maff.go.jp/chushi/heya/kouza.html
3 農林水産省からの情報
◆ 近畿農政局食育イベント「~農業体験を通じて食とその未来を考えよう!~」の開催について
本イベントでは、民間事業者の食育実践事例の紹介や実践者と参加者(オンライン参加も含める)との交流会を実施することで、子育て世代や若い世代による農業体験の機会が増加することを目的として開催します。
【開催日時】令和6年11月16日(土曜日)14時00分~16時00分
【開催場所】京都リサーチパーク1号館G会議室(京都市下京区中堂寺南町134)
【内容】
●講演
テーマ1 「つながりを育む農園~“おもしろおかしく”の具現化~」
講師:冨嶋真二 氏(株式会社堀場製作所管理本部総務部副部長)
テーマ2 「ヒト/コト/モノをつなぐ“かなこ農法”」
講師:小林加奈子 氏(株式会社小林ふぁーむ代表取締役)
●農業体験現場実況
場所:みつばちBunBunクロスケの大原野げんき畑(京都市西京区大原野南春日町1734-1)
内容:いちご栽培の農作業体験、食育の取組事例紹介
講師:田中クロスケ 氏(みつばちBunBunクロスケの大原野げんき畑代表)
体験者:同志社女子大学生活科学部学生、京都栄養医療専門学校学生
●パネルデイスカッション
テーマ:「これからの世代にたくさん農業体験を!」
パネラー:冨嶋真二 氏(株式会社堀場製作所管理本部総務部副部長)
小林加奈子 氏(株式会社小林ふぁーむ代表取締役)
石伏穣 氏(京都栄養医療専門学校講師)
田中クロスケ 氏(みつばちBunBunクロスケ大原野げんき畑代表)
ファシリテーター:大山憲二 氏(神戸大学農学部研究科附属食資源教育研究センター教授)
【募集人数】会場50名、オンライン200回線(YouTube)※(どちらも先着順)
【申込締切】令和6年11月13日(水曜日)
参加申し込みフォームはコチラ
https://www.secure-cloud.jp/sf/1727848123haUuYewE(外部リンク)
<詳しくは、こちらをご覧ください>(近畿農政局ホームページ)
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/241010.html
◆ 食品に関するリスクコミュニケーション「食品中の放射性物質~今と未来への歩み~」の開催について
農林水産省は、消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労働省及び経済産業省と連携して、「食品中の放射性物質~今と未来への歩み~」と題した意見交換会を開催します。
この会では、参加者の皆様と食品中の放射性物質に関する科学的な情報を共有し、生産者や事業者を含むパネリストと共に意見交換を行います。
【開催日時及び会場】
(1) 東京会場
日時:令和6年11月18日(月曜日) 13時00分~16時30分まで
会場:アットビジネスセンター 東京駅八重洲通り
(東京都中央区八丁堀1-9-8 八重洲通ハタビル 5階)
(2) 大阪会場
日時:令和6年11月25日(月曜日) 13時00分~16時30分まで
会場:新大阪ブリックビル貸会議室
(大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル3階)
【内容】
●基調講演
「放射性物質についての基礎知識」
講師:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 放射線医学研究所 熊谷敦史氏
●行政による情報提供
農林水産省消費・安全局、水産庁、消費者庁、厚生労働省健康・生活衛生局、資源エネルギー庁
●意見交換(パネルデイスカッション)
コーディネーター:フリーアナウンサー 竹山マユミ氏
パネリスト:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 放射線医学研究所 熊谷敦史氏
株式会社二本松農園 代表取締役 齊藤登氏
株式会社おのざき 取締役 小野崎雄一氏
一般社団法人消費科学センター 理事 井岡智子氏(東京会場のみ)
大阪よどがわ市民生活協同組合 副理事長 内山智美氏(大阪会場のみ)
【募集人数】定員各300名(会場100名、オンライン(Zoom)200名)
※申込多数の場合は、抽選とさせていただく場合があります。
【申込方法】
参加される方は、インターネット又は電子メールのいずれかの方法でお申し込みください。
(1)インターネット 東京会場:https://riscom2024.caa.go.jp/form/tokyo/(外部リンク)
大阪会場:https://riscom2024.caa.go.jp/form/osaka/(外部リンク)
(2)電子メール 以下「参加申込書」の参加者記入欄の項目を明記の上、下記の申込先にお送りください。
東京会場参加申込書/大阪会場参加申込書
申込先:contact@riscom2024.caa.go.jp
【申込締切】東京会場:令和6年11月11日(月曜日)必着
大阪会場:令和6年11月18日(月曜日)必着
<参加にあたっての留意事項等詳しくは、こちらをご覧ください>(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/seisaku/241017.html
◆ 令和6年度 米の流通状況等について
農林水産省は、これまで公表した令和6年度の米の流通状況等に関するデータ等について、流通段階別に整理したページを作成しています。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/r6_kome_ryutu.html
4 消費者庁からの情報
◆ 「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン(案)」に関する意見募集について
消費者庁は、外食時の食べ残し持ち帰りの推進を図る目的で、食べ残しの持ち帰りの活動に伴って生ずる法的責任について、消費者の自己責任であることを前提としつつ、民事上のトラブルを回避するために留意すべき事項を含め、食べ残し持ち帰り促進ガイドライン(案)を作成しました。
つきましては、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
【意見募集期間】
令和6年10月16日(水曜日)~11月15日(金曜日)まで(郵送の場合は同日必着)
<意見の提出方法等、詳しくはこちらをご覧ください>(消費者庁ホームページ)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/039718/
5 中国四国地域で行われる食育の取組(11月の予定)
◆ 五感で楽しむ秋 食の祭典 MARUI FOOD FESTA 2024 開催!(岡山県津山市)
岡山県の食に携わる生産者や食品関連事業者、地元の様々な団体など、100を超える食や健康に関する体験ブースがグリーンヒルズ津山に大集合!
各ブースでは、新しい食の提案や試食販売、ワークショップや体験イベント、料理教室、ゲーム、パフォーマンス、ステージイベントなど、様々な企画が実施されます。
日時:11月2日(土曜日)、3日(日曜日)10:00~16:00 雨天決行
場所:グリーンヒルズ津山(岡山県津山市大田920)
<詳しくは、こちらをご覧ください。>(株式会社マルイホームページ)
https://www.maruilife.co.jp/information/detail/212/2
◆ 「宇多津秋の大収穫祭」に参加(香川県宇多津町)
日々の生活実践に生かせることを目的とし、栄養相談、骨密度測定、脈波計測定を行います。
内容:栄養相談、骨密度測定、脈波計測定
日時:令和6年11月2日(土曜日)、3日(日曜日)
場所:JR宇多津駅前南口広場(香川県綾歌郡宇多津町五番丁)
主催:宇多津町
協力:(公社)香川県栄養士会
【問合せ先】 (公社)香川県栄養士会(電話 087-811-2858)
◆ 「香川ヤクルト健康フェア」に参加(香川県高松市)
内容:基調講演、栄養相談
日時:令和6年11月4日(月曜日)
場所:丸亀市綾歌総合文化会館アイレックス(香川県丸亀市綾歌町栗熊西1680)
主催:香川ヤクルト株式会社
協力:(公社)香川県栄養士会
【問合せ先】 (公社)香川県栄養士会(電話 087-811-2858)
◆ 「幼児における食育実践研究講座」を開催(香川県三木町)
幼児の食育を通じた健康づくりを目的に、エプロンシアターや講話「気になる子供の食習慣・好き嫌い」、お箸の持ち方、野菜クイズを行います。
内容:エプロンシアター、講話、お箸の持ち方、野菜クイズ
日時:令和6年11月6日(水曜日)10時00分~11時40分
場所:三木町立白山幼稚園(香川県木田郡三木町井戸2206-1)
主催:(公社)香川県栄養士会
【問合せ先】 (公社)香川県栄養士会(電話 087-811-2858)
◆ 「瓦町健康ステーション」に参加(香川県高松市)
健康や介護予防等に関する知識を習得し、日々の生活実践に生かせることを目的とした講座を開催します。
(1)内容:講話「高齢者の生活習慣病予防・改善のための食事」
日時:令和6年11月9日(土曜日)13時30分~15時30分
(2)内容:講話「運動の効果を高める栄養と口腔」
日時:令和6年11月26日(火曜日)10時00分~12時00分、13時30分~15時00分
場所:瓦町健康ステーション大会議室(瓦町FLAG 8階)
主催:高松市長寿社会福祉課
協力:(公社)香川県栄養士会
【問合せ先】 (公社)香川県栄養士会(電話 087-811-2858)
◆ 「子育て相談」を実施(香川県高松市)
さぬきこどもの国において、子どもたちの心と身体の健やかな育ちをサポートするため、子育て全般・子どもの食事等についての相談を受け付けます。
(1)内容:離乳食実演、子育て全般、こどもの食事等についての相談、料理講習会
日時:令和6年11月13日(水曜日)10時30分~10時00分
(2)内容:子育て全般・子どもの食事等についての相談
日時:令和6年11月14日(木曜日)、28日(木曜日)10時30分~15時00分
場所:さぬきこどもの国(香川県高松市香南町由佐3209)
主催:さぬきこどもの国
協力:(公社)香川県栄養士会
【問合せ先】さぬきこどもの国(電話 087-879-0500)
(公社)香川県栄養士会(電話 087-811-2858)
6 郷土料理のご紹介
◆ さばの姿ずし(高知県)
県内全域の食習慣として根づき、冠婚葬祭や神事に欠かせない「皿鉢(さわち・さはち)料理」。「皿鉢料理」は、土佐弁で宴会のことを指す「おきゃく」の際に振る舞われ、36cm~39cm位の大皿にごちそうが盛り付けられます。
その「皿鉢料理」の定番といえるのが、「さばの姿ずし」です。新鮮なサバを背開きにして酢でしめられており、なかには酢飯が、ぎっしり詰められています。すしを中心に据えて、切り取った頭と尾の部分を豪快に盛り付けるのを正調としています。
また、サバを使用したすしとしては「さばの押しずし」も、もてなしの席に並びます。高知県では魚を姿のまま調理する料理が多いのも特徴です。
京都府の「さばずし」も全国的に有名ですが、甘めな味付けの京都府に対して、高知県では酢と塩をきかせています。この味付けの違いは、使っているサバの種類が関係しています。京都府で使われるマサバは脂が多く、高知県でよくとれるゴマサバはマサバほど、こってりしていません。この差が味付けにも現れています。
「皿鉢料理」を出すほどでもないこぢんまりした会には、甘ダイやアジ、カマスなどの姿ずしが出されました。「ひめいち(ホウライヒメジ)の姿ずし」は、日常食。食堂などで稲荷ずしとともに総菜としてよく売られていました。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/sabanosugatazushi_kochi.html
【編集後記】
♪そこに行けば どんなに美味か 分かるというよ♪
最近、日増しに秋を感じるようになり、スーパーの食品売り場も彩りにあふれています。
それに伴い、夏は小食だった娘の食欲が旺盛になってきました。
お米が美味しいのか、特に「白米✕生たまご」にハマっています。こんな美味いごはんある?って感じ。
「美味しいから仕方ないよね」と、娘の健康を祈りながらご飯を炊く毎日です。
「TKG=たまごかけごはん」・・・というゴールデンなメニューがあるらしい。 in 岡山県美咲町
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆このメールマガジンは、登録していただいた方々に配信しています。
配信の変更などはこちらからどうぞ。
https://www.maff.go.jp/chushi/mailm/index.html
◆また、中国四国農政局ホームページにも掲載しておりますので、ご確認ください。
https://www.maff.go.jp/chushi/mailm/syokuiku/backno/index2.html
◆本メールマガジンでは、中国四国食育ネットワーク会員からの情報(食育イベントや体験講座など)についてもご紹介させていただきます。
皆様からの積極的な情報提供をお待ちしています!
◆本メールマガジンへのご意見・ご要望、または転載を希望される場合は、メールでお知らせください。
寄せられたご意見などは、個人情報を伏せた上でご紹介させていただくこともございますのであらかじめご了承ください。
◆お問い合わせ窓口
https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161125.html
◆ホームページURL
https://www.maff.go.jp/chushi/
◆編 集
〒700-8532 岡山市北区下石井1-4-1
中国四国農政局 消費・安全部 消費生活課
TEL:086-224-9428
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
<( _ _ )> 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 <( _ _ )>
お問合せ先
消費・安全部 消費生活課
担当者:食育推進班
ダイヤルイン:086-224-9428




