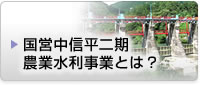さらに詳しく 安曇野りんごの歴史
幕末の文久2年(1862)、越前(えちぜん)藩主の松平慶永(春嶽)が幕府政事総裁の頃、アメリカからりんごの苗を輸入し、江戸の別邸に植えさせ、その後、津軽(つがる)地方の栽培適性を見抜き津軽藩に苗木を贈呈したと言われています。
また、明治4年、北海道開拓使次官であった黒田清隆(くろだきよたか)がアメリカから苗木75品種を持って帰国し、東京の官園で苗木を植え、翌年から北海道に送付したとも伝えられています。
明治7年、内務省勧業寮から長野県、筑摩(ちくま)県に3本ずつりんごの苗木が配布されました。長野盆地では「善光寺(ぜんこうじ)の参詣者」を相手にりんごが売られるようになりました。昭和初期に農家を支えていた養蚕業が不況となり、養蚕からりんご栽培への転換が急激に進みます。しかし、この頃、長野産の品種は「倭錦(やまとにしき)」と呼ばれ、市場では不評でした。先進地である青森の品種を導入し、昭和10年頃には、「紅玉(こうぎょく)」「国光(こっこう)」が栽培され、三郷村小倉を中心に三郷村や梓川村の山麓地帯にりんごが普及します。
戦争が始まると、米や麦などの増産が政府の方針となり、「果樹園転作令」が出されるなど一時停滞します。しかし、終戦後、それまでの化学工場は化学肥料工場として復興し、そこで生まれた新しい農薬がりんごの害虫駆除を容易にするなど、りんご農家の生産意欲を高め、やがて高度経済成長とともに果物が高値で取引されるようになりました。
昭和30年には、共同防除組合が設立。同39年にはスピードスプレーヤー(農薬噴霧車)なども導入され、産地間競争が激化する中で適地適産の選択的拡大が叫ばれますが、農薬散布に必要な水利施設がないことから、安曇野(あずみの)のりんご生産は頭打ち状態となります。
同46年、中信平土地改良事業により左岸幹線水路が完成。かんがい施設が整備されることにより、りんごの栽培熱は一挙に高まります。それまで、りんごの木は5mを超えるような大木でしたが、梓川村小室の果樹研究会が「わい化試験圃場」を設置し、2.5m程度の低木化を図ります。昭和50年頃には、安曇野のりんご園はすべて「わい化栽培」となります。そして、同59年、安曇野のりんごは日本農業賞天皇杯という最高の栄誉を獲得し、以来、量、質とも全国有数のりんご産地へと発展しました。
お問合せ先
農村振興部水利整備課ダイヤルイン:048-740-9836