2.国営中信平土地改良事業【事業に至る経緯】
国営梓川農業水利改良事業の実施
昭和6年、県営事業で造成された赤松頭首工では、洪水による河床低下や砂礫の堆積が著しく、取水、分水に支障をきたしていました。昭和18年、梓川(あずさがわ)両岸にまたがる5,228haを受益地とする「国営梓川農業水利改良事業」が着工され、赤松頭首工の上流2.5km地点に梓川頭首工が新設、同25年に完成しています。
しかしながら、梓川の水量の変動が大きいことに加え、小河川に頼る地区は相変わらず水源の水量に乏しく、また、畑作地帯における常習的な干ばつが問題となっていました。
国営中信平土地改良事業の完了
同じ頃、東京電力では梓川の電力開発を検討しており、同36年、発電と農業用水の調整が整い、土地改良事業の必要用水が確保されました。
そして、昭和40年、梓川右岸(松本市、塩尻市、波田町、山形村、朝日村)と左岸の旧梓川村(現松本市)、旧豊科町、旧穂高町、旧三郷町、旧堀金村(いずれも現安曇野市)にまたがる10,691haの水田、畑を受益地とする「国営中信平土地改良事業」が着工されます。
しかし、同45年には米の生産過剰による開田抑制政策が打ち出され、開田計画はすべて畑地かんがい計画に変更されました。
梓川上流に発電をともなった奈川渡(ながわど)ダム、水殿(みどの)ダム、稲核(いねこき)ダムが建設され、稲核ダムから新たに農業用水3.879m
| さらに詳しく |
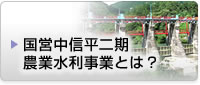




お問合せ先
農村振興部水利整備課ダイヤルイン:048-740-9836




