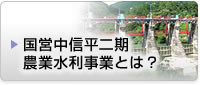4.安曇野農業水利事業【事業に至る経緯】
地域の変貌は農業ばかりではなく、特に高速道などの整備は工業や商業においても飛躍的な発展を見せました。昔農地であったところにも工場や住宅が立ち並び、広域農道沿いは商業エリアとしての開発も進みます。要するに、これまでの土地利用が、ここ4、50年の間にすっかり変わってしまいました。その大きな変化は、以下のように整理できます。
- 水田から高生産性畑地利用への転換
- 大規模な工業、商業団地の進出や住宅団地など、農地転用にともなう農地の減少
- 道路網の整備と舗装化の進展
- 林業の衰退にともなう山林の荒廃
こうした結果、当然のことながら、水の排水形態も大きく変わってしまいました。
また、とりわけ山林の荒廃は降雨の流出を早めてきています。間伐がおろそかとなり、枝木の密生によって光が地表に届かず、下草の成長が鈍くなる。その結果、山林の持っている肥沃かつ保水能力の高いスポンジ状の地表が形成されにくくなります。さらに、水田の大きな特徴である洪水防止機能、つまり大雨でも降雨を水田に貯めておける貯留機能が水田の減少とともに低下してきています。このために降雨の流出形態も変化し、水の流出率が徐々に高くなってきました。要するに、雨が降ると、これまでよりも早く、しかも、多く流出してしまうようになったわけです。
もともと大きな排水路がないこの地域は、大雨のたびに用水路から水が溢れ、被害をもたらしてきました。特に全国的にも珍しいケースですが、一級河川である黒沢川(くろさわがわ)の流末が用水路に流入していることも、被害を広域的なものにしています。とりわけ昭和58年の台風10号の被害、平成11年の梅雨前線の被害など記憶されている方も多いでしょう。
このため、安曇野(あずみの)地区では平成7年より、地域の排水対策として、国営安曇野農業水利事業及び県営かんがい排水事業が実施されました(国営事業は平成17年度に完了)。
水路から溢れた水(平成11年6月)
お問合せ先
農村振興部水利整備課ダイヤルイン:048-740-9836