宮城フォトレポート(令和5年度)
令和5年度
| [ 5年4月分 ] | [ 5年5月分 ] | [ 5年6月分 ] | [ 5年7月分 ] | [ 5年8月分 ] | [ 5年9月分 ] | |
| [ 5年10月分 ] | [ 5年11月分 ] | [ 5年12月分 ] | [ 6年1月分 ] | [ 6年2月分 ] | [ 6年3月分 ] |
新着情報
- 令和5年度JA古川子実とうもろこし検討会が開催されました(令和6年3月6日)
- 県内2JAの女性役員と意見交換を行いました(令和6年2月26日、29日)
- 大和町の新町長と意見交換を行いました(令和6年2月8日)
- 県内2JAの女性役員と意見交換を行いました(令和6年1月29日、31日)
- 県内各団体へ農林水産関係予算を説明し農政に関する意見交換を行いました(令和6年1月22日~30日)
令和5年度JA古川子実とうもろこし検討会が開催されました(令和6年3月6日)
令和5年度JA古川子実とうもろこし検討会(JA古川主催)が開催され約80名が参加しました。
JA古川では耕畜連携と国産飼料の生産拡大を目指し、令和4年度から全農と連携し、子実とうもろこしの大規模実証栽培に取り組んでいます。令和5年度の作付面積は約108ヘクタール(対前年17ヘクタール増)となり、獣害被害があった圃場を除く10a当たりの収量は、平均で675キログラムとなり、昨年に比べ2倍以上増加したことや、子実とうもろこしの後作大豆において、収量が増加したことなどが報告されました。また、JAからは、子実とうもろこしを飼料用だけでなく、穀物としても供給していきたいとの話がありました。
 |
 |
 |
| 子実とうもろこし検討会の様子 (JA古川本店) |
子実とうもろこしを活用した水田農業 の実践について講演する農研機構東北 農業研究センター篠遠研究員 |
令和5年度の実証結果について報告する 全農耕種総合対策部つくば営農企画室 村岡室長 |
県内2JAの女性役員と意見交換を行いました(令和6年2月26日、29日)
2月26日にJA仙台、2月29日にJA名取岩沼を訪問し、女性役員と意見交換を行いました。
役員の皆様からは、家族の理解と後押しで役員となり活動が続けられていること、また、地域の食育活動の状況や農家の後継者問題などの意見をいただきました。
 |
 |
|
| JA仙台の女性役員 | JA名取岩沼の女性役員 |
大和町の新町長と意見交換を行いました(令和6年2月8日)
大和町役場を訪問し、昨年10月に就任された浅野俊彦町長へ、食料・農業・農村基本法の見直しなど農業施策等の情報提供を行うとともに、大和町の環境保全米への取組、鳥獣被害や耕作放棄地の課題等について、幅広く意見交換を行いました。
 |
 |
|
| 浅野町長(左)と山田地方参事官(右) | 意見交換の様子 |
県内2JAの女性役員と意見交換を行いました。(令和6年1月29日、31日)
1月29日にJAみやぎ登米、1月31日にJA新みやぎを訪問し、女性役員と意見交換を行いました。
役員の皆様からは、女性の役員登用には家族の理解や協力が必要であることや、農家の高齢化、担い手不足が深刻であるなどの意見をいただきました。
 |
 |
|
| JAみやぎ登米の役員の皆さん | JA新みやぎの役員の皆さん |
県内各団体へ農林水産関係予算を説明し農政に関する意見交換を行いました(令和6年1月22日~30日)
宮城県の農業特性や事業の活用実績等を踏まえ、農業者、地方公共団体、JA等が支援対象となる農林水産関係予算の主要な事業を中心に、県内の各団体へ事業概要を説明するとともに、農政に関する意見交換を行いました。
各団体からは、水田活用の直接支払交付金の見直しに対する意見、みどりの食料システム戦略の取組や地域計画の策定状況の情報、食料・農業・農村基本法の見直しに期待する旨の発言などがありました。
 |
 |
 |
| 宮城県農政部との意見交換の様子 | JA宮城中央会との意見交換の様子 | JA全農みやぎとの意見交換の様子 |
 |
 |
 |
| みやぎ農業振興公社との意見交換の様子 | 宮城県農業会議との意見交換の様子 | 水土里ネットみやぎとの意見交換の様子 |
令和5年度涌谷町産子実用とうもろこしの成績検討会が開催されました。(令和6年1月19日)
涌谷地域農業再生協議会主催の「令和5年度子実用とうもろこし生産拡大に向けた成績検討会」が涌谷町役場で開催され約70名が参加しました。涌谷町は、耕畜連携と国産飼料の生産拡大を目指し、令和4年度から水田で子実用とうもろこしの実証栽培に取り組んでいます。令和5年度の作付面積は約51ヘクタール(対前年12ヘクタール増)となり、平均反収は496キログラムで前年の2倍以上となりました。暗渠排水が整備済みの圃場では反収900キログラムとなったところもありましたが、作付圃場のうち6割は暗渠排水が未整備であり、湿害対策が課題となっています。
 |
 |
|
| 農研機構東北農業研究センター、宮城県畜産試験場等からの説明に聞き入る参加者 | 涌谷町産の子実用とうもろこしを給餌した豚肉「みちのくの心意気」が涌谷町内の学校給食で提供され、食育にも一役かっています |
みやぎ生協の理事長と基本法やみどり戦略について意見を交わしました(令和6年1月18日)
みやぎ生活協同組合を訪問し、冬木理事長と食料・農業・農村基本法の見直しやみどりの食料システム戦略の推進などについて意見交換を行いました。
基本法の見直しは、国民一人一人の食料確保であったり、消費者の立場に沿った内容が多く検討され、消費者団体もかなり注目しているとの話がありました。
 |
 |
|
| 冬木理事長(右)と佐々木産直推進室長(左) | 意見交換の様子 |
東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞授与式を行いました(令和6年1月10日)
令和5年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞を受賞された一般財団法人村田町ふるさとリフレッシュセンターの村上理事長に賞状の授与を行いました。
村田町特産のそらまめをはじめとした農産物の販売・振興のため、年間を通じたイベントの開催や地元マスコミへのPR活動をとおし、来客数と売上アップにつなげている取組が高い評価を得ました。
令和5年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」の選定結果について(東北農政局ホームページ)
 |
 |
 |
| 道の駅村田で行った授与式の様子 | 村田町ふるさとリフレッシュセンター 村上理事長(左)と山田地方参事官(右) |
授与式後に行った意見交換の様子 |
県内2JAの女性役員と意見交換を行いました(令和5年12月15日、26日)
12月15日にJAみやぎ仙南、12月26日にJA加美よつばを訪問し、女性役員と意見交換を行いました。
役員からは、就任時の不安感をぬぐった農協幹部の助言や自給率の低下に対する危機感、漬物等の農産加工の課題等幅広い意見をいただきました。
 |
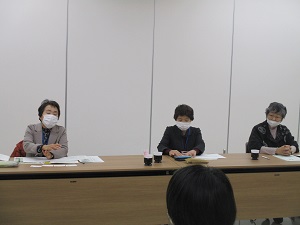 |
|
| JAみやぎ仙南の役員の皆さん | JA加美よつばの役員の皆さん |
東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」に選定された柴田農林高等学校と交流会を行いました(令和5年12月22日)
宮城県拠点は、令和5年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」として選定された柴田農林高等学校の皆さんと交流会を行いました。
活動は、同校の森林環境科森林専攻の貴重な収入源であったきのこが東日本大震災の福島第一原発事故の影響で栽培できなくなったことから始まります。今回の選定では、新しい収入源として演習林に自生するカエデ属の木の樹液からメープルシロップを製造し、地域の食品事業者等と連携してメープルシロップを活用した新商品づくりが評価されました。
中心メンバーである3年生からは、「重い樹液を山から降ろすことや、大鍋で煮詰める作業が大変だった。」との苦労話を伺いました。
令和5年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」の選定結果について(東北農政局ホームページ)
 |
 |
 |
| 選定証授与式の様子 | 交流会の様子(左から矢島さん、 菊地さん、佐藤さん、大和先生) |
樹液採取作業の様子 (柴田農林高等学校提供) |
東北地方環境事務所と連携し「生物多様性」に関する意見交換を行いました(令和5年12月19日)
宮城県拠点は東北地方環境事務所と共に、生物多様性保全に関心の高い大崎市、(有)伊豆沼農産及びJAみやぎ登米を訪問し、環境省が推進する「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を認定する自然共生サイトに関して意見交換しました。
環境事務所の担当者が自然共生サイトの仕組みなどについて説明し、大崎市は屋敷林「居久根(いぐね)」と周辺水田、旧品井沼周辺のため池群の下流水田、(有)伊豆沼農産は冬の間も水田に水を張る「ふゆみずたんぼ」、JAみやぎ登米は赤とんぼの乱舞する自然環境の復活を目指した「環境保全米」の生産水田を例に、自然共生サイトの活用の可能性などを意見交換しました。
 |
 |
 |
| 大崎市との意見交換の様子 | (有)伊豆沼農産との意見交換の様子 | JAみやぎ登米との意見交換の様子 |
 |
 |
 |
| 大崎市の屋敷林「居久根(いぐね)」 (写真:大崎市 提供) |
(有)伊豆沼農産のふゆみずたんぼ の生き物調査の様子 (写真:(有)伊豆沼農産 提供) |
JAみやぎ登米の環境保全米の生産水田 (写真:JAみやぎ登米 提供) |
宮城県内の学校給食用パンを製造する工場を訪問し、意見交換を行いました(令和5年12月14日、21日)
宮城県拠点は(公財)宮城県学校給食会と共に、名取市の「学校給食パン宮城協業組合」及び栗原市の「(株)熊谷製パン」の工場を訪問し、製造工程の説明を受けた後、意見交換を行いました。
県内の学校給食用パンは、令和4年度から国産小麦を100%使用しており、子どもたちからは「甘味がありもちもち感があっておいしくなった」と評判です。
宮城協業組合からは、「施設の老朽化に伴う設備更新や需要がある県内産小麦の確保などへの支援が必要」といった意見がありました。また、熊谷製パンからは、「国産小麦100%のパンのほかに、美里町の学校給食用として製造している町内産小麦「夏黄金」100%のパンについても生徒からの評判は良い」との情報がありました。
 |
 |
 |
| 学校給食パン宮城協業組合の工場外観 | パンの生地を成形する様子(名取工場) | 焼きたてのパンをコンベアに乗せて45分程度 冷ましている様子(名取工場) |
 |
 |
 |
| 国産小麦100%になり食パンやコッペパン が増えています(名取工場) |
意見交換の様子(12月14日) 学校給食パン宮城協業組合の皆さん(左) |
意見交換の様子(12月21日) 熊谷製パンの熊谷代表取締役(右) |
宮城県農業大学校の学生へ「水田農業ビジネス」の講義を行いました(令和5年12月8日)
12月8日、宮城県農業大学校水田経営学部の学生12名に対して「水田農業ビジネス」をメインテーマに、水田農業をめぐる状況、みどりの食料システム戦略、食料・農業・農村基本法の見直しについて若手職員が説明、紹介しました。
学生からは、「米の消費が年々減少する中で、農業者が生産だけでなく、マーケティングにも取り組んでいくべきと感じた。」「SDGsを意識して今後農業に取り組みたい。」「高齢化や鳥獣被害などの多くの対策が必要なことを改めて感じた。」などの声がありました。
 |
 |
 |
| 水田経営学部生の皆さんと宮城県拠点職員 (後列左) |
演壇に立つ宮城県拠点職員 | 真剣に講義に耳を傾ける学生たち |
イベントに出展し、みどりの食料システム戦略をPRしました(令和5年11月21日・22日、12月6日)
宮城県拠点は、JAグループ宮城主催の「営農支援フェスタ2023」(11月21日・22日、夢メッセ宮城)、みやぎ生協主催の「めぐみ野交流集会」(12月6日、仙台国際センター)に出展し、「みどりの食料システム戦略」をはじめとした主要施策のパネル展示や動画再生、チラシやパンフレットを来場者へ配布し、農林水産省の施策や事業について来場者へ周知しました。
 |
 |
 |
| 東北農政局が出展したブースの様子 (営農支援フェスタ) |
農林水産省の施策を紹介する職員(右) (営農支援フェスタ) |
屋外会場で展示された農業用機械 (営農支援フェスタ) |
 |
 |
 |
| 東北農政局が出展したブースの様子 (めぐみ野交流集会) |
みどり戦略の概要を説明する職員(右) (めぐみ野交流集会) |
多数の来場者で賑わう展示会場 (めぐみ野交流集会) |
県内3JAの女性理事と意見交換を行いました(令和5年11月27日~29日)
11月27日にJA古川、11月28日にJAみやぎ亘理、11月29日にJAいしのまきを訪問し、女性理事と意見交換を行いました。
理事の方々は農家、非農家と職業にとらわれずに選出されています。理事からは、食育に対する提言や「女性だけでなく男性の意識を変えなければ女性登用は進まない」等の率直な意見をいただきました。
 |
 |
 |
| JA古川 | JAみやぎ亘理 | JAいしのまき |
令和4年3月の福島県沖地震から復旧した美里グリーンベースを訪問しました。(令和5年11月16日)
宮城県美里町の「美里グリーンベース」は、リーフレタスを生産する次世代型植物工場として令和3年10月に生産を開始しました。令和4年3月の福島県沖地震により甚大な被害を受け生産量は大きく落ち込みましたが、現在は95パーセントまで復旧し、1日3万から3.6万株のリーフレタスを生産しています。
従業員の約3割はネパールからの特定技能実習生であり、インド出身のハスタック工場長は「従業員同士のコミュニケーションが大切で、話しやすい雰囲気作りを心掛けている。」と話されていました。
 |
 |
 |
| 被災3か月後(昨年6月)の施設内の様子 (生産量は30パーセント程度) |
現在は色とりどりのリーフレタスで 埋め尽くされています |
手早く収穫されたリーフレタスは、 ソイルブロックごと包装され、 全国に出荷されます |
 |
||
| 日本語のほか、英語とヒンディー語で 従業員とのコミュニケーションを図る ハスタック工場長 |
宮城県古川農業試験場で水田の排水対策について意見交換しました(令和5年11月10日)
宮城県古川農業試験場を訪問し、暗渠疎水材の簡易開削充填機(モミタス)の実演作業を見学しながら、畑作物を水田で栽培する際の排水対策について意見交換を行いました。
モミタスは暗渠管の上部にもみ殻を充填します。作業の前に暗渠管の位置を確認する必要があり、大変手間がかかります。RTK方式の自動操舵トラクターでは、もみ殻充填時に位置(座標)を記録できることから、次回から暗渠管の探査が不要で省力化が図られます。
 |
 |
 |
| 切削位置の確認。 写真のトラクターは100馬力(40馬力以上の機種で作業が可能である) |
もみ殻投入。 もみ殻は4~5メートルに1袋(約12キログラム)投入している。フレコンハンガーの取り付けも可能(その際は60馬力以上の機種で作業)。 |
開削充填作業。 トラクターは時速1キロで走行。補助作業員が棒で突っつくことでもみ殻が隙間なく入る。 |
 |
 |
 |
| モミタスによるもみ殻充填の様子 | トラクタ前輪による鎮圧。 開削した両脇からそれぞれ行うことで 均等で平らになり元の圃場に戻る。 |
鎮圧作業完了。 このあとに暗渠管に水を導くため、サブソイラーを横に3メートル間隔で入れている。 |
加美町長と意見交換を行いました(令和5年11月6日)
11月6日加美町を訪問し、今年8月に就任した石山敬貴町長と農業政策全般について意見交換を行いました。
石山町長からは、加美町の農産物等の輸出推進、地元の製粉業者と連携した米粉の利用拡大、有機農業産地づくりの推進、養蚕業の復活等に向けた取組を進めていきたいとお話がありました。
 |
 |
|
| 石山町長(左)と山田地方参事官(右) | 意見交換の様子 |
県内関係機関(農業会議、農業振興公社、水土里ネット)と意見交換を行いました(令和5年10月13日~26日)
宮城県拠点は10月13日から26日にかけて、宮城県農業会議、みやぎ農業振興公社、水土里ネットみやぎを訪問し、令和6年度予算概算要求の主要事業を説明するとともに、農政に関する意見交換を行いました。
各関係機関からは、「新たな農地転用が発生するたびに、地域計画を見直すのは負担が大きく困難(農業会議)。契約満期を迎える条件不利農地の遊休農地化が心配(農業振興公社)。土地改良事業は農業生産の基盤であり、食料安全保障に位置付けるとともに、土地改良区の体制強化への支援が必要(水土里ネット)」といった声がありました。
 |
 |
 |
| 宮城県農業会議との意見交換の様子 伊藤事務局長(中央) 山田地方参事官(右) |
みやぎ農業振興公社との意見交換の様子 江畑理事長(左) |
水土里ネットみやぎとの意見交換の様子 千葉専務理事(右) |
宮城県の農政部長と意見交換を行いました(令和5年10月10日)
10月10日、宮城県庁を訪問し、農政部の皆さんと意見交換を行いました。農政部長から地域計画の策定や中山間地域等直接支払交付金等の予算確保について要望がありました。後半は、農政部の副部長等に対し、令和6年度農林水産予算概算要求の主要事業を説明し、農政に関する意見交換を行いました。
 |
 |
|
| 農政部長(左奥)との意見交換の様子 山田地方参事官(右) |
農政部との意見交換の様子 農政部副部長(左から2番目) |
丸森町の高校生が大張沢尻棚田での稲刈り実習をする様子を取材しました(令和5年10月3日)
10月3日、丸森町の大張沢尻棚田(注)で伊具高校農学系列の2年生5名が稲刈り実習をする様子を取材しました。
作業始めにコンバインの機械トラブルがあり、生徒たちは手刈りの作業も体験することになりました。ぬかるんだ田に足を取られながらも、夏の草刈り実習で上達した鎌で、軽快に稲を刈っていきました。コンバインが作動してからは、1人ずつ運転して刈り取り作業に挑戦しました。同時にいくつもの操作が必要なため、はじめて体験する生徒たちは緊張した様子でした。
生徒たちは「棚田は丸森の誇り。これからもきれいに維持して、たくさんの人に広まってほしい」と口々に話していました。
(注)大張沢尻棚田は、「日本の棚田百選」 及び「つなぐ棚田遺産」 に選定されています。[農林水産省ホームページ]
 |
 |
 |
| 実習を行った大張沢尻棚田 7月に地域の方々が植えたヒガンバナは景観のためだけでなく、モグラ対策にも一役買っています |
手刈りした稲を手に、 誇らしそうな高校生たち |
棚田集落協定の大槻代表に見守られながら コンバインに挑戦する高校生 |
公益財団法人宮城県学校給食会と学校給食用パンの利用拡大について意見交換をしました(令和5年9月13日)
宮城県拠点では、公益財団法人宮城県学校給食会(以下、「宮城県学校給食会」と表記。)を訪問し、学校給食用パンの利用拡大やみやぎの環境保全米の米飯給食への提供について意見交換を行いました。
宮城県学校給食会からは、宮城県産小麦「夏黄金」生産者との連携や、宮城県学校給食会の食育推進における映像資料作成等の取組について話を聞くことができました。大沼理事長は、「宮城県拠点をはじめ他の関係機関と連携し、「夏黄金」利用拡大推進の取組を行っていきたい。」と話されていました。
 |
 |
 |
| 宮城県学校給食会の大沼理事長 | 昨年度から学校給食用パンは国産 小麦100%(うち宮城県産50%) 使用しており、好評を得ている |
意見交換の様子 山田地方参事官(右) |
丸森町に滞在中のザンビアからの研修生と地元農業高校生の交流の様子を取材しました。(令和5年9月12日)
丸森町耕野地区では8月下旬から約1か月間、アフリカのザンビア共和国の農業普及員の研修を受け入れていますが、宮城県伊具高等学校総合学科農学系列の生徒が研修にかかわり、研修生と交流しています。
8月25日は、町内の「大張沢尻棚田(注)」で研修生と高校生が稗(ひえ)取りを行いました。
9月12日は、交流会が開催されました。同校の農場で実習施設の見学や野菜の収穫作業体験を行い、研修生は母国にはない設備や技術についての説明を真剣に聞き、また令和元年台風19号の被害の跡を興味深く観察していました。『農業』という共通言語をもって、言葉の壁を乗り越えコミュニケーションを図る高校生たちの姿は頼もしく、印象的でした。
なお、宮城県拠点は交流会において、大張沢尻棚田における伊具高校の取組が模範的なのでホームページで紹介していることや、棚田の多面的機能とその重要性について英語で説明しました。
(注)大張沢尻棚田は、「日本の棚田百選」 及び「つなぐ棚田遺産」 に選定されています。[農林水産省ホームページ]
 |
 |
 |
| ザンビア人研修生と共に 稗取り作業をする伊具高校生 |
宮城県拠点、高校生と研修生が一緒に 昼食を取りながら和やかに過ごしました |
大張沢尻棚田で共に 汗を流した研修生と高校生 |
 |
 |
 |
| 宮城県拠点からは棚田の多面的機能と その重要性について英語で直接伝えました |
高校の実習施設に残る、令和元年 台風19号の浸水跡の高さに驚く研修生 |
高校の実習施設を見学する研修生。 暑さ対策の散水設備を体験 |
子実用とうもろこし実証圃場で2年目の収穫が行われました。(圃場:涌谷町)(令和5年9月1日)
涌谷地域農業再生協議会では、米・大豆との輪作作物として期待されている子実用とうもろこしの生産拡大に向けた試験栽培を行っています。昨年はアワノメイガ等による害虫被害により減収したこと、また、ドローンで散布可能な殺虫剤が登録されたことから、殺虫剤を散布した圃場と散布しない圃場を比較し防除の効果を検証しています。
9月1日開催の収穫実演会では、資材メーカーから「アワノメイガによるカビ毒を防止することで、製品の取引を行う際、優位な条件となるので殺虫剤の散布が望ましい。適正な時期に防除できれば1回の防除で十分効果がある。」との説明がありました。
今年は天候に恵まれ、カビや子実の脱落等の被害も少なく、登熟も大幅に早まり開花から60日足らずで収穫適期を迎えており、実証圃場では10アール当たり700キログラムの収量が見込まれています。
 |
 |
 |
| 刈取りはコーンヘッダーを装着した 汎用コンバインを使用 |
殺虫剤を2回散布した子実用とうもろこし。 色味も良くほとんど被害がない |
殺虫剤を散布していない子実用とうもろこし。 穂首にアワノメイガの害虫被害がみられる |
 |
 |
 |
| 刈取った子実をホッパーに入れ乾燥機へ (収穫時の水分は23パーセント) |
子実用とうもろこしの乾燥が できる汎用縦型乾燥機で調製 |
乾燥調製され製品となった黄金色の子実用 とうもろこし(水分13パーセントで調製) |
完熟発酵堆肥「郷の有機」の取組状況について話を伺ってきました(令和5年8月22日)
JA新みやぎあさひな地区のオーガニックプラントでは、管内地域から受け入れた畜産排泄物と回収した食品廃棄物等を使用し、高温発酵させた完熟発酵堆肥「郷の有機」を製造しています。フレーク状の堆肥は主にフレコン詰めで販売されていますが、他にフレーク状40リットル入りと粒状のペレット15キログラム入りの袋詰めを店頭販売しています。
「郷の有機」は管内地域の環境保全米の栽培に利用されており、JAでは予約を受けた水稲農家へ「郷の有機」を配達し、JAから委託を受けた生産組合が水田への散布を行っています。また、園芸農家にも利用されており、特に施設野菜の連作障害に有効で好評です。
オーガニックプラントの小川所長は「製品の成分内容を検討し、今後はペレットの製造量を増やしていきたい」と話されていました。
 |
 |
 |
| 小川オーガニックプラント事業所長(左) と山田地方参事官(右) |
オーガニックプラントでの高温攪拌の様子 | 「郷の有機」粒状のペレット15キログラム袋入り |
壽丸果樹園で「葉とらず樹成り完熟りんご」の生育状況を伺ってきました(令和5年8月9日)
宮城県白石市の壽丸(すまる)果樹園では、管理作業で大きな負担となる摘葉の省略と樹上完熟によって食味を向上させる「葉とらず樹成り完熟りんご」を栽培しています。また、堆肥等の有機肥料の施用により化学肥料(窒素成分)を慣行の01月02日に削減するとともに、病害虫の発生予防等の情報や園地の状況に応じ、効率的な農薬の選定、適期の防除により、農薬使用を抑制しています。
果樹園代表で地域特産物マイスターに認定されている菊地哲夫さんは、「今年は例年より暑く雨が少ないため、日焼けの被害が心配。ダニやカメムシも多い。台風の進路によっては落果被害も心配。」と話されていました。
 |
 |
 |
| 壽丸果樹園代表菊地さん(左) | 約2ヘクタールにわたり広がるりんご農園 | 壽丸果樹園のみなさま |
「夏休みこども見学デー」に宮城県拠点が環境保全米PRブースを出展しました。(令和5年8月8日)
8月8日、「夏休みこども見学デー」が東北農政局主催で開催されました。今回は「~みて、さわって、考えてみよう! わたしたちの食べものやくらし~」をテーマに、小学生とその保護者を主な対象として東北農政局各部だけでなく、他機関からも様々な企画や情報発信等が行われ、多数の来場者で賑わいました。
宮城県拠点では、みやぎの環境保全米をPRするブースを設けて、パネル展示や動画を再生するとともに、来場者にチラシやパンフレットを配布し、みやぎの環境保全米のPRを行いました。
 |
 |
 |
| 来場者に説明する宮城県拠点職員 | みやぎの環境保全米に関する展示 | パンフレットを配布する宮城県拠点職員 |
「はたけなか製麵株式会社」に国産小麦の利用状況を伺ってきました。(令和5年7月26日)
宮城県白石市の「はたけなか製麺株式会社」は、県内産や国産の小麦を使用し、地場産品の白石温麺をはじめ多種多様な麺製品を製造しています。
はたけなか製麺の特長は、材料となる小麦と麺に練りこむ野菜や海藻等の産地の特性に合わせた製品づくりです。また、地元大学との産学連携では、健康面に配慮した食塩不使用の麺製品の開発に取り組んでいます。
佐藤社長に国産小麦の利用状況を伺ったところ、「県内産、東北産の小麦を使用した麺がほしいと販売先からのリクエストが増えている」とのこと。はたけなか製麺では、品質の安定化やコスト面での工夫を凝らし、今後も白石市内の本社工場で製品を造り続けていくそうです。
 |
 |
|
| 自社製品の国産小麦利用 状況を語る佐藤社長(右) |
原料の小麦、塩分の量、麺帯の温度等、 日々探求を続けているとのこと |
JA宮城中央会の新会長と環境保全米について意見交換しました。(令和5年7月19日)
宮城県拠点はJA宮城中央会を訪問し、この度就任した佐野会長とみやぎの環境保全米について意見交換しました。
JA宮城中央会からは「今年で16年目となるみやぎの環境保全米の取組は、目的や意義が薄れてきており、改めて関係者へ研修を行っている」「環境にやさしい米づくりとして取り組んでいる環境保全米を環境に敏感な海外へ輸出している」といった取組について話を聞くことができました。
宮城県拠点からは「みやぎの環境保全米はみどりの食料システム戦略の先行した取組であり、特にSDGsを学んでいる子供たちへPRすることで家庭の消費につながる」といった消費者の理解醸成に向けての話をさせていただきました。
 |
 |
|
| JA宮城中央会の佐野会長 | 意見交換の様子 |
大張沢尻棚田で地元高校生の農業実習の様子を取材しました。(令和5年7月18日)
宮城県伊具高等学校では令和2年度から丸森町の大張沢尻棚田(注)で農業実習を実施しています。田植えから除草等の管理、稲刈りまでを行い、収穫した棚田米を加工してパン作りも行っています。今年3月に棚田地域の振興等に貢献したとして「つなぐ棚田遺産」のクリエイティブ部門の感謝状が贈呈されました。
今年度の大張沢尻棚田での農業実習の課程として、総合学科農学系列の生徒5名が草刈り機による除草と鎌を使った稗(ひえ)取りを行いました。棚田集落協定の大槻代表からレクチャーを受け、普段から農作業に親しんでいる生徒もそうではない生徒もしっかりと作業をしていました。大槻代表は、「みんな素直でよく話を聞いてくれるので、機械もすぐに扱えるようになる。将来、就農をしてもしなくても、きっと何かの役に立つと思う」と話していました。
(注)「日本の棚田百選」及び「つなぐ棚田遺産」に選定されています。
「つなぐ棚田遺産」感謝状について (農林水産省へリンク)
 |
 |
 |
| 大槻代表(左)の作業説明を しっかり聞く伊具高校の生徒たち |
草刈り機の使用は本日で2回目と話す生徒 もしっかりと操作できるようになりました |
大槻代表に見守られながら 黙々と作業を続ける生徒 |
地域活性化に取り組む「はなやまネットワーク」を訪問しました。(令和5年7月14日)
宮城県栗原市の一般社団法人はなやまネットワークは、花山地区が抱える人口減少や交通の不便等の課題に対応するため、空き家を利活用した移住体験交流や乗合デマンド交通、移動販売車での買い物支援等を行っています。
花山地区の人口は、年々減少し続けているため空き家が増え、高齢化率は56%となり栗原市内でも突出しているため、はなやまネットワークでは、移住者の受け皿として空き家を「住める空き家」にして、地区の女性たちや地域おこし協力隊が中心となって小正月料理づくりやカゴあみ、そば打ち教室などの田舎暮らし体験プロジェクトを毎年行ってきました。その効果もあってか、現在の移住者は、約20名となり、地元の方と結婚し花山地区に住み続けている地域おこし協力隊員もいるとのことです。地域の課題解決に向け農山漁村の活性化に取り組んでいる優良事例として、昨年度の第9回ディスカバー農山漁村(むら)の宝AWARDに選定されました。
地区にある花山湖は、近年、ワカサギの釣り場として注目を集め、冬には多くの釣り人が訪れていることもあり、はなやまネットワークの佐々木事務局長は、「今後は、自然豊かな花山地区のアウトドアを満喫するツアー等を企画し、民泊を開業して賑わいのある地域にしたい」と意気込みを話されました。
 |
 |
 |
| はなやまネットワーク 佐々木事務局長 |
意見交換の様子(正面左側: 地域おこし協力隊の海山さん) |
乗合デマンド交通のワゴン車 (運賃は一律300円) |
「鶏の健康を第一に」株式会社栗駒ポートリーと意見交換を行いました。(令和5年7月11日)
宮城県栗原市で採卵養鶏・鶏卵販売等の事業を展開する株式会社栗駒ポートリーは、市内と関東に鶏卵生産農場及び卵の洗卵、選別、パック詰め等を行う工場があり、年間約1万8千トンの卵を生産・販売しています。
宮城県拠点は、日本政策金融公庫仙台支店とともにHACCP(注)の認定を受けた市内の工場を訪問し、同社の事業概要と工場内の設備について説明を受け、鳥インフルエンザによる影響や卵の輸出等について意見交換を行いました。
オートメーション化された工場は、汚卵、ひび卵、異常卵を検査する装置や、パック詰め装置等の最先端の設備が揃っていました。同社では、安心安全な卵を消費者へ届ける仕組みづくりが行われており、農場から送られてきた卵が出荷されるまでのすべての製品工程がHACCPに沿って徹底管理されていました。
(注)HACCPは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。(厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html)
 |
 |
 |
| 意見交換の様子 栗駒ポートリー(奥) |
機械の説明を受ける山田地方参事官(右) | 汚卵検査装置とひび卵検査装置を通る卵 |
 |
 |
 |
| 高精度な画像分析により 正確に汚卵を検出します |
卵を軽く叩いたときの音色を分析し 音感の判別により瞬時にひびを検出 |
工場内は厳格に作業区域が分けられて おり、衛生管理が徹底されています |
「農業機械フェア2023」に東北農政局がブースを出展しました。(令和5年6月21日~22日)
令和5年6月21日から22日に夢メッセみやぎで開催された「農業機械フェア2023」(JAグループ宮城主催)では、新型農機や先進農機をはじめとした農業機械の展示だけでなく、営農情報やICT・デジタル田園化構想などのスマート農業に向けた情報発信が行われ、多数の来場者で賑わいました。
東北農政局も、「みどりの食料システム戦略」をはじめとした各種施策のパネル展示やスマート農業の動画を再生するブースを出展し、来場者に施策のチラシやパンフレットを配布しました。
 |
 |
 |
| 東北農政局が出展したブースの様子(1) | 東北農政局が出展したブースの様子(2) | 展示された農業用機械(1) |
 |
 |
 |
| 展示された農業用機械(2) | 展示された農業用機械(3) | 展示された農業用機械(4) |
大衡村の新村長と意見交換を行いました(令和5年6月20日)
宮城県拠点の山田地方参事官は、大衡村役場を訪問し、今年4月に就任された小川村長へみどりの食料システム戦略などの最近の農業施策等の情報提供を行うとともに、大衡村の吉田川水系の流域治水の取組を背景としたほ場整備と田んぼダムの取組、担い手の育成・確保等の地域農業の課題等について、幅広く意見を交わしました。
 |
 |
|
| 小川村長(左)と山田地方参事官 | 意見交換の様子 |
「ヤマザワ古川北店」へ東北農政局長からの感謝状をお届けしました。(令和5年6月8日)
宮城県拠点は、食品価格動向調査事業の協力店として貢献したヤマザワ古川北店(大崎市)を訪問し、東北農政局長からの感謝状を店長の堀江さんに手交しました。
食品価格動向調査事業は、食品の小売価格等を把握し、食品の価格安定対策の推進に資することを目的に、昭和53年度から実施しており、現在の調査協力店は全国で470店舗となっています。
東北農政局では表彰審査会を開催し、調査業務に関する情報提供に5年以上協力し、かつ、調査業務の推進等に功績のあった東北各県の協力店の中から、表彰者を選定しました。
今回、表彰されたヤマザワ古川北店は、平成30年4月から調査を委嘱され、今後も引き続き調査協力店としてご対応いただくこととしています。
 |
 |
|
| 感謝状を手交する宮城県拠点の 山ノ内総括農政推進官 |
感謝状を手にする ヤマザワ古川北店の堀江店長 |
日本政策金融公庫仙台支店と連携強化を図るため情報交換しました。(令和5年6月1日)
宮城県拠点は、県内関係機関と連携強化を図り、現場の課題や要望を把握するとともに、解決に向けた取組を行うため、本年1月に引き続き、日本政策金融公庫仙台支店(以下、「公庫」と表記。)と情報交換を行いました。
今回は、ワイナリー設立のため、醸造免許と6次化の認定取得を目指している生産者の情報や、酪農経営における主食用品種での稲WCS(ホールクロップサイレージ)の課題について、公庫から情報提供を受けました。
宮城県拠点からは、以前に公庫から紹介された事業者の課題等を把握するため、公庫とともに訪問し連携して対応していくことを確認させていただきました。
 |
 |
|
| 日本政策金融公庫仙台支店の 平田事業統括 |
意見交換の様子 日本政策金融公庫(左)、宮城県拠点(右) |
宮城県農業大学校から食料・農業・農村基本法の検証・見直しへの意見等を伺いました。(令和5年5月25日)
宮城県拠点の山田地方参事官は、宮城県農業大学校を訪問し水田経営学部の皆さんへ食料・農業・農村基本法(以下、「基本法」と表記。)の講義を行いました。
基本法の検証・見直しについては、食料・農業・農村政策審議会の基本法検証部会において、昨年10月の1回目から15回(5月25日現在)の検討を重ねているところですが、幅広い層からの意見を踏まえた検証とするため、農林水産省は特に学生、若手農業者、農業女子から意見を伺う取組を行うこととしており、今回の講義は大学の協力を得て実施したものです。
講義を受けた学生の皆さんからは「法人だけでなく個人農家も営農継続できることが大事。個人農家も支えていくような法律にしてほしい。」といった要望や、「国は自給率の低い作物の生産を推進していくと思うが、例えばデュラム小麦は作れるのか、生産の現場とズレはないのか。」といった意見がありました。
宮城県拠点では、今後も幅広い層から意見を伺うため、県内の関係機関と連携して意見集約を行います。
 |
 |
 |
| 講義をする山田地方参事官 | 学生との意見交換の様子 | 水田経営学部の皆さんと山田地方参事官(中央) |
高収益作物の栽培、新規就農者等への技術指導に尽力する村田町の農家を訪問しました。(令和5年5月22日)
アスパラガスやそらまめ、スイートコーンなど多様な高収益作物を栽培している村田町の佐藤民夫さんを紹介します。佐藤さんは、作目毎に複数品種を栽培し、肥培管理など栽培技術の試行錯誤を繰り返しながら、村田町の土地と気候に適した品種を選択して生産しています。作業の省力化などコスト削減を徹底する一方、自ら値をつけて地元の農産物直売所で販売することにより所得向上に取り組んでいます。
また、長年に亘り収集した品種毎の特性や栽培技術を積極的に農業専門誌へ投稿し、各地での講演や視察の受け入れなどを通して技術の普及に努めるとともに、就農希望者の研修にも携わるなど、地域農業の発展、農業者育成に尽力しています。
 |
 |
 |
| アスパラガス栽培の状況を説明する 佐藤民夫さん |
ハウス内で意見交換しました | 丹精込めて生産したアスパラガス |
「黄金レモンの花が咲いている」涌谷町の園芸農家を訪問しました。(令和5年5月15日)
涌谷園芸ファームでは、4品種のレモン約180本を独自の肥培管理により無農薬で栽培しています。中でも糖度が11度もあるレモンは、涌谷町が日本初の「金」の産地であることにちなんで、「黄金レモン」と名付けられました。これらのレモンは、主に県内の飲食店に販売していますが、渋みやえぐみが少なく皮まで美味しいとの評判が広まり、町内外から涌谷園芸ファームへ直接買いに来る人が増え、本年産のレモンはすぐに完売したそうです。
今後は、300キログラム以上の収穫を目指し、300本程度まで生産規模を拡大する予定です。
 |
 |
 |
| ハウスでのポット栽培。12月から収穫できるよう、11月から4か月程度加温しています。 | レモンの花は4月から次々と咲き始め、黄金レモンの花も咲いていました。 | 自家消費用に冷凍したレモン。真ん中が黄金レモンです(両側の黄色いレモンと違い、オレンジに近い色が特徴)。 |
木の香り漂う「JAみやぎ登米」の新庁舎を訪問し、意見交換を行いました。(令和5年5月8日)
宮城県拠点は、今年度から新庁舎での営業を開始したJAみやぎ登米本店を訪問し、「みどりの食料システム戦略」の取組等について意見交換を行いました。
登米市は、全国有数の環境保全米と仙台牛の生産地であり、耕畜連携による地域循環型農業に取り組む先進地です。
JAみやぎ登米は、新庁舎建築にあたっても地元森林組合の協力のもと、主に登米市産のFSC認証材(注)である杉材を使用する木造建築としました。
JAの佐野組合長からは、新庁舎のコンセプトは「ヨリアイ(寄り合い)」。「ここに来れば誰かと会える、ほっとする、困りごとは皆で解決しよう」と思える場所にしていきたい。そして、今年の秋には、将来を担う子供たちが気軽に遊び回り、JAを身近に感じてもらえるよう、庁舎の庭に標高2メートル程の「おにぎり山(ヨリアイひろば)」を造る計画が語られました。
(注)森林認証制度は、第三者機関が、森林経営の持続性や環境保全への配慮等に関する一定の基準に基づいて森林を認証するとともに、認証された森林から産出される木材及び木材製品(認証材)を分別し、表示管理することにより、消費者の選択的な購入を促す仕組み。
「FSC認証」は世界自然保護基金(WWF(World Wide Fund for Nature))を中心に発足した森林管理協議会(FSC(Forest Stewardship Council))が管理する国際的な森林認証制度。
 |
 |
 |
| 地域に開かれたような 縁側のある新庁舎の外観です |
庁舎の中心となる「ヨリアイホール」では、4月に登米ジュニア吹奏楽団による ロビーコンサートが行われました |
日本の木造伝統工法が施された吹き抜けは、天井の八角形の束ね柱と八方向に伸びる重ね肘木が特徴的です |
 |
 |
 |
| 庁舎の所々には市内の高校生の 絵画や写真が展示されています |
佐野組合長から建物構造の 説明を受けました |
完成後の「ヨリアイひろば」の イメージです |
自動操舵トラクターによる子実用とうもろこし播種実演会を見学しました。(圃場:美里町)(令和5年4月25日)
涌谷地域農業再生協議会が行っている「子実用とうもろこし生産拡大に向けた実証試験」の2年目がスタートしました。令和5年産の播種は昨年より10日程度早い4月12日から行われ、50ヘクタールの作付けを計画しています。
実演会は、真空播種機とバキュームシーダ側条施肥ユニットを搭載した自動操舵トラクターで播種し、自動操舵で播種できない外周は運転手が操縦しました。実証圃場は、昨年7月中旬の大雨で出来川が氾濫したため冠水し、低収量となりましたが、今年は10アール当たり550キログラム以上の収量を目指しています。
 |
 |
 |
| 自動操舵による播種は 1ヘクタールを30分弱で終えます |
播種箇所はタブレットに色付けされます | 株間は18センチメートル前後、播種深度は3~5センチメートルで播種されていました |
「子実用とうもろこし」の播種作業実演会が行われました。(JA古川)(令和5年4月19日)
新たな転換作物として注目されている「子実用とうもろこし」の播種作業実演会がJA古川の主催により大崎市で開催されました。実演会には県内外から多くの関係者が出席され、子実用とうもろこしへの関心の高さがうかがえました。
当日は天候に恵まれ、目皿式播種機や真空播種機を装着したトラクターによる実演が行われ、種苗会社の担当者から、「最も大切なのは播種作業であり、条間と株間・播種深度をしっかり調整し、高速での播種作業は控える」等の説明がありました。また、JA古川大豆・麦・子実用トウモロコシ生産組織連絡協議会の鈴木会長から、「大崎市は本州一の大豆の産地であり、子実用とうもろこしを輪作体系に組み入れることにより大豆の収量アップに繋げていきたい、今年の子実用とうもろこしは10アール当たり700キログラムの収量を目標に取り組みたい」と抱負を話されました。
JA古川が推進する令和5年産の子実用とうもろこしの作付面積は、102ヘクタールを超える見込となっています。
 |
 |
 |
| 開会の挨拶をするJA古川の 佐々木代表理事組合長 |
挨拶をするJA古川生産組織 連絡協議会の鈴木会長 |
挨拶をする伊藤大崎市長 |
 |
 |
 |
| 目皿式播種機による播種作業の実演 | 子実用とうもろこしの種子・肥料 | 真空播種機による播種作業の実演 |
過去の宮城フォトレポート
|
|
お問合せ先
宮城県拠点〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号(仙台合同庁舎A棟)
代表:022-263-1111(内線4510)
直通:022-266-8778




