中国四国消費生活・食育ネットワークメールマガジン第47号
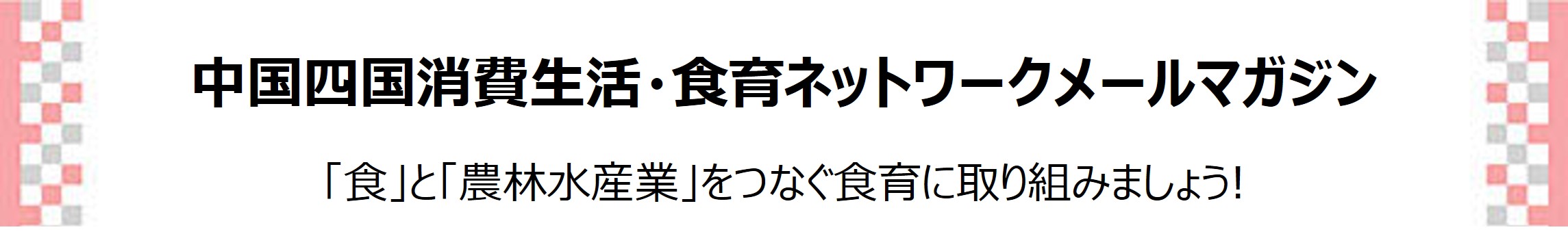
★もくじ (^_^)v
1 注目情報
◆ 野菜・山菜と似た「有毒植物」に注意しましょう!
例年、春先から初夏にかけて、野菜や食べられる山菜・野草と間違えて「有毒な成分を含む植物」を食べてしまうことによる食中毒が数多く発生しています。
食用と確実に判断できない植物は、絶対に採らない、食べない、売らない、人にあげないようにしましょう。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(中国四国農政局ホームページ)
https://www.maff.go.jp/chushi/anzen/seisan/yuudoku.html
◆ 第1回みどり戦略学生チャレンジ(全国版)中国四国ブロックの受賞チーム決定
農林水産省は、みどりの食料システム戦略の実現に向けて、将来を担う若い世代の環境に配慮した取組を促すため、大学生や高校生等によるみどりの食料システム戦略に基づく取組を表彰する「第1回みどり戦略学生チャレンジ(全国版)」を実施しました。
中国四国ブロックでは、中国四国農政局長賞をはじめとする各賞の受賞チームを決定しましたので、お知らせします。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(中国四国農政局ホームページ)
https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/250226.html
2 中国四国農政局からのお知らせ
◆ 「食に関するお役立ちBOOK」好評配信中!
中国四国農政局では、これから新生活を始める(始めた)若い方や単身者の方などへ、新生活が始まる前に知っておいてほしい、知っていると便利な知識を提供し、健康を維持して楽しい新生活を送ってほしいという思いから、「これから新生活が始まる皆さんへ 食に関するお役立ちBOOK~健康を維持して楽しい新生活を!~」を作成しましたので、是非ご活用ください。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(中国四国農政局ホームページ)
https://www.maff.go.jp/chushi/syokuiku/katudou/oyakudati.html
◆ 消費者の部屋展示のご案内
〇「瀬戸内海国立公園展」
瀬戸内海国立公園は、1934年3月16日に雲仙、霧島とともに日本で最初に指定された国立公園で、自然と人の暮らしが溶け込んだ風景が特長です。昨年は、指定90周年を迎え、各地で開催された行事等は多くの方でにぎわいました。
今回の「消費者の部屋」の展示では、瀬戸内海国立公園の四季折々の風景だけでなく、多様な歴史文化、産業、食、体験など自然と人の暮らしがともにある国立公園に興味を持ち、訪れるきっかけとなるようパネルや動画で紹介します。
【開催日時】
令和7年3月17日(月曜日)~4月4日(金曜日)
9時00分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く。最終日は13時まで)
【開催場所】
中国四国農政局「消費者の部屋」展示コーナー
岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎1階
【展示内容】
・瀬戸内海国立公園、国立公園等の紹介
・瀬戸内海国立公園プロモーション動画上映 など
「消費者の部屋」webサイトでは、展示の様子をご覧いただけます。
https://www.maff.go.jp/chushi/heya/index.html
<詳しくは、こちらをご覧ください>(中国四国農政局ホームページ)
https://www.maff.go.jp/chushi/press/seikatsu/250303.html
◆ 食育ネットワークに加入して食育の輪を広げませんか?
中国四国農政局では、食育についての情報交換や情報発信、連携・協力を行う「中国四国食育ネットワーク」の会員を募集しています。会員の方には、全国の食育に関する情報やイベント情報等をいち早くお届けするとともに、会員の方の活動状況やイベント予定をホームページやメールマガジン等で紹介し、広く情報発信します。
すでに食育や農林漁業体験活動に取り組んでいる方、これから食育に取り組むなど食育に関心がある方、「食育」よくわからないけど、イベント等参加してみたい方など、是非ご加入ください。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(中国四国農政局ホームページ)
https://www.maff.go.jp/chushi/syokuiku/syushi_nyukai/index.html
◆ 皆様が開催される研修会などに講師を派遣します!
日々の暮らしの中で、「この食品は安全?」、「将来、食料や農業は大丈夫?」、「災害時に備えた家庭での食品備蓄はどうしたらいいの?」といった疑問を持たれることはありませんか。
そんな疑問にお答えするため、中国四国農政局では、消費者団体等の皆さまのご希望の日時・場所に、職員を無料で派遣する「食と農の知っ得講座」を実施しています。
「持続可能な食を支える食育の推進」の講座では、食育ピクトグラムを使って様々な食育の取組を紹介し、持続可能な食を支えるために私たちができることを一緒に考えていきます。是非ご利用ください。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(中国四国農政局ホームページ)
https://www.maff.go.jp/chushi/heya/kouza.html
3 農林水産省からの情報
◆ 肉用鶏の衛生水準の向上等に関する検討会の中間取りまとめを公表しました
カンピロバクター食中毒は、細菌性食中毒の中で、平成15年以降、毎年、最も発生届出件数が多く、生や加熱不十分な鶏肉の喫食による食中毒が依然として発生しています。肉用鶏の生産段階から消費までのフードチェーン全体における食中毒低減の取組の更なる推進が課題です。
肉用鶏の衛生水準の向上等に関する検討会においては検討の視点として1.技術面の課題、2.社会の意識向上の面の課題、3.情報発信の面の課題について議論し、以下の対応の方向性を取りまとめました。
1.技術面の課題
データに基づく科学的根拠による低減対策を推進するため、
・産官学が連携した調査実施体制(協議会)の構築
・フードチェーンを通じた定量データの収集
・対策に資する管理手法の明確化及び簡便な検査手法の確立
・調査結果等の生産現場への活用
2.社会の意識向上の面の課題
フードチェーン全体の衛生に関する取組の環境醸成を推進するため、
・生産者・食品関連事業者による衛生に関する取組の社会に向けた発信(自主取組宣言の仕組の構築)
・「自主取組宣言」運動の展開による食品安全意識の社会への定着
3.情報発信の面の課題
効果的な情報提供に基づく行動変容を推進するため、
・食肉の生食での喫食頻度が高い年齢層(20代から30代)を対象とした取組
・小中学生を対象とした取組
・飲食店従業員への教育に係る取組
上記3つの面の課題への対応による相乗効果により、カンピロバクター食中毒の低減につなげていきたいと考えています。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/seisaku/250314.html
◆ 英語版みえるらべるの愛称が決定!
農林水産省は、みどりの食料システム戦略に基づき、農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」を推進しています。令和6年3月に本格運用を開始後、同年6月からは「みえるらべる」の愛称で取組を進めてきた中、今般、インバウンド需要への対応や輸出展開を見据え、英語版みえるらべるを作成し、本ラベルの愛称を「ChoiSTAR(チョイスター)」に決定しましたので、お知らせします。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/250312.html
◆ 2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)に出展します
農林水産省は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)にて「農林水産業と食文化の発展は世界をもっと豊かにつなぐ」をコンセプトに、6月7日(土曜日)から6月15日(日曜日)まで展示を行います。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/wasyoku/250124.html
◆ 令和6年度 米の流通状況等について
農林水産省は、これまで公表した令和6年度の米の流通状況等に関するデータ等について、流通段階別に整理したページを作成しています。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/r6_kome_ryutu.html
◆ “今週のお手頃野菜”をお知らせします!
野菜はビタミンやミネラル、食物繊維、機能性成分が豊富に含まれています。お手頃野菜を活用して、毎日を元気に過ごしましょう。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/otokuyasai.html
◆ 鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及について
政府としては、鶏肉・鶏卵は「安全」であり、我が国の現状において、家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザに感染する可能性はないと考えています。
なお、鳥インフルエンザに感染した鶏肉・鶏卵が市場に出回ることはありません。
一方、鳥インフルエンザウイルスは、通常、ヒトに感染することはありませんが、感染したトリに触れる等濃厚接触をした場合など、きわめて稀に鳥インフルエンザウイルスがヒトに感染することがあります。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html
4 環境省からの情報
◆ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針等の公布及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(案)意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)の基本方針等が令和7年3月14日(金曜日)に公布されましたので、意見募集(パブリックコメント)の結果とともにお知らせします。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(環境省ホームページ)
https://www.env.go.jp/press/press_04594.html
5 消費者庁からの情報
◆ 風評に関する消費者意識の実態調査(第18回)について
消費者庁では、東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、平成25年(2013年)から被災県の農林水産物等に対する消費者意識の実態調査を行っており、今般、第18回目となる調査を実施しました。
普段の買物で産地を気にする理由として「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」と回答した人の割合は11.4%となり、昨年(9.3%)を約2ポイント上回りました。同様に、放射性物質を理由に購入をためらう産地として「福島県」及び「被災地を中心とした東北」と回答した人の割合も昨年を上回りました。
「十分な情報がないため、リスクを考えられない」と回答した人の割合は34.6%となり、昨年(30.4%)を約4ポイント上回りました。また、「食品中の放射性物質の検査が行われていることを知らない」と回答した人の割合は65.0%となり、昨年(61.5%)を約4ポイント上回りました。
風評を防止すべきために行うこととして、食品の安全に関する情報提供、科学的な説明、また、産地や産品の魅力発信との回答が多く挙げられました。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(消費者庁ホームページ)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/041338/
6 中国四国地域で行われる食育の取組(4月の予定)
◆ 「第5回 食と健康セミナー(良い食品の見分け方)」を実施(広島県)
食未来プロジェクトでは、生鮮食品や加工食品などの良い食品の選び方を学び、安全安心で美味しく、健康的な食生活を送るための勉強会を全12回コース(第4回まで終了)開催します。普段の食生活が健康に及ぼす影響や、食品を見分けるために必要な知識や情報について分かりやすく説明します。
内容:塩、砂糖、蜂蜜、みりん
日時:(1)令和7年4月8日(火曜日)10時00分~11時30分
(2)令和7年4月17日(木曜日)10時00分~11時30分
場所:(1)広島市南区民文化センター3F小会議室
(2)廿日市市文化ホールさくらぴあ1F会議室
講師:野本利夫(上級食育アドバイザー)
募集人数:各会場15名
参加料:1,000円
お申込み:下記宛にTel、Fax、Mailいずれかでお申込みください。(締切:各セミナーの1週間前まで)
主催:食未来プロジェクト
【問い合わせ先】Tel 080-2262-2823
Fax 050-1344-0339
Mail shokumirai@hi3.enjoy.ne.jp
<詳しくはこちらをご覧ください>
第5回 食と健康セミナー(PDF : 478KB)
◆ 「子育て相談」を実施(香川県高松市)
香川県栄養士会では、さぬきこどもの国において、子どもたちの心と身体の健やかな育ちをサポートするため、子育て全般・子どもの食事等についての相談を受け付けます。
内容:子育て全般・子どもの食事等についての相談
日時:令和7年4月10日(木曜日)、24日(木曜日)10時30分~15時00分
場所:さぬきこどもの国(香川県高松市香南町由佐3209)
主催:さぬきこどもの国
協力:(公社)香川県栄養士会
【問合せ先】さぬきこどもの国(Tel 087-879-0500)
(公社)香川県栄養士会(Tel 087-811-2858)
◆ 「みなスポ!かがわ2025」に参加(香川県高松市)
香川県民誰もが共にスポーツやレクリエーション活動に親しむイベント「みなスポ!かがわ2025」が開催されます。
香川県栄養士会では、握力測定、野菜釣り掘、栄養相談を実施します。
内容:握力測定、野菜釣り掘、栄養相談
日時:令和7年4月29日(火曜日・祝日)10時00分~16時00分
場所:あなぶきアリーナ香川(香川県高松市サンポート)
主催:県民スポーツ・レクリエーション祭実行委員会
【問合せ先】県民スポレク祭実行委員会事務局(Tel 087-832-3762)
(公社)香川県栄養士会(Tel 087-811-2858)
7 郷土料理のご紹介
◆ ふきのとう味噌(島根県 出雲地方、石見地方など)
春の味覚としてお馴染みのふきのとう。清らかな水と肥沃な大地に恵まれた島根県でも親しまれています。田畑のあぜ道や山間部の山林、市街地の土手や公園まで、さまざまな場所に姿を見せ春の到来を告げる山菜です。
お年寄りが散歩の途中に拾ってきたり、子どもたちが下校途中に拾ってきたり、いたるところに自生するふきのとうが各家庭の食卓を飾ります。農園の一部を利用してふきのとうを栽培する農家も存在します。
ふきのとうは、冷凍保存ができるため、大量に調達して1年を通して、ふきのとう料理を楽しむことも可能です。とれたふきのとうは、天ぷらや和え物、炒め物などに活用されます。味噌とふきのとうを和えた、「ふきのとう味噌」はごはんのおともや、お酒のつまみとしても定番です。
<詳しくは、こちらをご覧ください>(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/fukinotomiso_shimane.html
【編集後記】
♪ああ 男の子って 私を悩ませるわ♪
「自分で歩く!(抱っこした腕の中で身をよじり、スルリと着地)」「自分で食べる!(食べさせようとする私の手を払いのける)」「そっちの方がおいしそう!ちょうだい!!(隣で同じものを食べようとする私を指さし、あ″―と怒る)」「お代わり!(お鍋を指さし、空の器を指でトントン)」
→まさか、1年でこんなにも成長(主張)するとは…。
去年の今頃は、あてもなくベビーカーを押していました。今年は、何を見ても目をキラキラと輝かせて喜ぶ我が子と共に春の訪れを楽しみたいと思います。私が誰よりいちばん♡♡♡
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆このメールマガジンは、登録していただいた方々に配信しています。
配信の変更などはこちらからどうぞ。
https://www.maff.go.jp/chushi/mailm/index.html
◆また、中国四国農政局ホームページにも掲載しておりますので、ご確認ください。
https://www.maff.go.jp/chushi/mailm/syokuiku/backno/index2.html
◆本メールマガジンでは、中国四国食育ネットワーク会員からの情報(食育イベントや体験講座など)についてもご紹介させていただきます。
皆様からの積極的な情報提供をお待ちしています!
◆本メールマガジンへのご意見・ご要望、または転載を希望される場合は、メールでお知らせください。
寄せられたご意見などは、個人情報を伏せた上でご紹介させていただくこともございますのであらかじめご了承ください。
◆お問い合わせ窓口
https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161125.html
◆ホームページURL
https://www.maff.go.jp/chushi/
◆編 集
〒700-8532 岡山市北区下石井1-4-1
中国四国農政局 消費・安全部 消費生活課
TEL:086-224-9428
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
<( _ _ )> 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 <( _ _ )>
お問合せ先
消費・安全部 消費生活課
担当者:食育推進班
ダイヤルイン:086-224-9428




