令和5年度 食育の取組紹介
境 嘉代子氏(農家レストラン大門:富山県砺波市)
 |
| 境 嘉代子氏(後ろは「花嫁のれん」) |
 |
| 農家レストラン大門(アズマダチ家屋) |
 |
| 農家レストラン大門で提供する御前 |
 |
| 小学校料理クラブ活動 |
 |
| PTA親子地場料理教室 |
令和6年2月7日、富山県砺波市で活発に食育活動等に取り組んでいる、「農家レストラン大門(おおかど)」女将の境 嘉代子(さかい かよこ)氏にお話を伺いました。
境氏は、空き家となっていた明治30年建築(現在は築126年)の砺波の伝統的家屋「アズマダチ」を活用し、郷土料理を提供する「農家レストラン大門」を切り盛りする傍ら、郷土料理の保存・継承活動に取り組んでいます。
農家レストラン大門株式会社は、地場産農産物を活用した優れた取組により、平成28年度地産地消給食等メニューコンテスト「外食・弁当部門」において、北陸農政局長賞を受賞しています。
また境氏は、令和5年7月に砺波の伝承料理を軸とした食育活動により、「第2回北陸農政局食育活動表彰 北陸農政局長賞」を受賞しました。
【食育活動の取組内容を教えてください】
1.食生活改善推進員の取組
平成11年から、食を通した健康づくりのボランティアである食生活改善推進員を、近所の人からの誘いをきっかけに、「料理のレパートリーが増えたらいいな」くらいの軽い気持ちで始めました。
料理教室をすることになって、最初は分からないことが多く失敗続きでしたが、食生活改善推進員の先輩や地元の管理栄養士さんに教えてもらいながら続けました。
その中で、後輩たちが同じ思いをしないよう、レシピや資料をきちんと整理して残してきました。そのおかげで、伝承料理を調べたり、子供たちに伝承料理を教えたりするのに、ずいぶんと役立っていると思います。
また、食生活改善推進員のとき、管理栄養士さんからアドバイスをもらってレシピを作ったことで、塩分を控えた「薄味」を覚え、現在提供している料理にも役立っています。
食生活改善推進員をやめた今でも、市から料理教室を依頼されて、年に一度はかぶらずしを教えています。ほんとうは糀から作るのですが、なるべく簡単にできるように買えるものは買って、調味料も少し工夫して、それを教えています。
2.「卯月(うづき)の会」の取組
平成18年に、市役所から障がい者の自立支援を行えないかというお話をいただきました。市の食生活改善推進員協議会には負担が大きいと考え、退会した食生活改善推進員の経験者を中心に、ボランティア団体「卯月の会」を結成しました。
障がいを持った方が、介助者がいなくなった時、一人でも生活していけるようになってもらいたいという思いで調理指導を始めました。
参加するのは、20~40歳代の心身に障害のある方です。初めて顔を合わせたときは、なかなか心を開いてくれず、調理実習もうまくできませんでしたが、回数を重ねていくうちに私たちにも慣れ、料理も楽しんでくれるようになりました。
3.地域の子供たちへの食育
地元の小学校で、料理クラブの講師や親子料理教室を行っていましたが、コロナ禍では小学校に郷土料理のレシピを配布して、自宅で調理を体験してもらいました。
中学2年生の職場体験に来た生徒には、食材とレシピを渡し、どのように調理するのか見せます。そして、自分の家で作ってもらい、翌日作ったものを持ってきてもらうという取組を行っています。
レシピは、昔のままの手順だと面倒なので、少し簡単にして、味付けも少し現代にあうように変えています。
コンビニや飲食店など、自分で調理しなくても簡単に食事ができるようになっており、自分で調理しない人が多くなっています。郷土料理は若い方は食べないと思われがちですが、自分で作れることがわかると、自信がつき、ほかの料理にも興味を示してくれるようになります。その結果、子どもたちだけでなく、そのご家族にも郷土料理が伝わり、定番料理になったということもあります。
核家族化や共働きで郷土料理の伝承ができなくなってきていますが、このように新しい形で、子どものときから伝承料理に馴染んでもらえるよう、「食育」に取り組んでいます。
【北陸農政局長賞受賞後の変化を教えてください】
受賞したからということではありませんが、「料理学校の学生が洋食ばかり専攻しているため、和食について講演してくれないか」という打診が料理学校からありました。また、東京・新宿で全国各地の料理を提供している店の板前さんが、富山の郷土料理を教えてくださいと言いに来られました。そのときは、東京の富山出身の方に地元の味を感じてほしいと思い、「ほうきんの実※のよごし」のレシピを渡しました。
郷土料理に関する問合せが増えていることから、少しずつ皆さんが昔の料理は伝承しなければならないと分かってきていると感じています。
※ほうきんの実とは、ほうき草(アカザ科ホウキギ属の一年草であるホウキギ(昔は茎を束ね、ほうきとして利用))の実のこと。直径1~2mmの粒状で、味はないが、プチプチした魚の卵に感じられる食感を楽しむ食材。その食感から「畑のキャビア」などとも呼ばれる。コキア。
【今後の活動予定について教えてください】
小学6年生の子供たちに、経営しているレストランで食事をしてもらい、箸の使い方など、食事のマナーを教えるとともに、伝承料理の素晴らしさを伝えたいと思います。
子ども向けだけでなく、介護食アドバイザーの認定を受けているので、介護食等をテーマにした食育活動を行っていきたいです。
また、後継者育成のため、砺波市の食生活改善推進協議会において推進員への指導・助言を続けていきます。
石川県料理学校協会主催「~地産地消・ガンバレじわもん食材~世界に飛立つ新感覚SUSHIコンテスト
(令和5年11月12日)」(石川県金沢市)
 |
| 協会会長(代理)挨拶 |
 |
| 森下消費・安全部長挨拶 |
 |
| 実食による審査 |
令和5年11月12日、石川県料理学校協会(以下「協会」という。)が主催する地元食材を使った料理コンテストが金沢市内の料理学校で開催されました。コンテストでは、1次審査で選ばれた10組が自身で考案した作品を作り、料理の腕を競いました。
北陸農政局からは、森下消費・安全部長が審査員として出席しました。
【コンテストの概要】
協会では、食生活の向上と家庭料理の教育普及のため、毎年地元食材を使った料理コンテストを実施しており、令和6年度は、「~地産地消・ガンバレじわもん食材~世界に飛立つ新感覚SUSHIコンテスト」と題して、新たなすし料理をテーマに実施しました。
令和5年8月1日(火曜日)から令和5年10月7日(土曜日)までの応募期間に、協会会員校やその他の料理教室の生徒、石川県内の生徒・学生などから多くの応募があり、中には中学生の応募もありました。
コンテストでは、10組がそれぞれ考案したレシピに基づき調理を開始し、1時間後には、それぞれの作品ができあがりました。
調理を終えた参加者は、完成した作品を写真に撮ったり、試食して、出来栄えを話し合っていました。
【審査結果】
審査は、北陸農政局、石川県栄養士会、協会の3名の審査員により行われ、作品の出来栄えだけでなく、独創性、地元食材の使用割合、手際の良さなどについて、審査を行い、最優秀賞1点、優秀賞2点を決定しました。
最優秀賞に選ばれたのは、「石川の食材を使った手毬寿司、押し寿司」を作った小西さん、平野さん(鵬学園高等学校)。「見た目や食材の組み合わせ方、食感などが被らないようにした」とのPRポイントのとおり、審査員からは「地産食材と組み合わせられた寿司飯と味のバランスがよく、発想に優れている。細やかな調理技術、丁寧な盛り付けが華のある作品にまとめられている」と評価されました。
優秀賞には、「丸芋とろろのドーナツ寿司」を作った浜田さん、藏谷さん(石川県立野々市明倫高等学校)と、「甘エビのおすしの天ぷら」を作った蔵岡さん(金沢製菓調理専門学校)が選ばれました。
「丸芋とろろのドーナツ寿司」は、大きなドーナツ型の寿司飯に丸芋のとろろが入り、刺身や大葉、ニンジンなどで飾り付けてあり、華やかな印象でした。
また、「甘エビのおすしの天ぷら」は、下味をつけた甘エビを寿司飯と寿司用昆布で巻いたものと、型抜きした寿司飯に加賀レンコン、甘エビをのせたものに衣をつけて揚げた2種類の天ぷらでした。
なお、今回の2次審査に選ばれた方々には、審査員がプレゼンターとなって賞状と記念品が贈られました。
 最優秀賞
最優秀賞「石川の食材を使った手毬寿司、押し寿司」
 優秀賞
優秀賞「丸芋とろろのドーナツ寿司」
 優秀賞
優秀賞「甘エビのおすしの天ぷら」
 賞状、記念品の贈呈
賞状、記念品の贈呈(公社)ふくい・くらしの研究所(福井県福井市)
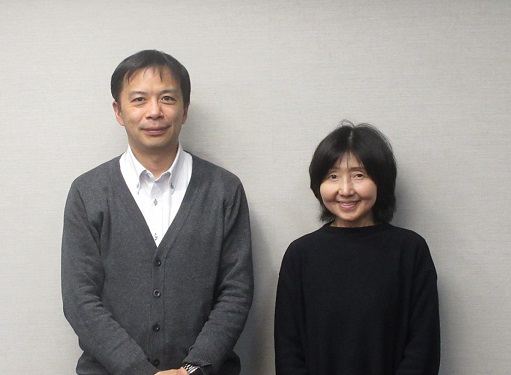 |
| 高井氏(左)と亀谷氏(右) |
 |
| 消費生活講座(福井県委託事業) |
 |
| SDGsセミナー(鯖江市委託事業) |
 |
| 男の料理教室 |
令和5年12月14日、福井県福井市で活発に食育活動等に取り組んでいる、「ふくい・くらしの研究所」の高井(たかい)氏と亀谷(かめたに)氏にお話を伺いました。
「ふくい・くらしの研究所」は、「食」「環境」「福祉」「物価」「文化」など幅広い『くらし』をテーマに、県民に役立つための具体的な活動を実践する目的で、平成7年に設立されました。
平成19年、身近なくらしのナビゲーターを目指し、県民のみなさまに知っていただけるように愛称を「くらなび」としました。
平成23年には、福井県から公益社団法人として移行認定を受け、より一層公益性による組織の信頼を高める取組を行っています。
【「ふくい・くらしの研究所」の取組内容を教えてください】
公益社団法人として、消費者に対する啓発活動や消費者トラブルの防止等を中心に、大きく分けて次の三つの柱を持って活動しています。
1.消費者の自立支援
消費者市民社会でのSDGsの実現ということで、消費者力の向上を目的にした消費者講座や、地域でのリーダーづくりを目的とした講義を開催しています。
主には福井県から委託を受けている「消費生活講座」を実施しています。福井県以外では、鯖江市から講座の委託を受けています。
また、消費者が選択して行動するエシカル消費の取組や、国連が定めた2030年の開発目標「SDGs」の県民への理解促進や普及を行っています。
2.家族のくらし支援、地域のくらし貢献
福井県における地域に合った暮らし方の提案ということで、食生活に関する学習会、食の悩みや不安に対する相談など、独自の講座を開催しています。
特に、子育て層向けの「食育講座」や男性の食の自立と社会参加づくりを目的にした「男の料理教室」を実施しています。
3.くらしにかかわる役立つ情報提供
平成15年度から、県民のくらし向きに関するマインド調査を、春、秋の年2回実施しています。最近では、物価高に関する調査やコロナ禍での暮らし方に関する調査などを実施し、県民の生活実感や消費マインドの変化を分析・発表しています。
また、情報誌「くらなび」を年2回発行するとともに、「くらなび」ホームページでは、各講座の募集案内や講座内容の報告、活動内容や調査報告などをわかりやすくタイムリーに掲載して、消費者に役立つ情報を発信しています。
【工夫している点や苦労している点を教えてください】
工夫している点は、食育講座では、あまり専門的になりすぎないように、初めての方でもある程度わかるようなものにしていたり、一般の県民の方が理解できる内容で講師にリクエストしたりして講座を組み立てています。
また、料理教室のメニューについては、事前に準備せず、その日に買物に行って食材を選び、できるだけ地元の美味しいものを使用したメニューにするようにしています。
苦労している点は、最近の物価高で材料費も高騰してきており、参加費だけでは赤字となってきている点です。無料の料理教室へ人が流れていることもあり、値上げもしにくく、運営するのが大変になってきています。
【今後の活動予定について教えてください】
消費者市民としての新しい価値観による「よりよいくらし」を選択し行動できる消費者リーダーを育成し、地域で学びあい、教えあう場を増やします。
また、「消費者が一人ひとりの価値観を持ってくらせる、福井らしい地域社会の実現へのお役立ち」を理念として、行政や地域の諸団体・グループ、専門家と連携し、新しい生活様式に対応しながら、ふくい・くらしの研究所の情報提供力を強化し、『くらしのコーディネーター』としての役割を担い、地域に必要とされる存在になりたいと考えています。
燕市児童研修館「こどもの森」、「サークルきらら」(新潟県燕市)
 |
| 神保一江館長 |
令和5年12月7日、新潟県燕市で活発に食育活動に取り組んでいる、児童研修館「こどもの森」館長の神保一江(じんぼ かずえ)氏にお話を伺いました。
神保氏は、新潟県燕市社会教育委員として、家庭教育支援チーム「サークルきらら」においても家庭教育活動を行っています。
【燕市児童研修館「こどもの森」の取組】
「こどもの森」は、さまざまな体験活動を通じて、子どもたちの豊かな感性を育むことを目的とする施設です。専門の指導員のもとで、いろいろな体験学習ができるほか、子育て中の大人向けの講座なども開催しています。
現在行っている主な活動として、野菜の栽培、収穫を体験し、採れたての野菜を調理して味わう体験活動「もりもり食堂」を毎月1回実施しています。参加した親からは、「自分で植えて育てた野菜を、子どもがすごく喜んでもりもり食べる姿に驚いた」等の感想が寄せられ、神保氏は、「とてもやりがいを感じることができた」とお話されました。
そのほかにも、地域の方を講師に、梅干しや味噌、切り干し大根作りなど伝統食を伝える活動にも挑戦。調理以外にも、さつまいものつるを使ったリース作りで環境を意識したり、読書活動につなげたりするなど様々な観点で活動を展開。近年は、防災や食物アレルギーにも視野を広げています。
令和5年6月の食育月間(6月1日~30日)では、絵本や工作、館内探索などを楽しみながら「食」への関心を深める【おはなしand「食育」】を開催。期間中、大人323人、子ども383人が参加しました。
また、6月17日~18日には、「ぼうさい」をテーマにクイズやお買物ごっこなどで、遊びながら「食」について学ぶ【チャレンジ!食育】を開催。2日間で、大人196人、子ども177人が参加しました。
 さつまいもの収穫
さつまいもの収穫 さつまいもの調理
さつまいもの調理 料理を味わう親子
料理を味わう親子 おはなし and 「食育」
おはなし and 「食育」 チャレンジ!食育(クイズ)
チャレンジ!食育(クイズ) チャレンジ!食育(お買物ごっこ)
チャレンジ!食育(お買物ごっこ)【「サークルきらら」の取組(らんらんランチ会)】
「サークルきらら」は、神保氏が子育て中に、友人たちと地区の集会所を借りて子育てについて悩みを話し合う場を設けたのがはじまりです。「サークルきらら」のメンバーには、保育士、管理栄養士、燕市食生活改善推進委員など、子育てと食の知識や経験が豊富な方々がおり、そこで食事を作って食べながら、家庭教育を学ぶ会を始めることとしました。
平成29年からは、ただ単に「家庭教育の勉強会」ではなく、楽しんで学んでもらうために、メンバーの専門性も生かしながら、燕市教育委員会と共催で「らんらんランチ会~食育活動から展開する家庭教育講座~」をスタートさせました。
令和5年度も、絵本に出てくる食べ物を親子で作って食べる「らんらんランチ会」を年5回実施しています。「社会教育の観点から、子どもたちの読書活動の推進にも寄与できたら」と神保氏は考えています。
 「ごはん」の絵本で学ぶ
「ごはん」の絵本で学ぶ 炊き込みごはんの調理
炊き込みごはんの調理 親子で会食
親子で会食【工夫している点や苦労している点を教えてください】
工夫している点は、活動の継続が、調理・食堂への参加者増につながることが分かったため、単発の活動で終わらせないことです。例えばさつまいもを育てることでは、苗植え、収穫、調理、クリスマスリース作り、絵本の掲示など多角的に活動を展開させ、年間を通じて食への関心が途切れないようにしています。
また、食生活改善推進委員や、つばめアレルギーっ子クラブ、市の防災課の職員などの専門家と若い母親たちが話す場を設け、「こどもの森」の職員では伝えることのできない食に関する知識を高める工夫をしたり、更生保護女性会など地域で子育てに関わっている方とのつながりが持てるような講座も実施し、食を通じたコミュニケーションを充実させています。
苦労している点は、食べ物を扱うので、食中毒や衛生管理、食物アレルギーには気をつけなければいけないことや、献立を考えること、スタッフの人数が足りないこと、参加者を集めることなどです。
【今後の活動予定について教えてください】
「こどもの森」については、来年度(令和6年度)、野外でアウトドアクッキングを行うなど、「おでかけこどもの森」みたいな活動をしてみたいと考えています。
燕市で子育てをしている母親の多くは、子どもが1歳になると働きに出てしまいます。1歳未満でも、4月には入園する子どもがとても多い地域で、生後半年が勝負です!それまでに家庭教育の大切さを伝え、子育ての喜びを感じてもらいたいという気持ちで活動を続けていこうと思います。お料理をするという楽しさの中で、ほんの一言でも心に残るフレーズを伝えていきたいです。それだけではなく、「らんらんランチ会」を通して、若いお母さん方に、地域に頼れる大人がいることを知ってもらいたいという思いもあります。
地域の宝物である子どもたちの未来が、キラキラと輝く世界であるために私たちにできることを考え、常に新しい情報にアンテナを張り、私自身もスキルアップしていかなければならないと思います。一生続く「食べる」ということが楽しみにつながるように、親子の絆が深まるように、子育てが楽しい地域になるように、活動していきます。
山内かぶらちゃんの会「伝統野菜山内かぶら収穫祭(令和5年11月21日)」(福井県若狭町)
 |
| 山内かぶらちゃんの会 |
 |
| 鳥羽小学校の収穫体験 |
 |
| かぶらを洗う児童 |
 |
| 山内かぶらの唄を斉唱する児童 |
令和5年11月21日、福井県若狭町で「伝統野菜山内かぶら収穫祭」が開催されました。収穫祭には若狭町立鳥羽小学校の3年生24名も参加し、秋晴れの下、山内かぶらを収穫しました。
【山内かぶらとは?】
平成28年に「地理的表示(GI)保護制度」※1を取得した山内かぶらは、古くから若狭町山内で栽培されてきた在来品種です。煮ても煮崩れせず、漬物にするとパリッとした歯ごたえが楽しめます。
※1 地理的表示(GI)保護制度:地域で長年育まれ、その農林水産物等の名称から産地が分かり、品質や社会的評価などがその産地と結びついていることが特定できる名称を知的財産として保護する制度です。山内かぶらを含む北陸農政局管内の事例については、こちら
【山内かぶらちゃんの会】
「山内かぶらちゃんの会」は、現在、12名で活動しており、地域で栽培されてきた伝統野菜「山内かぶら」の生産・継承に取り組んできました。※2
あわせて、食育活動にも取り組んでおり、例年、地元の鳥羽小学校の3年生を招いて、種まきや収穫体験等を実施しています。
※2「山内かぶらちゃんの会」の会員が運営する「合同会社山内かぶらちゃんの会」は、農林水産省及び内閣官房の「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第10回選定)にビジネス・イノベーション部門で選ばれました。詳細は、こちら
収穫祭の開催にあたって、「山内かぶらちゃんの会」代表の飛永悦子(とびなが えつこ)氏からは、「今年、新たに男性が1名入会した。引き続き、山内の人達に声を掛けて山内かぶらの種をつないでいきたい」、等と挨拶がありました。
【いざ、収穫!】
収穫作業が始まってしばらくすると、次々と子どもたちの歓声が上がりました。収穫の感想を聞くと、「抜こうとしてもなかなか抜けなくて、重かった」とのこと。収穫したかぶらをひとつ持たせてもらうと、土がついて見た目以上にずっしりしていました。
収穫後、子どもたちは「山内かぶらちゃんの会」の会員に教わりながら、自分で収穫したかぶらを丁寧に洗い、ひとつひとつタグをつけて袋詰めしていきました。
山内かぶらには、窪みとヒゲ根が多いという特徴があります。子どもたちがタワシを使って丁寧に土を洗い、大切に袋詰めしている様子が印象的でした。収穫作業後は、山内かぶらの試食会があり、小学生は山内かぶらを使った餃子やコロッケを楽しみました。
試食会後、子どもたちは山内かぶらの唄を斉唱し、地域の宝である山内かぶらの大切さについて学びを深めた様子でした。
取材をしていると、児童の一人が、「山内かぶらはここ(山内)でしかできないかぶらだ」と嬉しそうに教えてくれました。子どもたちにとって、農を通して地域の伝統や食を学ぶ、貴重な経験になったのではないでしょうか。
お問合せ先
消費・安全部 消費生活課
担当者:「食育ネットほくりく」事務局
ダイヤルイン:076-232-4227




