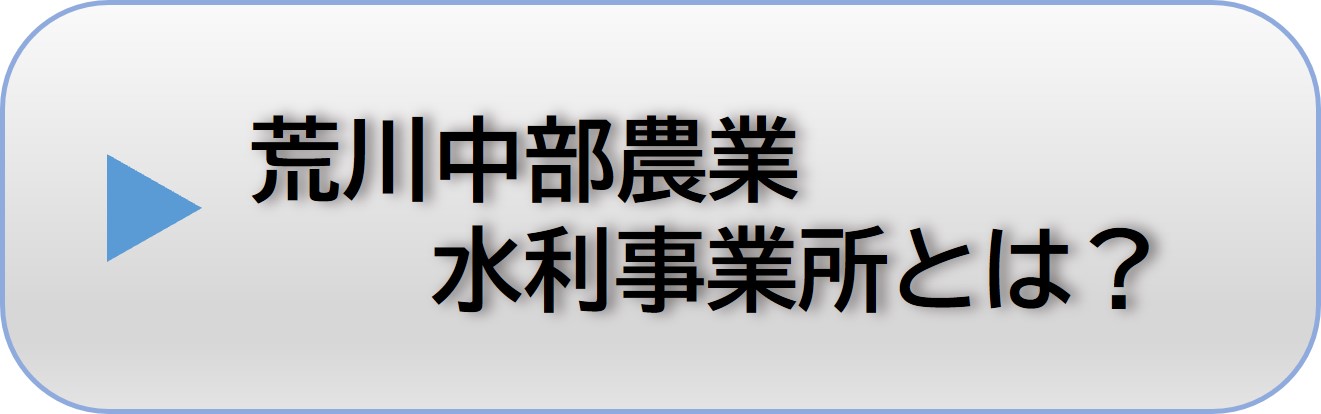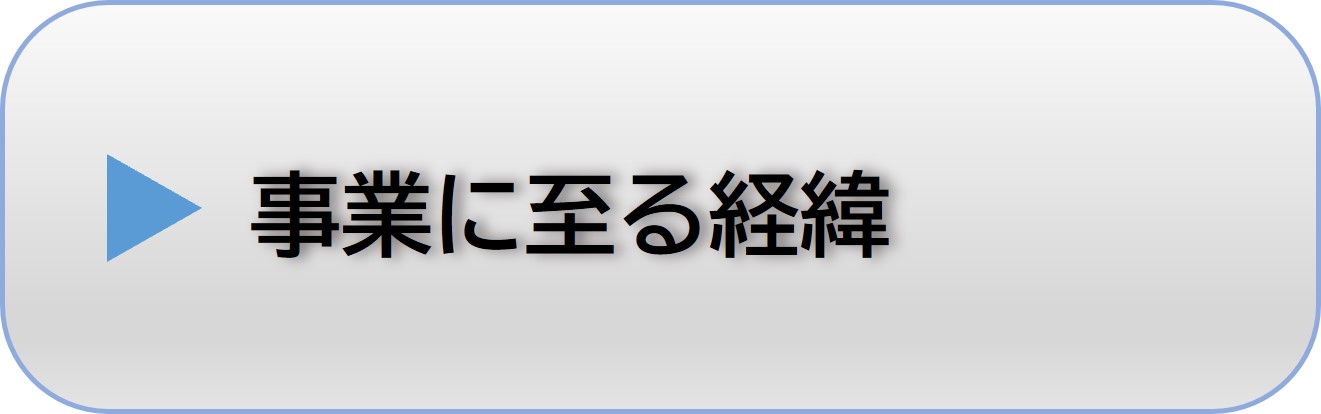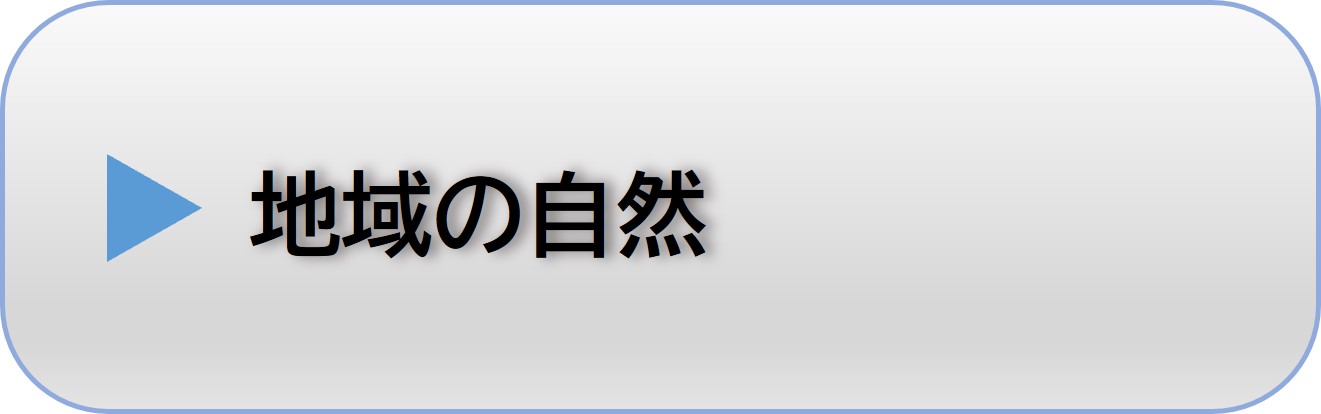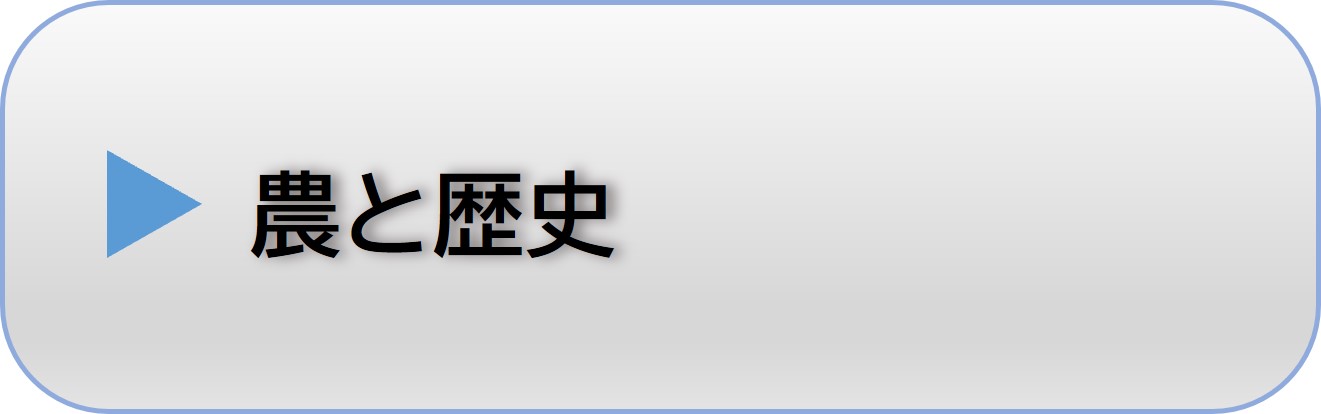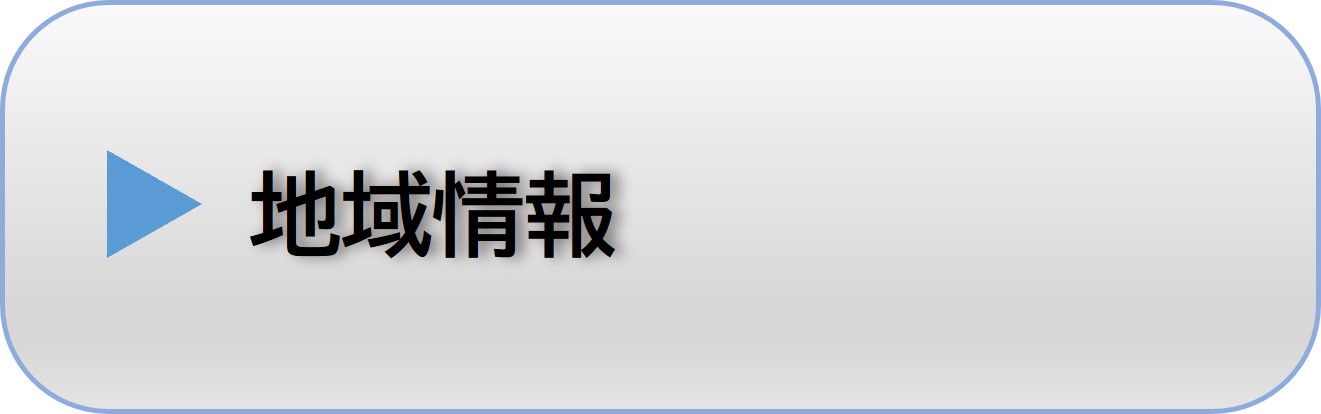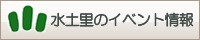❷ 事業に至る経緯
2. 荒川中部農業水利事業(前歴事業)の概要
昭和34年度から昭和41年度において前歴事業の荒川中部農業水利事業が実施されました。
前歴事業は、荒川総合開発の一環として、荒川中流部沿岸に展開する熊谷市外2市8町村の洪積台地の畑地及び沖積地帯の水田の水利開発(8,600ha)を目的として実施されました。
本地域の用水源である荒川は、洪水量に比して渇水量は極めて少なく、このため、本川を水源としてかんがいしている区域は主として六堰(大里用水)の約3,500haに過ぎず、同用水も植付期の遅延等や用水等の不足にしばしば悩まされていました。
これと隣接する元荒川上流地域は星川、忍川の自然湧水を利用していましたが、荒川の河床低下と都市側の地下水利用の急激な増加により逐次その利用が困難となってきました。
また、櫛挽、本畠の洪積台地の畑地帯は水利施設がなく、降雨量のみに依存している状況でした。
本事業は、これら地域の対策として水源の確保と水利施設の改修、新設を行うもので、水源の確保については二瀬ダムを利用し、大里、元荒川上流地区約4,400haに対しては既設六堰頭首工より最大約16.5m3/s取水し、幹線水路、約8,200mにわたって水路舗装の改修を行い、用水の不足解消を図るものでした。
また、本荒川中部地区に当たる櫛挽地区約3,800haに対しては、寄居町地先に農業、発電共用の玉淀ダムを新設して最大約9.1m3/sを取水し、導水幹線水路約16,600mを新設して用水の導入を行い、畑地の開発を図るものでした。
なお、荒川右岸台地の本畠地区約400haは県営事業として施行されました。
受益面積及び地積 : 8,603 ha
| 新 規 水 利 用 地 域 | 用 水 補 給 地 域 | ||
| 櫛挽地区 | 3,829 | 大里地区 | 3,472 |
| 本畠地区 | 396 | 元荒川地区 | 906 |
| 計 | 4,225 | 計 | 4,378 |
本事業で、大里、元荒川地域の既成水田の用水不足の解消と、櫛挽、本畠台地の畑地帯への新たな導水を目的に、二瀬ダムを水源として、荒川から取水する玉淀ダム掛(櫛挽地区約3,800ha)及び六堰頭首工掛(大里・元荒川・本畠地区約4,800ha)を対象として整備が行われました。
その後、平成6年~18年度の期間において、六堰頭首工等の施設の老朽化等から、六堰頭首工掛である大里・元荒川・本畠地区約3,800haについて、国営農地防災事業「大里地区」により整備が行われました。
櫛挽地区約3,800haは、受益面積の変動等により3,212haとして現在の荒川中部農業水利事業が行われています。
(当初の計画水利権9.11m3/sは、開田抑制政策により畑地かんがいを中心とした事業に転換し、5.375m3/sに変更されました。(平成11年))
荒川中部農業水利事業(昭和30年代に行われた前歴事業)の概要図

事業地区情報一覧/事業概要一覧
お問合せ先
荒川中部農業水利事業所ダイヤルイン:048-585-4600