3.水戸藩の開発
備前堀の開削
那珂川沿岸の開発が大きく進んだのは、江戸幕府によって天下が定まり、水戸に城下町が築かれた近世以降のことです。家康は、水戸城主に実子を置き、水戸藩は御三家として重要な立場を与えられました。以後、水戸藩の手により、那珂川沿岸では、現在の原型を形作るような大規模な開発が進んでいきます。
1610年には、那珂川の豊かな水を引き、右岸の低地を潤す大用水「備前堀(びぜんぼり)」の開削が行われました。工事の指揮を行ったのは、関東郡代・伊奈備前守忠次(いなびぜんのかみただつぐ)、幕府直轄の技術者として、関東平野の治水や新田開発に携わったことで名高い人物です。かつては、東京湾へと注ぎ込んでいた利根川を現在の流れへと変えたのも、伊奈一族の行った事業の一つです。その技術は「関東流(伊奈流)」と呼ばれ、今日の関東平野の原型を築き上げたと言っても過言でもありません。
工事が完成し、見事、延長12kmにもおよぶ水路が引かれると、21か村、約1,000haにもおよぶ農地に水が行き渡りました。その功績を称え、用水路には、彼の名を取った「備前堀」の名が付けられました。備前堀には、千波湖(せんばこ)の氾濫による水戸城下の水害を防ぐ効果もあり、城下町の整備にも大きく役立ったといえます。
驚くべきことに、この水路は、その後、明治、大正、昭和、平成と、改修を続けながらも受け継がれ、現在も農業用水路として重要な役割を果たしています。伊奈氏の技術の秀逸さを目の当たりにするようです。
疏水百選(平成18年)の一つに選ばれている備前堀の風景
疏水名鑑ホームページへ
小場江用水の開発
一方、那珂川左岸でも、初代藩主・徳川頼房(よりふさ)のもと、1656年、かんがいのための堰と用水路整備に力が注がれました。
那珂川の左岸には、低地より一段高い土地が階段のように連なる河岸段丘が広がっており、川から水を引くのが困難でした。そこで、上流から水路を掘り、左岸一帯を潤す大用水、小場江(おばえ)用水の開発が計画されます。事業を命じられたのは、諸国の金山や鉱山の開発に携わっていた永田茂右衛門(ながたもえもん)・勘衛門(かんえもん)父子です。彼らは、沿岸一帯の流水量や土地の高低差を詳細に調査し、計画を立てました。その結果、現在の那珂市にあたる下江戸(しもえど)に堰が築かれ、20か村にもおよぶ村々を 潤す大用水が完成しました。1798年には、水路はひたちなか市の三反田までの約28kmまで伸ばされ、 24か村、7,700石の農地を支えるまでになりました。
この他にも、永田茂右衛門父子は、久慈川(くじがわ)筋の辰ノ口堰(たつのくちぜき)や岩崎堰(いわさきせき)、水戸城下の上水道であった笠原水道(かさはらすいどう)など、領内の治水・利水事業に数々の功績を残しています。1694年には、名君で知られる二代目藩主・徳川光圀から、勘衛門に対し、「円水」の称号が送られています。
備前堀と同じように、この小場江用水路も、現在も利用されており、農業を行う上で欠かせない役割を果たしています。このように、那珂川の沿岸の農地を潤すかんがい施設は、水戸を中心とした水利開発に力が注がれた江戸時代に、大きく発展しました。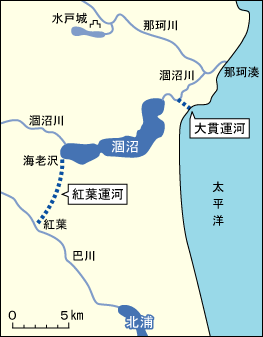
近世水戸藩の水利事業 備前堀と小場江用水
| さらに詳しく |
お問合せ先
那珂川沿岸農業水利事業所
〒310-0002 茨城県水戸市中河内町960-1
電話番号:029(227)7571


















