+a さらに詳しく 運河の開削と宝永の一揆
1690年、徳川綱篠(つなえだ)が三代藩主になったころから、水戸藩では、著しい財政難に悩まされました。水戸藩の藩主は参勤交代がなく、江戸に常駐しなければならなかったため、江戸と水戸で二重の支出があったことや、二代藩主・光圀(みつくに)の時代に『大日本史(だいにほんし)』の編纂のため、全国から多数の学者を集めたことによって人件費が増大したことなど、財政難の要因には、様々な理由があったようです。
1706年、藩は財政建て直しのため、各地の藩で財政改革に関わったことで知られる松浪勘十郎(まつなみかんじゅうろう)を登用しました。松波は、役人を削減し、諸経費の節約を図り、年貢を増やして財政収入を確保するなど、積極的な改革を推し進めます。この一連の改革は宝永の改革と呼ばれますが、その中心となったものに運河の掘削事業がありました。
当時、水戸と江戸とを結ぶ内陸水路として、那珂川―涸沼川(ひぬまがわ)―涸沼(ひぬま)―北浦(霞ヶ浦)―利根川と続く運送路が利用されていましたが、このルートには、涸沼と北浦の間で陸上輸送を行わなければならないという難点がありました。この間に運河を掘削することで、利用を増大させ、税の増収や経済の発展を図るというのが松波の考えでした。
この運河は紅葉(もみじ)運河と名づけられ、1704年7月から開削工事が着工され、四ヵ月後の11月には完了しますが、大部分が砂地という地質からすぐに土砂で埋まってしまい、翌年から絶えず修復工事に追われることになります。また、同時に涸沼川を太平洋へとつなぐ大貫(おおぬき)運河の開削工事も行われましたが、こちらもすぐに砂で埋まってしまい、運行ができなくなってしまいました。
この二つの運河の工事は、領内の農民を動員して行われましたが、労働は過酷で、負担を強制させられた農民の数は、延べ130万人に達したといいます。また、賃金もほとんど支払われなかったことから、農民たちは田畑を耕すことができなかった上に、収入もなくなり、さらには、工事に使われた材料費や用具代まで自分たちで払わなければならないといった悲惨なありさまでした。
1708年から宝永の一揆と呼ばれる農民たちの大規模な一揆が起こり、ついには、松波勘十郎は、改革の責任をとり、水戸の赤沼(あかぬま)の牢獄に入れられ、獄死したといいます。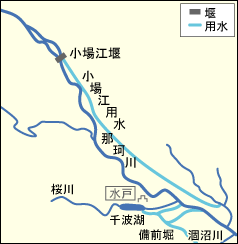
紅葉運河と大貫運河

1. 農耕の始まり 2. 中世の農 3. 水戸藩の開発 4. 近代農業の発展
お問合せ先
那珂川沿岸農業水利事業所
〒310-0002 茨城県水戸市中河内町960-1
電話番号:029(227)7571

















