+a さらに詳しく 干拓事業の実施
大正から昭和の時代には、食糧増産のため、千波湖(せんばこ)や涸沼(ひぬま)などの湖沼で干拓事業が盛んに行われました。
水戸の城下の南側を占めていた千波湖は、江戸時代には、約129haありましたが、大正10年から昭和7年までに行われた干拓事業によって、現在では、三分の一ほどの大きさになっています。これらの干拓によって、備前堀(びぜんぼり)を使い、千波湖(桜川)から取水していた千波湖土地改良区は、干拓によって不足する水を那珂川からの取水に振り替えています。
また、下流の涸沼の辺りでも、江戸時代から干拓事業が行われており、現在、周辺に広がる水田地帯は、昭和43年まで行われた大規模な干拓によって生み出されたものです。
こうして新たな農地の開発が進んでいくにつれ、必要とされる水の量も増し、さらなる水利開発が求められるようになっていきます。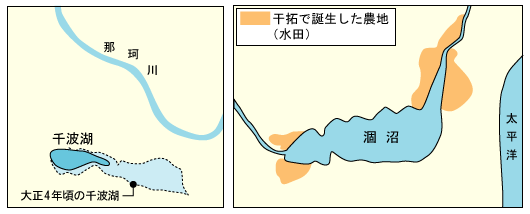
千波湖と涸沼の変遷
お問合せ先
那珂川沿岸農業水利事業所
〒310-0002 茨城県水戸市中河内町960-1
電話番号:029(227)7571


















