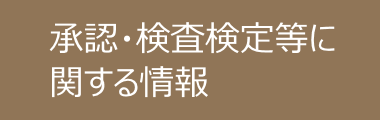愛玩動物薬剤耐性(AMR)調査に関するワーキンググループの検討結果の概要
|
薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2016-2020)(国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議(平成28年4月5日))の取組目標の達成のため、「愛玩動物における薬剤耐性に関する動向調査」を行うにあたり、対象動物、対象菌種、調査対象薬剤等に関する有識者の意見を聴くために、平成28年9月に「愛玩動物薬剤耐性(AMR)調査に関するワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を動物医薬品検査所に設置しました。 |
愛玩動物薬剤耐性(AMR)調査に関するワーキンググループの検討結果の概要
実施日時:
平成28年12月8日(第一回会合)14時00分~16時00分
平成29年1月25日(第二回会合)13時30分~16時30分
平成29年3月30日(第三回会合)13時30分~16時30分
委員:田村 豊委員(座長;酪農学園大学 教授)、石丸 雅敏委員(日本動物用医薬品協会 参与)、大木 麻生委員(富士フイルムモノリス株式会社)、境 政人委員(日本獣医師会 専務理事)、原田 和記委員(鳥取大学 准教授)、村田 佳輝委員(むらた動物病院 院長)
1. 調査対象動物
イヌ及びネコ
2. 調査対象薬剤
(1)グラム陰性菌;現在のJVARM対象薬剤(アンピシリン、セファゾリン、セフォタキシム、ストレプトマイシン、カナマイシン、ゲンタマイシン、テトラサイクリン、クロラムフェニコール、コリスチン、ナリジクス酸、シプロフロキサシン、スルファメトキサゾール+トリメトプリム)に、セファレキシン、イミペネムまたはメロペネムを追加する。
(2)グラム陽性菌;現在のJVARM対象薬剤(アンピシリン、ストレプトマイシン、ゲンタマイシン、エリスロマイシン、テトラサイクリン、クロラムフェニコール、ナリジクス酸、シプロフロキサシン)に、セファレキシン、セフメタゾール、アジスロマイシン又はクラリスロマイシンを追加する。
3. 薬剤感受性試験方法
微量液体希釈法
4. サンプリング地域
可能な限り全国から偏りなく収集する。
5. サンプリング方法
(1)病気動物由来株
1)サンプリングスキーム
ア モニタリング体制としては、原則として、動物専門の検査機関を通じて、次項の対象菌株を収集することが適当と考えられる。なお、原則として1株/菌種/病院としてサンプリングする。
イ 収集された菌株については、追加解析のために保存する。
2)菌種・採材部位・株数・実施頻度
| 優先順位 | 菌種 | 採材部位 | 菌株数/年 | ||
| イヌ | ネコ | ||||
| グラム陰性菌 | (1) (2) (3) (4) (4)(4) |
Escherichia coli Klebsiella属菌 Enterobacter属菌 Pseudomonas aeruginosa Proteus mirabilis Acinetobacter属菌* |
尿・生殖器 尿・生殖器 尿 尿・耳 尿・耳 尿・皮膚 |
100 100 100 100 100 50 |
100 100 100 100 100 50 |
| グラム陽性菌 | (1) (2) |
コアグラーゼ陽性Staphylococcus属菌 (S. aureus, S. pseudintermedius 他) Enterococcus属菌 (E. faecalis, E. faecium 他) |
尿・皮膚 尿・耳 |
100 100 |
100 100 |
*Acinetobacter属菌は、分離頻度が低く、菌株が集まらない可能性があることから、各々、50株を目標とする。
サンプリングの対象菌種について、調査対象菌種の優先順位の高いEscherichia coli、コアグラーゼ陽性Staphylococcus属菌、Klebsiella属菌、Enterococcus属菌は毎年対象とし、優先順位の低いEnterobacter属菌、Pseudomonas aeruginosa、Proteus mirabilis、Acinetobacter属菌については、ローテーションを組んで隔年又は数年ごとに実施する。
(2)健康動物由来株
1) サンプリングスキーム
ア モニタリング対象は、家庭で飼育されている健康なイヌ及びネコとし、ワクチン接種等の際に直腸スワブ等を採取して菌分離を行う。
イ サンプル収集の際には、飼い主から、口頭又は書面によるインフォームドコンセント(同意書)を得ることが必要と考えられる。
ウ 収集された菌株については、追加解析のために保存する。
2) 菌種・採材部位・株数・実施頻度
Escherichia coli及び、可能であれば腸球菌(Enterococcus faecalis及びE. faecium)も含めて、直腸スワブサンプル等からそれぞれ各調査年100株以上を目標として1株/菌種/病院として収集する。調査の実施頻度は数年に1回程度とする。