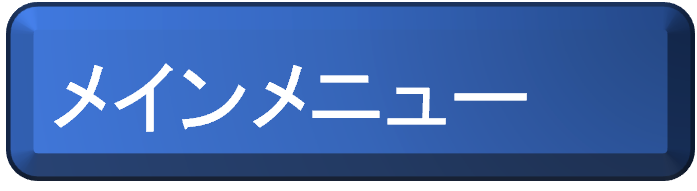地域の紹介

(岡島頭首工:揖斐川上流側から撮影)
|
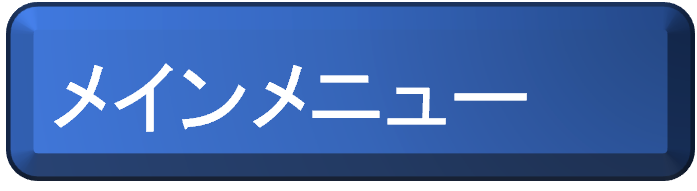

|

湧水
岐阜県西南部に位置する西濃地域は、大垣市、養老町、垂井町、神戸町、揖斐川町、大野町、池田町にまたがり、北に揖斐山地、西に伊吹山と養老山地を望み、東には肥沃な平野が広がります。
古くから岐阜県は「飛騨の山、美濃の水」という意味で「飛山濃水」の地と呼ばれてきましたが、この地域でも木曽三川のひとつである揖斐川の他、相川、牧田川、杭瀬川、粕川、桂川など多くの河川が流れ、豊かな自然景観を生み出しています。
また、この地域には日本でも有数の自噴帯(じふんたい。自噴とは地下水が自然に湧き出てくること)があり、豊富で良質な地下水を利用するための掘り抜き井戸と呼ばれる自噴の井戸が作られ、地域の中心である大垣市は、市内の各所で湧水が見られるなど、水にかかわる歴史遺産や文化を活かした町作りが認められ、平成7年に「水の郷」として認定されました。
地域北部の自噴帯となる揖斐川沿岸の神戸町、西部の相川沿岸の垂井町、養老山地の急崖にできた扇状地の末端部では、伏流水が湧き出る「河間(がま)」と呼ばれる湧泉や湧水池があり、古くから農業用水や生活用水として利用されてきました。
|

湧水池(大垣市曽根城公園内)
|

掘り抜き井戸発祥地(大垣市)
|
輪中
水の恵みを受ける一方、この地域の歴史は、洪水との闘いとは切っても切り離せない関係にあります。
木曽三川が合流する本地域では、古くから洪水被害に悩まされ、人々は洪水から農地や集落を守るために、周囲に堤防を巡らせた「輪中(わじゅう)」を作ってきました。
また、輪中の中にある集落では、高く石積みした土地の上に母屋を建て、さらにそれよりも高い場所に土蔵などを設けて家財や食料、洪水の際に避難するために用いる舟(上げ舟)などを保管した水屋を建て、非常時に備えました。
また、輪中の南部の低い地域では排水が悪く、収穫に悪影響が出るため、土地の一部を掘って別の場所に積み上げ、そこで稲作を行う「堀田(ほりた)」が作られ、掘った場所は「掘りつぶれ」と呼ばれる水路として、収穫した作物を運ぶために利用していました。
このように、洪水から生活を守るための人々の智恵が西濃地域独特の地域社会を生み出すことになりました。
|

大垣市に残る水屋
|

掘りつぶれを行く田舟
大垣市輪中館『輪中』より
(河合孝氏 撮影)
|
|

堀田と伊吹山
大垣市輪中館『輪中』より
(河合孝氏 撮影)
|
|

発展の石礎
西濃地域は、東海地方最大級の前方後円墳である昼飯大塚古墳や6基の前方後円墳を始め様々な墳墓が集まる野古墳群など、数多くの古墳が作られました。
また、全国の鉱山、金属業の総本宮として親しまれている、鉱山の神として信仰される金山彦を主祭神とする南宮大社は、崇神天皇の時代に奉還されたと伝えられ、以来美濃国一宮として多くの崇敬をうけてきました。
奈良時代になると、聖武天皇の勅願により現在でも唯一寺跡全体が現存する美濃国分寺が建立され、中世には東大寺領大井荘をはじめとする多くの荘園が成立しました。
これらのことから、古代からこの地域が栄えていたことが分かります。
また、日本のほぼ中央に位置する地域であるため、律令国家時代には畿内と国府を結び、鎌倉時代には鎌倉と京を結ぶ交通の要衝でした。
|

昼飯大塚古墳(大垣市)
写真は大垣市教育委員会提供
|

南宮大社(垂井町)
写真は垂井町から提供
|
東西交流の一大拠点
江戸時代になると、江戸と京を結ぶ重要幹線として整備された中山道の宿場として発展し、中でも中山道六十九次の56番目の宿場である赤坂宿は、杭瀬川を利用した船運の拠点でもあり、将軍が京へ向かうための宿泊地としてお茶屋屋敷が設けられるなど、大いに栄えました。
また、大垣市は大垣藩十万石の城下町であり、中山道と東海道を結ぶ美濃路の宿場町としても栄え、大垣城の外堀であった水門川から揖斐川を経て、桑名、伊勢、三河と結ぶ船運が開かれるや、水運で大いに繁栄しました。
|

赤坂宿(大垣市)
写真は大垣市観光協会HPから抜粋
|

全国で唯一残る将軍の休泊施設、お茶屋屋敷跡
写真は大垣市観光協会HPから抜粋
|

米(れんげのかおり(ハツシモ))

岐阜県の県花でもあるれんげの名前が付いたお米が「れんげのかおり」。
4~5月にれんげと一緒に田を耕し、土にれんげを鋤きこむことで生まれた栄養豊かな土壌が可能にする、化学肥料や農薬の利用を抑えた安全、安心なお米です。
|
柿(袋掛け富有柿、早秋、太秋)

岐阜県は全国有数の柿の生産地で、中でも渋みが全く残らない味で「甘柿の王様」とも称される、富有柿の発祥の地として有名です。中でも袋掛け富有柿は、9月頃に袋掛けして樹上で大事に完熟させ、市場に出荷されます。
|
いちご
(濃姫、美濃娘、とちおとめ)

昭和63年に品種改良で誕生した「濃姫」は、平均果重16グラムという大粒のいちご。
甘みと酸味の絶妙なバランスで、濃厚な味と香りが自慢です。
その濃い味と色から、岐阜県ゆかりの織田信長の正室濃姫に因んで名付けられました。
写真はJAにしみのから提供
|
|

美濃国分寺跡(大垣市)

金堂、講堂、回廊などの規模や配置が確認され、全寺域が完全に残されたものとして全国的に注目を集めている。(国指定史跡)
写真は大垣市HPから抜粋
|
奥の細道むすびの地・船町港跡(大垣市)

松尾芭蕉が奥の細道の旅を終えた地。ここ船町港跡は大垣城水運の拠点であった。(市指定史跡)
写真は大垣市から提供
|
赤坂港会館と川湊跡(大垣市)

大正時代まで水運交通の要衝として栄えたが、現在は跡地に隣接して広場が整備されている。(市指定史跡)
写真は大垣市から提供
|
中山道赤坂宿(大垣市)

中山道六十九次の江戸から数えて57番目の宿場町。本陣跡を整備した本陣公園や、赤坂湊の常夜塔などが残る。毎年11月上旬に、中山道赤坂宿まつりが開催される。
(地域的価値)
写真は大垣市から提供
|
南宮大社(垂井町)

旧国幣大社で、美濃一の宮として、また広く全国の金属業の総本社として、古くから厚く崇敬されている。濃尾の祖神が祭られている。(国指定文化財)
写真は垂井町から提供
|
南宮大社 御田植神事(垂井町)

美濃国一宮である南宮大社において、御田植祭が行われる。早乙女と呼ばれる少女21人が田植歌に合わせて、松葉を苗に見立てて植えつける神事である。(国指定重要無形民俗文化財)
写真は垂井町から提供
|
表佐太鼓踊り(垂井町)

江戸時代初期のころ、美濃中山(現南宮山)の水神様に雨乞いをし、願いが叶ったお礼に太鼓、鉦鼓を鳴らして感謝したのが起こりである。(県指定無形民俗文化財)
写真は垂井町観光協会HPから抜粋
|
美濃国府跡(垂井町)

大化改新(645年)によって全国に国府が作られ、美濃では府中地区一帯にあったといわれている。(県指定史跡)
垂井町観光協会HPから抜粋
|
マンボ(垂井町)

垂井扇状地には、「マンボ」と呼ばれる特殊な農業用水施設がある。マンボとは地下水を集めて導水する暗渠で、かつて、垂井では113本あったとされ、現在では洗い場や水田のかんがい用に利用されている。
(地域的価値)
写真は垂井町観光協会HPから抜粋
|
両界山横蔵寺(揖斐川町)

平安時代(801年)に伝教大師最澄が創建したと伝えられる寺。22体の国の重要文化財が安置され、多くの絵画、書籍を蔵していることから"美濃の正倉院"と呼ばれている。(国指定重要文化財)
揖斐川町役場HPから抜粋
|
野古墳群(大野町)

大野町内には、200基を超える古墳があちこちに点在していますが、その中でも野の集落西にある九基の前方後円墳と円墳は、国史跡になっている。(ぎふ水と緑の環境百選・国指定重要文化財)
写真は大野町から提供
|
昼飯大塚古墳(大垣市)

標高25mの牧野台地上に立地する東海地方最大級の前方後円墳である、築造は古墳時代前期末頃と考えられる。平成10年度に岐阜県の、平成12年度に国の史跡に指定されている。
写真は大垣市教育委員会提供
|
日吉神社(三重塔)(神戸町)

日吉神社は817年に伝教大師が創建した神社で、近江坂本の日吉大権現を主神として7柱の神が祀られている。
その境内にある三重塔は室町時代の建築様式を遺憾なく発揮した、神仏習合の名残を留める貴重なものである。
写真は神戸町から提供
|
神戸山王まつり(神戸町)

日吉新宮は平安時代のはじめ、最澄(伝教大師)が安八太夫安次の懇請に応じ、近江の国坂本の日吉大社の御霊を移し、お祀りしたことに始まると伝えられている。
郷土の人々のあつい信仰に支えられた日吉の祭りは、「神戸山王まつり」(県重要無形民俗文化財)と言われている。
神戸町役場HPから抜粋
|
笹山古墳(大野町)

大正2年(1913)の開墾によって滅失し、長らく円墳だと考えられていたが、平成22年(2010)に天理大学が実施した地中レーダー探査によって前方後方墳であることが判明した。令和2年に行った内容確認調査の結果、後方部にテラスが巡ること、出土遺物から築造時期が3世紀頃に遡ることが分かった。
写真は大野町から提供
|
願成寺西墳之越古墳群(池田町)

池田山麓の段丘上に100基以上の古墳が密集する、県下最大級の群集墳。主に6世紀から7世紀に造られた直径約8m~20mまで、大小様々な古墳が所狭しと盛り上がる眺めは、東海地方でも希な景観である。
(岐阜県指定史跡)
写真は池田町から提供
|
霞間ヶ渓(サクラ)(池田町)

ヤマザクラやエドヒガンなど日本固有種が群生する桜の名所。春の開花期には、山に桜色の霞がかかったように見える所から「霞間ヶ渓」の字が当てられるようになったと言われている。「国の名勝」と「天然記念物」の2種類の指定を受けている。
写真は池田町から提供
|
高田祭(養老町)

高田祭は、愛宕神社の火産霊神(カグツチ)を祀るもので、高田の町の防災、特に防火を祈願して、5月の第3週の週末に行われる。
祭りは、愛宕神社の祭神が高田の町をまわり(神幸の儀)、御旅所(神幸神社)にて休息、夜に愛宕神社へ還る(還幸の儀)という順番で進行します。また3輌の曳軕(県指定文化財)がこれに随行し、祭りに花を添える。
写真は養老町から提供
|
養老の滝(養老町)

養老の滝は、養老町のシンボルであり、「日本の滝百選」にも選定され、江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎も訪れ、滝の様子を浮世絵で描いている。標高約280mに位置し、高さ約30m、巾約4mあり、岩角をうってとうとうと流れ落ちる水は清冽を極め、砕け散る飛床は霧のように立ちこめ、夏なお肌寒さを感じさせます。
写真は養老町から提供
|
谷汲踊(揖斐川町)

約800年前、源平合戦の勝利を祝った武者踊から始まったと伝えられ、長さ4mの竹製で鳳凰の羽をかたどったシナイを背負い、胸には直径70cmの大太鼓を抱えて踊るもので、岐阜県重要無形民俗文化財第1号に指定されている。
写真は揖斐川町から提供
|
谷汲山華厳寺(揖斐川町)

平安時代初期、798年に創建。「たにぐみさん」の愛称で親しまれ、日本最古の巡礼業であり日本遺産に認定されている「西国三十三所」の最終霊場として、また願いが叶う「満願霊場」として愛される名刹で、桜や紅葉の名所でも知られる。
写真は揖斐川町から提供
|
|
|
お問合せ先
西濃用水第三期農業水利事業所工事課
(電話) 0584-84-2723
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。