5.農地の宿命【第3章「農」が造った国土】
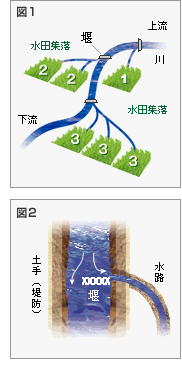 さて、以上のことを頭において、ある平野に水田を造るとしましょう。
さて、以上のことを頭において、ある平野に水田を造るとしましょう。
水田の水の多くは川から引いてくるので、川の近くにいくつかの農地や集落ができます(図1)。水路を引く場合、川の流れを木の枠組みや石などでせき止め、そこから田んぼへつながる水路へ水を送ります(図2)。この仕組みを堰(せき)といいます。
最初、1の集落(水田)が川から水を引いてきました。そうすると2の集落は、1の堰の下流から引くことになります。川の水を引くのは、上流のほうが有利になるからです。さらに3の集落は2の堰の下から引くことになります。こうやって川の水の量に余裕がある限り、水路が引かれ、水田が造られてていきます。
このようにして、その平野は、川から引ける水の量のギリギリまで開発されることになります。ところが、川の水量は常に変動します。雨が降れば水かさは増すし、日照りが続けばだんだん減ってきます。
さて、ここで集中豪雨が来たとします。たちまち川は濁流となって、堤防いっぱいまで水かさが増します。このとき、堰が頑丈であればあるほど、洪水は水路のほうへ流れてきます。むしろ、流されてしまうくらいの粗末な構造のほうが望ましいことになります。 昔の堤防はそれほど頑丈ではないので、水路を引いたところから崩れてきます。そして、こともあろうに自分達が苦労して掘った水路をつたって、洪水がおそいかかってくるのです。川のそばほど多くの集落がかたまっています。悲劇ですね。
今度は、日照りが続いたとします。川の水かさは日に日に減っていきます。上流の村はできるだけたくさん取ろうとします。すると、下流の村には全然水が流れてきません。日照り続きで、稲も弱ってきました。稲が枯れるということは、1年間の収入もゼロになるということを意味します。下手すれば、村中が全滅です。
さあ、皆さんならどうします? ・・・・上流の村に分けてもらう?いえいえ、上流も必死です。・・・水が余っているわけではないのです。
- 日本の地形の特徴
- 水路を引くむずかしさ
- なぜ日本は水田を求めたのか
- アジア・モンスーン ―地球10周分の水路網
- 農地の宿命
- 水争いと「農」の秩序
- 二次的自然の形成―琵琶湖40個分の湿地帯
- 江戸の水系社会
お問合せ先
農村振興部設計課
代表:048-600-0600









