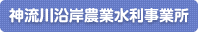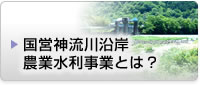2.みどころ 【地域情報】
間瀬堰堤
昭和12年に児玉町(現在の本庄市)小平を流れる間瀬川を間瀬堰堤(間瀬ダム)で堰き止め、児玉用水の貯水池として造られたものが間瀬湖(まぜこ)です。このダムは堰堤の高さ27.5m、延長126mの重力式ダムで、東日本に残る最古の農業用重力式ダムです。間瀬湖は県立上武自然公園の中にあり、新日本百景にその名を連ねています。また、ヘラブナ・ワカサギ釣りの名所として、また春には桜の名所としても有名です。
写真提供:本庄市
猪俣の百八燈
猪俣の百八燈(いのまたのひゃくはっとう)とは、毎年お盆の8月15日に、猪俣地区の18歳以下の若者たちが中心となって行われる伝統的な祭りです。高台院(猪俣)で準備を整えた提灯行列がゆっくりと堂前山に向かい、その尾根に築かれた百八基の塚に灯をともしていく様子はとても幻想的です。これは武蔵(むさし)武士として勇名を馳せた、猪俣党の棟梁・猪俣小平六範綱(いのまたこへいろくのりつな)とその一族の霊を慰めるための行事と伝えられています。猪俣小平六は、源義朝(みなもとのよしとも)に従った雄将として知られ、源頼朝にも仕えて戦場で功績をあげたとされています。
写真提供:美里町
七輿山古墳
七輿山古墳(ななこしやまこふん)は、6世紀前半につくられた三段構成の前方後円墳です。全長145m、幅106m、高さは16mにおよび、6世紀代の古墳としては東日本最大級の大きさで、昭和2年には国の重要文化財に指定されています。出土遺物は円筒・朝顔型円筒・人物・馬・盾などの埴輪(はにわ)類や須恵器(すえき)・土師器(はじき)があり、特に円筒埴輪は径50cm・高さ110cmに7条の凸帯(タガ)が巡る大型品で、全国でも稀なものです。七輿山の由来は羊太夫(ひつじたゆう)の伝説とされ、朝廷の討伐軍に追われた羊太夫の女房ら7人がここで自害したのを、それぞれ輿に乗せて葬ったので「七輿山」という名前が付けられたと伝えられています。
写真提供:藤岡市
お問合せ先
農村振興部設計課
ダイヤルイン:048-740-0541