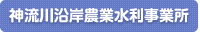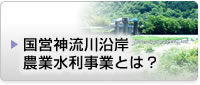1.近代までの開発【事業に至る経緯】
渇水と洪水の苦悩
神流川沿岸地域での農業の歴史は古く、700年前後には、すでに上真下(かみましも)、下真下(しもましも)、北堀などの条里水田のために、九郷(くごう)用水や真下大溝などのかんがい水路が開削されたとみられています。鎌倉時代には、坂東武士の勢力拡大の基盤となり、農地の開発に力が注がれましたが、大規模な水利事業が実現したのは、江戸時代に入ってからのことです。大都市江戸のお膝元として、それまで手付かずだった原野にも開発の手が及び、江戸時代の後半には、神流川には8つもの堰が築かれています。
このようにいくつもの堰が築かれ、水利開発が進んでいくと、同時に、取水に関する争いも増加していきました。特に、渇水の際には、激しい水争いが起こるようになり、明治に入ってからも、1877年、1881年、1884年、1888年と五年を置かず、激しい争いの記録が残っています。こうした状況は、大正、昭和に至っても続き、さらに流血を伴うような熾烈な紛争へと拡大していきます。
沿岸の人々を苦しめたのは、渇水時の水不足だけではありません。ひとたび豪雨に見舞われると、山間に降った雨は落差の激しい神流川を一気に流れ落ち、洪水を引き起こしました。沿岸では大氾濫が起こり、堰が流されるなどたいへんな被害を被りました。この被害も、昭和に入っても続き、その度に膨大な出費と労力が修復工事に費やされました。
- 近代までの開発
- 悲願の事業-国営埼玉北部農業水利事業
- 地域の農業と課題
お問合せ先
農村振興部設計課
ダイヤルイン:048-740-0541