2. 悲願の事業-国営埼玉北部農業水利事業【事業に至る経緯】
神流川筋6堰合口事業
昭和の初めには、江戸時代に8堰あった神流川の堰は、統合、廃止により、埼玉県の3カ所(九郷(くごう)用水、阿保領(あぼりょう)用水、五明用水)、群馬県の3カ所(牛田用水、根岸用水、神流用水)の6堰となっていました。
渇水時は、上流の3堰(九郷、阿保、牛田)では、かろうじて取水することができましたが、下流の3用水(五明、神流、根岸)では、表流水がほとんどなくなり、水をめぐる紛争は絶えませんでした。昭和5年7月15日の大干ばつの際には、長幡村(ながはたむら)、神流村の1,500名が神流川を挟んだ河原で石を投げ合い、負傷者を出す大乱闘となっています(神流川の石合戦)。後には、埼玉県、群馬県両知事間の紛争にも発展しましたが、ようやく農水省の仲裁案に基づき埼玉県側77.5%、群馬県川22.5%の水量割合を決定し、6つの堰をひとつにまとめる神流川合口堰の建設が動き出しました。これが埼玉県の行った神流川筋合口用水改良事業です。工事は10年の歳月を経て完了し、1955年、現神流川頭首工が完成しました。
しかし、もともとの水源が乏しい上、河床の低下も重なって、この事業でも根本的な用水不足を解消するには至らず、その後も幾度となく水争いは起こりました。
国営埼玉北部農業水利事業
1957年、建設省により、利根川総合開発計画の一環として、神流川上流に大規模な多目的ダム(現在の下久保(しもくぼ)ダム)の開発が企画されます。その目的は、東京都の水道用水の確保、洪水調整、流域の農業用水の取水の安定を図ることにありました。水不足の解消はもちろん、洪水対策の面からも、神流川の持っていた地形的宿命が克服されることになります。
農水省はこのダムを水源とする農業開発計画を調査、1967年には、待望の国営埼玉北部農業水利事業が着手され、1980年に用水施設(受益面積は水田2,789ha、畑地かんがい1,229ha)が完成しました。
この事業により、神流川頭首工の改修、機能アップと新神流川幹線、上里幹線、児玉幹線の総延長26kmの用水路、サイホンなどの主要設備が整備され、ようやく用水の安定的供給が実現されました。
神流川で最初に水争いの調停が行われたのは、江戸時代の1717年のことだと言われています。以来、実に260有余年に及ぶ水との苦闘の歴史に、終に幕が下ろされました。

下久保ダム
事業実施年度
昭和42年(1967)10月~昭和55年(1980)9月
許可水量
秒速13.668立方メートル(13.668m3/sec)
地域
埼玉県本庄市・旧児玉町(現本庄市)・上里町・旧岡部町(現深谷市)・神川町・美里町・群馬県藤岡市(旧2市5町、現在は合併により3市3町)
水源・取水施設
|
事業実施年度 |
水量 |
高さ |
幅 |
|
|
神流川頭首工 |
昭和19年~29年 |
(取水量) 13.68m3/sec |
112.6m |
|
|
下久保ダム |
昭和34年~43年 |
(貯水量) 1億2千万m3 |
129m |
598.2m |
主要工事
(1)頭首工
|
施設名 |
堰長 |
取水量 |
主要構造 |
|
神流川頭首工 |
95.3m |
13.68m3/sec |
土砂吐(2門)、取水水門(4門)の新設 |
(2)用水路
|
施設名 |
延長 |
通水量 |
主要構造 |
|
新神流川幹線 |
2.4km |
7.6m3/sec |
コンクリートライニング |
|
上里幹線 |
16.6km |
5.1m3/sec |
コンクリートライニング及びパイプ |
|
児玉幹線 |
6.9km |
2.5m3/sec |
コンクリートライニング及びパイプ |
さらに詳しく |
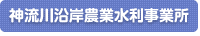
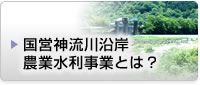




お問合せ先
農村振興部設計課
ダイヤルイン:048-740-0541




