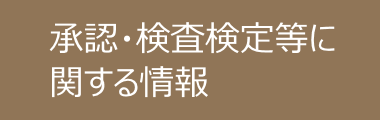動物用医薬品の添付文書の記載要領に関するQ&A
|
本Q&Aは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務の取扱いについて」(平成12年3月31日付け12動薬A第418号農林水産省動物医薬品検査所長通知)の別添15の「動物用医薬品の添付文書の記載要領」に関する照会事項の中で共通する内容をまとめたものです。本Q&Aに含まれていない事項について不明な点がある場合は、個別に照会してください。 |
Q2:既承認の品目の添付文書について、いつまでに添付文書の記載要領に沿って改訂すればよいか。
Q3:添付文書の記載要領の項目のうち、製品によっては記載できない項目(後発品の「薬理学的情報等」等)があるが、それらについて記載を省略してよいか。
Q4:動物用医薬品の容器又は被包に添付文書等記載事項を記載しているものについて、どのような例外的な記載が認められるのか。
Q6:最新の承認指令書番号を記載することについて、製造販売承認事項変更承認申請が承認された場合、即座に書き換える必要があるか。
Q7:販売開始年月を記載することについて、新規で承認された動物用医薬品については、添付文書の発注時点では販売時期が未定で、記載することができない場合がある。この項目の記載は必須か。
Q8:再審査結果公表年月を記載することについて、再審査の対象品目でない場合は、記載しないことでよいか。(平成29年4月11日改)
Q9:指定医薬品である場合は「指定医薬品」と記載することとされている一方で、動物用医薬品協会の通知では四角囲みで「指定」と記載することとされている。どちらに従って記載すればよいか。
Q10:一般的名称を記載することについて、動物用生物学的製剤基準に収載される前の一般的名称のないワクチンの品名の下に、動物用生物学的製剤検定基準に収載された名称を記載してもよいか。
Q11:薬理学的情報等を記載することについて、公表できる情報がない場合には空欄とすることでよいか。
Q12:「製品情報のお問い合わせ先」及び「製造販売元」を記載することについて、両方が同じ場合は、片方のみを記載することでよいか。
Q13:保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止のための報告に関して記載することについて、動物に直接的及び間接的に暴露しない製品についても本記載が必要か。
Q14:既承認の品目の使用上の注意を使用上の注意の記載要領に沿って整備する場合、使用上の注意の変更届が必要か。
Q15:既承認の品目の使用上の注意を使用上の注意の記載要領に沿って整備した際、添付文書等記載事項変更届出書を提出する必要があるか。
Q16:既承認の品目の使用上の注意を使用上の注意の記載要領に沿って整備する場合、どのような点に留意すればよいか。
Q17:既承認の品目の使用上の注意を使用上の注意の記載要領に沿って整備する際に、どの項目に分類すべきか判断に迷う場合、その部署に相談すればよいか。
Q18:今後申請する品目の使用上の注意について、使用上の注意の記載要領に沿っていない内容で申請することは可能か。
Q19:新規で承認申請し、審査中の品目について、どの時点で使用上の注意の記載要領に沿った使用上の注意に整備すればよいか。
Q20:既承認の製品の使用上の注意について、いつまでに使用上の注意の記載要領に沿って整備すればよいか。
Q21:使用上の注意の記載要領の項目のうち、製品によっては記載できない項目(類型Aに該当する製品の専門的事項等)があるが、それらについて記載を省略してよいか。
Q22:後発品の使用上の注意について、先発品よりも先に使用上の注意の記載要領に沿って整備してもよいか。
Q23:既承認の製品の一物多名称製品を申請する場合、申請する製品の使用上の注意は使用上の注意の記載要領に沿って記載する必要があるか。
|
【用語の定義】 法:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) 所長通知:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務の取扱いについて(平成12年3月31日付け12動薬A第418号農林水産省動物医薬品検査所長通知) 添付文書等:法第52条第1項で定められた添付文書等 添付文書等記載事項:法第52条第1項で定められた添付文書等記載事項 添付文書の記載要領:所長通知の別添15の「動物用医薬品の添付文書の記載要領」 使用上の注意:法第52条第1項第1号で定められた使用及び取扱い上の必要な注意 使用上の注意の記載要領:添付文書記載要領の別紙3の「動物用医薬品の添付文書における使用上の注意の記載要領」 使用上の注意の変更届:所長通知の12の(1)のアに基づき、所長通知の別記様式16により提出する「使用上の注意の変更について」の書類 |
【法第52条の2第1項、法第63条の3第1項及び法第65条の4第1項関係】(添付文書等記載事項の届出等)
Q1:添付文書の記載要領の対象となる品目は何か。
全ての動物用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)について、今後作成される添付文書に適用します。原則として、体外診断用医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品についても適用しますが、人用の記載要領がある場合には、それに沿って整備することでも差し支えありません。
また、添付文書の代わりに動物用医薬品の容器又は被包に添付文書等記載事項を記載する動物用医薬品についても適用しますが、記載面積の都合等により本要領に従って記載することが困難である場合は、この限りとはしません。
Q2:既承認の品目の添付文書について、いつまでに添付文書の記載要領に従って改訂すればよいか。
添付文書に記載されている事項を変更した場合、添付文書の在庫がなくなった場合等により新たに添付文書の印刷を発注する際に改訂してください。なお、大量に在庫がある場合であっても、平成29年9月末日までを目途に改訂するよう努めてください。
Q3:添付文書の記載要領の項目のうち、製品によっては記載できない項目(後発品の「薬理学的情報等」等)があるが、それらについて記載を省略してよいか。
差し支えありません。なお、この場合、省略する項目を立てる必要もありません。
Q4:動物用医薬品の容器又は被包に添付文書等記載事項を記載しているものについて、どのような例外的な記載が認められるのか。
薬理学的情報等の項目に自社のURLを記載し、そこに薬理学的情報等を掲載する場合は例外として認められます。これ以外は、程度によるため、容器又は被包の案を提示して個別に相談してください。なお、新規で承認を取得した動物用医薬品については、添付文書を添付することを検討してください。
Q5:承認指令書番号を記載することについて、新規で申請した動物用医薬品については、承認されるまで当該番号を知ることができない。承認後、すぐに製造販売できるようあらかじめ添付文書を準備する都合上、あらかじめ承認指令書番号を知らせてほしい。
承認指令書番号をあらかじめお知らせすることはできません。なお、承認されるまでの間に添付文書の記載要領の項目にどのような変更があるかわからないことから、承認されてから添付文書を準備した方がよいと考えます。
承認されるまでの間に添付文書を発注されるのであれば、必ずしも承認指令書番号を記載する必要はありませんが、発注数量を必要最小限とし、承認指令書番号を記載した次の版を遅滞なく添付するなど工夫してください。
Q6:最新の承認指令書番号を記載することについて、製造販売承認事項変更承認申請が承認された場合、即座に書き換える必要があるか。
この場合、次に添付文書を発注する際に、その時点における最新の承認指令書番号を記載することで差し支えありません。
Q7:販売開始年月を記載することについて、新規で承認された動物用医薬品については、添付文書の発注時点では販売時期が未定で、記載することができない場合がある。この項目の記載は必須か。
この場合、販売開始年月を記載する必要はありません。添付文書を新たに発注する際に追加してください。
Q8:再審査結果公表年月を記載することについて、再審査の対象品目でない場合は、記載しないことでよいか。
再審査の対象とならない動物用医薬部外品のような規制区分の品目や先発品が再審査を受けていることから再審査を受けていない後発品については、再審査結果公表年月を記載する必要はありません。
なお、後発品の添付文書において、先発品の再審査結果公表年月を記載しているものについては、添付文書の切り替え時に修正することで差し支えありません。
(平成29年4月11日改)
Q9:指定医薬品である場合は「指定医薬品」と記載することとされている一方で、動物用医薬品協会の通知では四角囲みで「指定」と記載することとされている。どちらに従って記載すればよいか。
どちらの記載でもかまいません。
Q10:一般的名称を記載することについて、動物用生物学的製剤基準に収載される前の一般的名称のないワクチンの品名の下に、動物用生物学的製剤検定基準に収載された名称を記載してもよいか。
差し支えありません。
Q11:薬理学的情報等を記載することについて、公表できる情報がない場合には空欄とすることでよいか。
本欄に記載する事項がない場合は、項目を作る必要はありません。
Q12:「製品情報のお問い合わせ先」及び「製造販売元」を記載することについて、両方が同じ場合は、片方のみを記載することでよいか。
「製品情報のお問い合わせ先・製造販売元」のように、両者を統合して記載することで差し支えありません。
Q13:保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止のための報告に関して記載することについて、動物に直接的及び間接的に暴露しない製品についても本記載が必要か。
この記載は、副作用に限って報告を求めるものではありません。したがって、動物に直接的及び間接的に曝露しない製品についても本記載が必要です。
【使用上の注意の記載要領関係】
Q14:既承認の品目の使用上の注意を使用上の注意の記載要領に沿って整備する場合、使用上の注意の変更届が必要か。
使用上の注意の変更届が必要です。なお、通常、使用上の注意の変更届には新旧対照表を添付していただいているところですが、本文を全面的に改訂する場合は、必ずしも新旧対照表の形式ではなく、旧本文の全文と新本文の全文を添付することでも差し支えありません。この場合、変更箇所に下線を引く必要はありませんが、届出書の参考事項欄に全面改訂である旨をことがわかるようにしてください。
Q15:既承認の品目の使用上の注意を使用上の注意の記載要領に沿って整備した際、添付文書等記載事項変更届出書を提出する必要があるか。
要指示医薬品、高度管理医療機器及び再生医療等製品について整備した場合は、必要です。届け出る時期については、「添付文書等記載事項の届出に関するQ&A」のQ3を参照してください。
Q16:既承認の品目の使用上の注意を使用上の注意の記載要領に沿って整備する場合、どのような点に留意すればよいか。
既存の使用上の注意を「基本的事項」と「専門的事項」に分類してください。その後、使用上の注意の記載要領に基づいて更に細分化してください。この際、「専門的事項」は獣医師等の専門的知識を有する者が、「基本的事項」はそれ以外の者が読むことを意識して使用する用語や情報量等に配慮してください。
同じ使用上の注意であっても、製品によって読むであろう者が異なると考えられる事項については、「基本的事項」と「専門的事項」のどちらに区分するか十分に検討してください。具体的には、例えば、注射部位の特定に関する注意事項は、牛用の製品であれば獣医師等が投与することが想定されることから「専門的事項」に、豚や鶏用の製品であれば飼養者が投与することが想定されることから「基本的事項」に記載することが適切であると考えます。
Q17:既承認の品目の使用上の注意を使用上の注意の記載要領に沿って整備する際に、どの項目に分類すべきか判断に迷う場合、その部署に相談すればよいか。
使用上の注意の記載要領の本文に加え、既に要領に沿って整備された同種の製品の使用上の注意や添付文書の記載要領の別紙1のひな型を参考にしても使用上の注意の分類を判断することができない場合は、審査調整課の担当者へ照会してください。ただし、この場合、各製品について照会するのではなく、代表的な製品について照会してください。
Q18:今後申請する品目の使用上の注意について、使用上の注意の記載要領に沿っていない内容で申請することは可能か。
新たに申請する品目については、使用上の注意の記載要領に沿った内容で申請してください。沿っていない内容で申請された場合、申請書は受理しますが、指摘事項、差し替え等の際に使用上の注意の記載要領に沿った内容に整備していただきます。
Q19:新規で承認申請し、審査中の品目について、どの時点で使用上の注意の記載要領に沿った使用上の注意に整備すればよいか。
指摘事項のやりとりがある場合はその回答の際に、ない場合は最終差し替えの際にそれぞれ整備してください。
ただし、特段の事情がある場合は、使用上の注意の記載要領に沿っていない内容で承認し、承認後から最初の製造販売までの間に使用上の注意の変更届により整備することでも差し支えありません。なお、要指示医薬品、高度管理医療機器又は再生医療等製品にこれを適用する場合は、最初の製造販売の前に添付文書等記載事項届出書(添付文書等記載事項変更届出書ではありません。)を提出してください。
Q20:既承認の製品の使用上の注意について、いつまでに使用上の注意の記載要領に沿って整備すればよいか。
使用上の注意以外の添付文書に記載されている事項を変更した場合、添付文書の在庫がなくなった場合等により新たに添付文書の印刷を発注する際に、製造販売承認事項変更承認申請又は使用上の注意の変更届により整備してください。なお、大量に在庫がある場合であっても、平成29年9月末日までを目途に整備するよう努めてください。
Q21:使用上の注意の記載要領の項目のうち、製品によっては記載できない項目(類型Aに該当する製品の専門的事項等)があるが、それらについて記載を省略してよいか。
差し支えありません。なお、この場合、省略する項目を立てる必要もありません。
Q22:後発品の使用上の注意について、先発品よりも先に使用上の注意の記載要領に沿って整備してもよいか。
差し支えありません。
Q23:既承認の製品の一物多名称製品を申請する場合、申請する製品の使用上の注意は使用上の注意の記載要領に沿って記載する必要があるか。
既承認の製品の使用上の注意を同一の内容としてください。その後、同時期に、製造販売承認事項変更承認申請又は使用上の注意の変更届により使用上の注意の記載要領に沿った内容に整備してください。