2.武蔵七党の活躍【「農」と歴史】
中世の歴史
やがて鎌倉幕府が成立すると、武蔵国(むさしのくに)を中心とする坂東の地は、幕府の分国として位置づけされ、幕府を支える米倉・財源として重要視されました。この地域には、平安時代末期におこった武蔵七党と呼ばれる集団が活躍しており、やがて、坂東武士として勢力を拡げ、経済基盤の強化のために農地の開発に力を注いでいくことになります。
鎌倉時代は、全国的に農業技術が進み、牛馬による耕作、米麦の二毛作も広まった時代です。この地域でも、当時、武蔵野と呼ばれていた原野の開拓も始まりました。武蔵国の農地面積の推移を見てみると、平安時代の『倭名称(わみょうしょう)』では36,690町歩、鎌倉時代末期の『拾芥抄(じゅうかいしょう)』では51,540町歩、安土桃山時代の太閤検地では51,315町となっており、中世の前半に約15,000町歩の開発が進んだことがわかります。
また、もう一つ注目すべきこととして、鎌倉街道の交通路が整備されたことが挙げられます。街道の開通によって、宿場ができ、物資の交易のための貨幣経済が発達したことで、街道沿いに出現した一大消費地に農産物を供給することが求められるようになりました。これも開発が進んだ大きな要因と言えるでしょう。
金鑚神社(かなさなじんじゃ)
武蔵国内で氷川神社とならぶ格式の高い神社で児玉党一族の崇敬を受けていました。本殿を持たず、拝殿の奥の山全体がご神体となっています。
畑地の発達
中世の各国の年貢品目を見ると、近畿、山陽をはじめとする西日本では、米が主でしたが、武蔵(むさし)、上野(こうずけ)、下野(しもつけ)、下総(しもうさ)、常陸(ひたち)の利根川流域5ヶ国では、絹や布が多くを占めています。利根川を始めとした大小河川の乱流、都からの距離が遠く、進んだ文化や技術が伝わりにくいという地理的条件、洪積台地が広く分布する地形、こういった条件から、関東は稲作より、むしろ山間地域を中心とした畑作農業に適していた地域だったと言えるのかもしれません。
しかし、江戸に幕府が開かれ、人口が急増すると、関東地方一帯でも、水田の開発が積極的に行われていくことになります。
さらに詳しく |
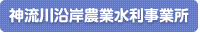




- 「くに」の成立
- 武蔵七党の活躍
- 近世の開拓と水をめぐる混乱
- 明治の苦闘と近代産業の影響

お問合せ先
農村振興部設計課
ダイヤルイン:048-740-0541




