4.水を分ける
一本の水路から運ばれてきた水を、3つの集落に分けるとします。各集落は大きさもまちまちであり、仮に水田の広さが3:2:1だったとします。そうすると水田に必要な水の量も3:2:1となります。現在は、分水工という水利施設で正確に分けられますが、昔は水の位置エネルギーだけで分けました。
最も多く見られるのは、右の図にあるように、水路を断面の大きさで分ける方法です。これなら工法も簡単であり、誰が見ても公平に分けられるように思えます。
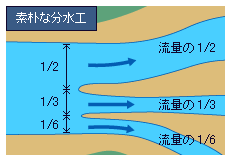 しかし、そうでもありません。水は位置エネルギーによって流れるので、流量は3つの集落(水田)の標高差によって変わってきます。集落への勾配が大きい水路ほどたくさんの水が流れ込むことになります。つまり、3集落への距離と標高差によって流れ込む水の量(速度)が変わってくるのです。また、分水後の水路の構造(特に断面が滑らかかどうか)によっても流量は変わってきます。
しかし、そうでもありません。水は位置エネルギーによって流れるので、流量は3つの集落(水田)の標高差によって変わってきます。集落への勾配が大きい水路ほどたくさんの水が流れ込むことになります。つまり、3集落への距離と標高差によって流れ込む水の量(速度)が変わってくるのです。また、分水後の水路の構造(特に断面が滑らかかどうか)によっても流量は変わってきます。
3つの集落とも分水工から同じ距離で同じ標高に位置していれば、この分水方式は理にかなっているのですが、そんな理想的な集落はなかなかありません。したがって、どれくらいの断面で分けたらいいのかは、たいへんな計算と工夫が必要でした。極端なことを言えば、この分水工の前に、石をひとつ置いただけで流量は変わってきます(実際にそうした方法がとられ、水争いの元となりました)。
 |
|
東金分水工 (千葉県東金市)
写真提供 : 両総土地改良区 |
この欠点を解消したのが、右の写真の円筒分水工です。下の穴からあふれ出た水が、水平に仕切られた断面で分配され、各水路の分だけ流れ落ちます。この先の水路の勾配が急であろうが緩かろうが、構造がどうなっていようと、この分配方式であれば一切影響を受けません。この円筒分水工だけで位置エネルギーによる水の分配は完結しているのです。誰が考案したのは不明ですが、なかなかのスグレモノですね。
では、こうした用水ができる前、関東地方の水田は、どのように水を手当てしていたのでしょうか。
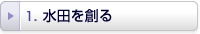


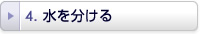

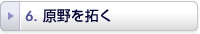

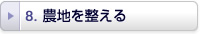
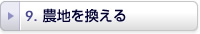

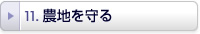
お問合せ先
農村振興部設計課
ダイヤルイン:048-600-0600




