2.水を取る
通常、川はその土地の一番低いところを流れています(天井川は例外)。したがって、川から水路に水を引こうとすれば、川の水位を水路より上にしないと水路には水が流れてきません。つまり、川の水位を高くして水路へ流れ込むように川をせき止めます。すると、せき止めたところは水位が上がります。そこから水を水路へ落とすというわけです。
 |
| 六堰頭首工(総合農地防災事業大里地区) 写真提供:埼玉県農林部大里農林振興センター |
この川をせき止める構造物は堰(せき)と呼ばれています。堰はその構造物の単体を示すこともあれば、「拾ヶ堰」「矢原堰」といったように水路全体を示す場合もあります。つまり、堰と用水は一体的なものなのです。
この堰は、洪水でも流されないような石垣で造ってもいいのですが、そうすると、洪水の時には水路をつたって洪水が水田まで流れこんできます。したがって、この堰の構造は様々な工夫がなされてきました。多くの堰は、川の底に丸太を打ち込んで屋根のような形を造り、そのスキマを草や小枝でふさぐという構造でした。これだと洪水の時には、草や小枝は流されてしまいます。また、そのスキマから流れる水は下流の堰で取り入れます。
この構造は一見稚拙(ちせつ)なようにも見えますが、実によく考えられており、現代の頭首工(堰)が誕生するまで、ほとんどの堰はこうした構造でした。しかし、洪水のたびに流されてしまい、その修復には多大な労力と費用を要しました。
現代の頭首工(堰)の多くは鉄製のゲートを上げ下げして水位を調節しています。
さあ、こうして川から取った水を、今度は何十kmも下流の集落まで運ばなければなりません。
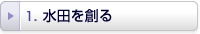


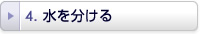

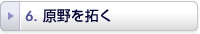

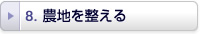
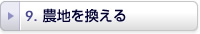

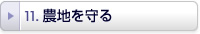
お問合せ先
農村振興部設計課
ダイヤルイン:048-600-0600




