5.水を溜める
千葉県の九十九里平野のように大きな川に恵まれないところでは、ため池に頼らざるを得ませんでした。上総台地の麓周辺には雄蛇が池、八鶴湖、小中池など多くのため池があり、また、砂丘の間にあった沼などもため池代わりに使っていました。
ため池は山や台地のくぼ地を利用したものが多いのですが、平野部でも見られます。特に奈良県には「皿池」と呼ばれる四方を土手で囲ったため池が多く見られます。関東平野にもありました。江戸時代の初期まで、埼玉県の川口市とさいたま市にまたがる広大な沼地がありました。幕府の関東郡代・伊奈忠治はそこに約900mの堤を築いて「見沼溜井(みぬまためい)」というため池を造りました。この見沼溜井は下流の水田約5,000haを潤したという巨大なため池でした。やがて、利根川に堰を築いて水路にしたのが見沼代用水、つまり、見沼溜井の代わりの用水というわけです。
 |
| 深山ダム(那須野原総合開発事業) |
ところで、ため池とダムはどこが違うのでしょうか。ダムといっても発電ダムや治水ダムもありますが、農業用ダムに限って言えば、両者に違いはありません。ただ、水をせき止めている堤(つつみ)の高さが15m未満のものをため池と呼んで区別しているだけです。
では、ため池と普通の池や沼とはどこが違うのでしょうか。
ため池は、水さえ溜めればいいというわけにはいきません。堰と同じように、そこから農地まで水路を引いてこなければならない。ということは、農地よりも高いところに造らなければならないということになります。さらに、ため池から水を抜く構造が必要になります。10mも水が溜まると水圧はかなりなものとなります。木製の取水口を人の手で開け閉めするわけですから、その構造には高い技術が要求されました。
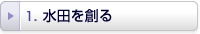


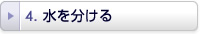

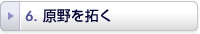

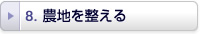
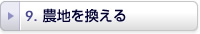

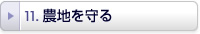
お問合せ先
農村振興部設計課
ダイヤルイン:048-600-0600




