8.農地を整える
 どれだけ水路を築き、原野を開拓し、海や湖沼を干拓しても、国土の広さには限りがあります。また、新しい農地を拓くには莫大な労力と資金が必要になります。
どれだけ水路を築き、原野を開拓し、海や湖沼を干拓しても、国土の広さには限りがあります。また、新しい農地を拓くには莫大な労力と資金が必要になります。農地の広さを変えずに生産性を高めるためには、品種の改良や農業技術の進歩が必要になってきます。とりわけ、近年の機械化により農業労働は大幅に軽減され、生産性も飛躍的に向上しました。
しかし、その機械化農業を効率的に行うためには、農地もそれに合わせた形に整えなければなりません。いくら性能の良い大型田植え機を使っても、農地が小さかったり分散したりしていては、かえって移動する手間のほうが大きくなってしまいます。
こうした必要性が高まってきたのは明治時代でした。明治になると、農地は農民の所有となり、年貢も廃止されて、その代わり地代を納めることになります。当然のことながら農民の生産意欲が高まり、様々な農業技術が発展することになります。
その代表は、「乾田馬耕(かんでんばこう)」と呼ばれる馬を使った農法でした。水田の水を抜き(排水改良)、馬に大きな犂(すき)を引かせて耕すためには、農地の排水改良や区画を整えることが何よりも重要になってきます。
明治20年代に行われたのが「田区改正」で、耕地の整形・交換を行うと同時に排水改良を行うという、現代の「ほ場整備」とよく似た工法です。
明治の初期、静岡県であぜ道や道路を直線化したのが近代的な田区改正の発端であると言われています。一方、西欧の土地整理法を模範とし、政府の奨励により進められたのが、石川県で行なわれていた「石川式」田区改正です。
この「静岡式」「石川式」の田区改正は近代的営農の第1歩として全国に広まり、やがて、明治32年に法制化される「耕地整理」へと発展していくことになります。土地改良は、学術面からは「農業土木」といわれていますが、実は、この農業土木学の誕生は、東京帝国大学における上野英三郎博士の「耕地整理技術」に始まるのです。
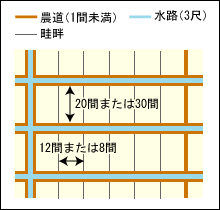 |
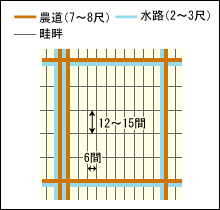 |
| 石川式 | 静岡式 |

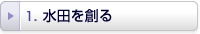


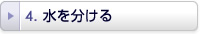

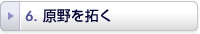

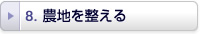
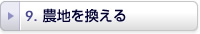

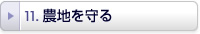
お問合せ先
農村振興部設計課
ダイヤルイン:048-600-0600




