6.原野を拓く
 原野を拓(ひら)いて農地を造る場合には、上で述べてきたような水路を引く工事が伴いました。しかし、近世までには、農地のできる場所はほとんど開発され尽くしていました。明治以降の農用地開発は、これまで水の行き届かなかった台地や高原のような場所に目が向けられました。必然的に国家予算を投じた大規模な事業となります。
原野を拓(ひら)いて農地を造る場合には、上で述べてきたような水路を引く工事が伴いました。しかし、近世までには、農地のできる場所はほとんど開発され尽くしていました。明治以降の農用地開発は、これまで水の行き届かなかった台地や高原のような場所に目が向けられました。必然的に国家予算を投じた大規模な事業となります。
明治以降、水路によって拓かれた代表的な例としては、まず安積疏水が挙げられます。現在の福島県郡山市は当時人口七千人程度の宿場町でした。付近の台地数千haは水がないため古来一度も耕されたことのない原野でした。明治の元勲・大久保利通などの尽力によって完成した安積疏水(猪苗代湖から導水)によって、郡山は人口34万人の大都市にまで発展しました。栃木県の那須疏水(※)も約4万haという荒野が国営事業によって県下最大の穀倉地帯に変貌した例です。
北海道の開拓はあまりにも有名です。他に、青森県の三本木原の開拓(十和田市の誕生)、明治用水(日本のデンマークといわれた安城市の誕生)など、水路一本によって広大な荒地が穀倉地帯に変貌した例は数多くあります。
関東平野では、明治初期、士族授産事業として始まった
静岡藩の旧幕臣による牧之原の開墾(静岡県、明治2年)
佐倉藩士族の結社同協社による印旛郡の開墾(千葉県、明治4年)
静岡藩士族による三方原の開墾(静岡県、同9年)
また、政府の依頼を受けた商人のプロジェクトであった八街市や冨里市の開拓が知られています。
那須疏水は、安積疏水(福島県郡山市とその周辺地域)、琵琶湖疏水(滋賀県琵琶湖-京都市)と並び、日本三大疏水の一つに数えられる用水路です。栃木県北部に広がる広大な扇状地「那須野ヶ原」に那珂川の水を引き入れるため、明治18年に造られました。それまでは一面荒地だった那須野ヶ原は、この用水によって県内有数の農業地帯に生まれ変わっています。
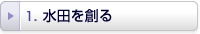


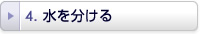

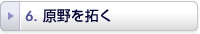

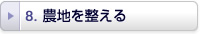
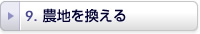

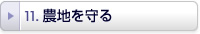
お問合せ先
農村振興部設計課
ダイヤルイン:048-600-0600




