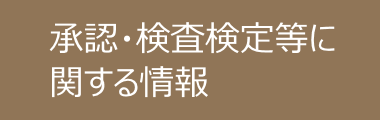5. 動物用生物学的製剤
・ VICH GL50R,55(特定動物試験省略)関係
| 所長通知の別添2の「5-4動物用不活化ワクチンの対象動物バッチ安全試験省略要件」(以下答24-1から答24-4において「VICH GL50R」という。)で定義されている「バッチ」とは、動物用生物学的製剤基準で定義されている「ロット」と同じか。 |
|
| 日本の動生剤基準では、「一つの最終バルクに由来する小分け製品の一群」を1ロットと規定していますが、VICH GL50Rでは「均一であると予期し得る1回のプロセス又は連続したプロセスで加工された出発材料、包装資材又は製品の規定量」を1バッチと定義しています。 別添(PDF:106KB) に示すパターンAやBの製造である場合、1バッチと1ロットは同義といえます。 しかし、別添に示すパターンCの場合は、最終バルクに由来する小分け製品としては日本でいうところの3ロットに該当しますが、最初の培養は1回のみであり均一ですので、 VICH GL50Rの定義では、1バッチに該当することとなります。 したがって、パターンCのような方式で製造を行う場合、最初の培養工程10バッチに由来する最終小分け製品での対象動物安全試験が必要になります。 |
|
| VICH GL50Rは動物用不活化ワクチンが対象とされていますが、トキソイドワクチンやコンポーネントワクチンも対象か。 |
|
| トキソイドワクチンやコンポーネントワク チンも対象です。 |
|
| VICH GL50Rの2の(3)のアの「安全性の点で危険性を内在する製剤」とは具体的にどのような製剤か。 |
|
| 例えば、グラム陰性細菌を主成分とする不活化ワクチンのように、野外で重篤な副作用が発生する危惧があるものは慎重に判断する必要があるかも しれません。 また、製造経歴において、対象動物バッチ安全試験で不適合になった経験のある製品や、対象動物バッチ安全試験を実施することが製品の安全性確保の大きな割合を占めていると推測される製品については、慎重な判断が必要になると思われます。 |
|
| VICH GL50Rの2の(3)のアで対象動物バッチ安全性の再実施が必要となる場合として例示されている「製造工程の重要な変更」とは具体的にどのような変更か。 |
|
| 添加物の成分量又は規格の変更、培養条件 の変更、濃縮・精製工程の変更、不活化方法の変更など、小分製品の組成又は不純物プロファイルが変化 する変更が行われた場合に該当するものがあるかもしれません。 したがって、製造工程の変更を行う際は、その変更による製品の安全性への影響を十分検討する必要があります。 |
|
| 所長通知の1の (3) のアの (ア) の対象動物を用いる安全試験には、鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチンの小分製品の規格及び検査方法に規定される「免疫抑制否定試験」は含まれるのか。 |
|
| 「免疫抑制否定試験」は鶏伝染性ファブリキウス嚢病の製造用株の安全性を確認する目的の試験であることから、特定動物試験省略の条件を満たす場合は当該試験を省略して差し支えありません。ただし、動生剤基準のシードロット規格には同主旨の規格が含まれないことから、省略する場合はマスターシードウイルスの規格に、下記例にならい、新たに免疫抑制否定試験を設定してください。なお、実際の試験法についてはマスターシードウイルスの更新の際に試験法の妥当性を検討のうえ規定することとし、その旨を新旧対照表の備考欄に記載してください。 (例)対象動物を用いた免疫抑制否定試験:動生剤基準の「鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン(ひな用中等毒)(シード)」の免疫抑制否定試験を準用して試験するとき、適合しなければならない。 |
|
| シードロット製剤として承認された製品と製造方法が同じ製品が既に外国で販売されている場合、特定動物試験の省略のための製造販売承認事項変更承認申請において外国で販売された製品の製造記録を使用することは可能か。 また、製造販売承認申請において外国で販売された製品の製造記録を使用することにより所長通知の1の(3)のアの特定動物試験を省略することは可能か。 |
|
| シードロット製剤における特定動物試験の省略に係る製造販売承認事項変更承認申請において、外国で承認され、販売されている製品の製造記録を使用することが可能な場合は、当該製造販売承認事項変更承認申請された製品と外国で承認され、販売されている製品の製造方法が同一であることを示すことができる場合に限られます。 また、製造販売承認申請において、所長通知の1の(3)のアの特定動物試験を省略することが可能な場合は、当該申請製剤と外国で製造され、販売されている製品の製造方法が同一であることを示すことができ、所長通知の1の(3)のウの(イ)に準じた添付資料を提出できる場合に限られます。 なお、外国の承認申請書において、我が国の製造販売承認申請書の規格及び検査方法で設定している試験が設定されていない場合であっても、我が国で設定されている規格及び検査方法の試験成績を提出する必要があることにご留意ください。 |
|
| 混合製剤の「バッチ」はどのように数えればよいか。また、すべての成分が所長通知の1の(3)のイのバッチ数を満たす必要があるか。 |
|
| 混合製剤の各成分について、上記に示した単味製剤の1バッチの考え方を基にして数え、すべての成分が所長通知の1の(3)のイのバッチ数を満たすようにしてください。 ただし、混合製剤の一部の成分が所長通知の1の(3)のイのバッチ数に満たない場合であっても、次の(ア)から(ウ)を満たす場合には、特定動物試験の省略のための製造販売承認事項変更承認申請をすることは可能です。 (ア) 少なくとも一成分の原液が10バッチを満たしていること (イ) 他の成分の原液が少なくとも複数バッチであること(1回以上更新されていること) (ウ) (ア)及び(イ)であっても、原液のバッチごとの品質の均一性、並びに小分製品のバッチごとの品質、有効性及び安全性の均一性が科学的に説明できること。 |